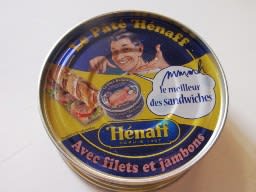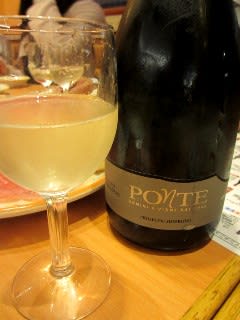東京ビッグサイトで「ワイン&グルメジャパン2015」が開催された先週、同展示会を主催するケルンメッセ株式会社と、ワイン誌「ワイン王国」を発行する株式会社ワイン王国の共催で、
「Night of Wine」というイベントがホテル日航東京で行われました(4月16日)。
その内容は、
カリスマ経営者、ソムリエが、「ちょいプレワイン」と「2015 ワイントレンドを占う!」という2つのテーマで語り合うパネルディスカッション。

パネリスト 左から)
藤森 真氏、遠藤 誠氏、丸山 宏人氏、中島 大輔氏
藤森 真氏
「VINOSITY」、「VINOSITY magis」、「VINOSITY maxime」オーナー
遠藤 誠氏
「遠藤利三郎商店」、「神泉遠藤利三郎商店」、「角打ワイン利三郎」オーナー
丸山 宏人氏
オザミワールド株式会社 代表取締役
中島 大輔氏
株式会社ワルツ マルゴグループ 丸の内エリアマネージャー
飲食業界では知らない人がいない著名な店の経営者、ソムリエの4氏がパネラーで登場。
藤森氏を司会進行役に、熱いトークが繰り広げられました。
各氏のトークは入り混じっていましたが、語った内容を個別に書き出してみます。
 ちょいプレワイン
ちょいプレワイン
ミドルレンジのワインが売れていない?
2500円以上のミドルレンジのワインを伸ばして、市場を活性化しよう、ワインの裾野を広げよう!というのが最初のテーマ。
中島氏
マルゴの各店舗では毎月何かしらのフェアがある。デイリーよりも少しアッパーレンジのワインをなるべく飲んでいただこうと、毎月提案している。店舗にもよるが、通常のグラスワイン20種、フェア用のスポットで3、4種類を追加。
普段よりもちょっといいワインを売るには、スタッフがどれだけ説明できるか?が重要。少し高いかなと思われるワインも提案するが、オススメポイントをきっちり説明し、お客様に満足してもらい、リピートに繋げるようにしている。結果、実際にリピートがある。
客も市場価格を知っているから、ただ出すだけではダメで、スタッフがきちんと飲み、客に近い目線で説明している。
丸山氏
店で一番売れているのがミドルレンジ。スタッフが本当においしいと思っているワインがこのレンジに多い。名前がないが、美味しくてコスパ高いものが揃っている。
19年間、グラスワインは600円から2000円のレンジの価格帯を全部カバーして出してきた(本店)。提供するワインの主流は、ちょいプレ、ノーネームのもの。個人生産者が多い。スペイン、イタリア、チリなど。ただし、仕入れ価格3000円以上になるノーネームワインは買わない。総合的に見て、一番コスパがいいのはスペインだと感じている。技術力ではフランスがトップだけど、ちょいプレがプレミアムワインになりえるのはスペイン。スペインのスターコンサルタントが人気を集めているし、2500円までのスペインワインはケース買いしてストックしやすく、10年後もリスクが少ないお買い得品だと思う。
遠藤氏
飲むとおいしいと言ってもらえるのがミドルレンジ。原価的にもお得感がある。日本人には松竹梅の真ん中を選ぶ傾向がある。ほんのちょっと贅沢したい、という気持ちがあるし、そこそこ満足感が得られる。ただし、ミドルレンジのワインは説明が必要。店の対応が重要なので、現場にワインを選ばせている。そうすると、熱を込めて説明できる。
店舗のひとつに立ち飲み500円均一の角打があり、ここにはワインを飲んだことない人も来ている。ワインは高いと思われているが、500円なら、と立ち寄ってもらえる。ここで週に1回、1杯1000円で特別なワインを出すようにしたら、売り上げがアップした。要は、いかに贅沢な満足感を与えられるか、だと思う。丸山氏の話に出たスペインは、土地としてはまだまだ田舎だが、若い人が入ってきて生産量が増えている。スペインには若い人が活躍できる場がある。
藤森氏
2500円以上のワインはまあまあ売れている。売れないと思ったことがない。他店では売れないという話をよく聞くが、売れないと思うから売れないのでは?客の立場から見ると、よくわからないから選びにくいのだと思う。
当店では、販売価格2000~3000円が主流。価値があることがわかってもらえれば、注文してもらえるはず。

「ちょいプレワイン」が、2500円以上となっていましたが、その上限は?
いくら以上が「プレミアム」?
これは、客によっても、店によっても、価格の捉え方が違ってきますよね?
店に来てくれる客が支払う平均額よりちょっと上、と考えていいでしょうか。
4氏の話をまとめると、
「価値をどれだけ伝えられるか」、「説明する側の情熱」、「客目線」、がちょっと上のクラスのワインを売る秘訣でしょうか。
 2015年のワイントレンドを占う
中島氏
2015年のワイントレンドを占う
中島氏
日本ワインは根強い人気で、このまま続くと思う。イタリアワインも気になる。季節によって飲みたいワインも変わってくるので、当店グループでは、新緑の季節ならソーヴィニヨン・ブランやグリューナー・フェルトリナー、といった提案をインポーターからしてもらえると、店で企画しやすく、客にも説明しやすい。だから、国にとらわれず、旬にこだわるようにしている。
丸山氏
日本ワインへの注目度が高まっているのを感じる。実はオザミでもワイナリーにチャレンジしようと思っている。JAの支援などもあり、新規ワイナリーが増えていて、日本のパワーを感じる。日本ワインって、意外と安い。しかも、魂の入ったワインがけっこうある。酒屋でも日本ワインの扱いが増えている。
その他での注目はガメイ。いいテロワールがあり、日々飲むワインにピッタリ。やさしくて、樽のニュアンスがなくて、頭が痛くならない。安くて品質がいい。例えばコート・ド・ピュイ(仏ボジョレ、モルゴン)など。価格は上がっていないのに、クオリティが上がっていてコスパがいい。ロワールの個人生産者なども面白いと思う。
このところ日本人の食文化が変わり、飲むワインも変わってきた。マリアージュを考えずに飲みたいことだってある。食とワインがどんどん進化して行くと思う。今は焼き鳥屋でもワインを出す時代。カジュアルと言われる飲食店のレベルが上がってきた。ワインもうまくて安いものがたくさんある。星付きシェフがビストロを出している時代だし。二極化は感じる。
遠藤氏
今はもう“ワインブーム”というよりも、普段からワインを飲む人が多くなり、当たり前になってきていると思う。家飲みブームも影響していると思う。だから、ワインはそれほど特別なものではないし、自分でつくりたい人も増えている。首都圏から山梨県、長野県のワイン産地に通い、勉強したり、農作業したりする人も珍しくない。東京オリンピックの2020年までは、日本のワインは伸びていくと思う。その後は淘汰がある。イタリアはコスパがよく、売りやすいもののひとつ。
どの国を見ても、最近はワインの情報量が多過ぎるように感じる。わかりやすさは大事だと思う。食では肉 、とりわけ赤身肉が人気だが、料理にいかに合わせるか?いかに提案していくか?それを自分の言葉で語れるか?が大事だと思う。
藤森氏
自社輸入しているのはイタリアワイン。
あまりにもマニアックすぎると、客が付いていかないと思う。
一般的に、ワインと料理が合わない経験は、あまりないのでは?トレンドは作っていくもの。今は飲食店がトレンドを作っていると思う。名前のないワインに光を当てて引き上げていくことで新しいトレンドが作れるように思う。

前半の「ちょいプレ」でも、彼らの注目するワインが出てきましたね。
国なら、
日本、スペイン、イタリア。
品種ならボージョレの
ガメイ。
スタイルとしては、
食とのマリアージュを考えすぎなくていいワイン、情報量の多すぎないワイン、わかりやすいワイン、季節や旬を感じられるワイン。
藤森氏が述べた、
「名前のないワインに光を当てて引き上げていくことで新しいトレンドが作れる」には大いに共感。
誰かの予測をただ待つのではなく、トレンドは自ら発掘し、発展させていける可能性があるものだと思います。
そのトレンドが、最初はたとえ店内だけのものでもいいと思います。
そのはじめの一歩が、やがて周囲に広がる可能性があるかもしれません。