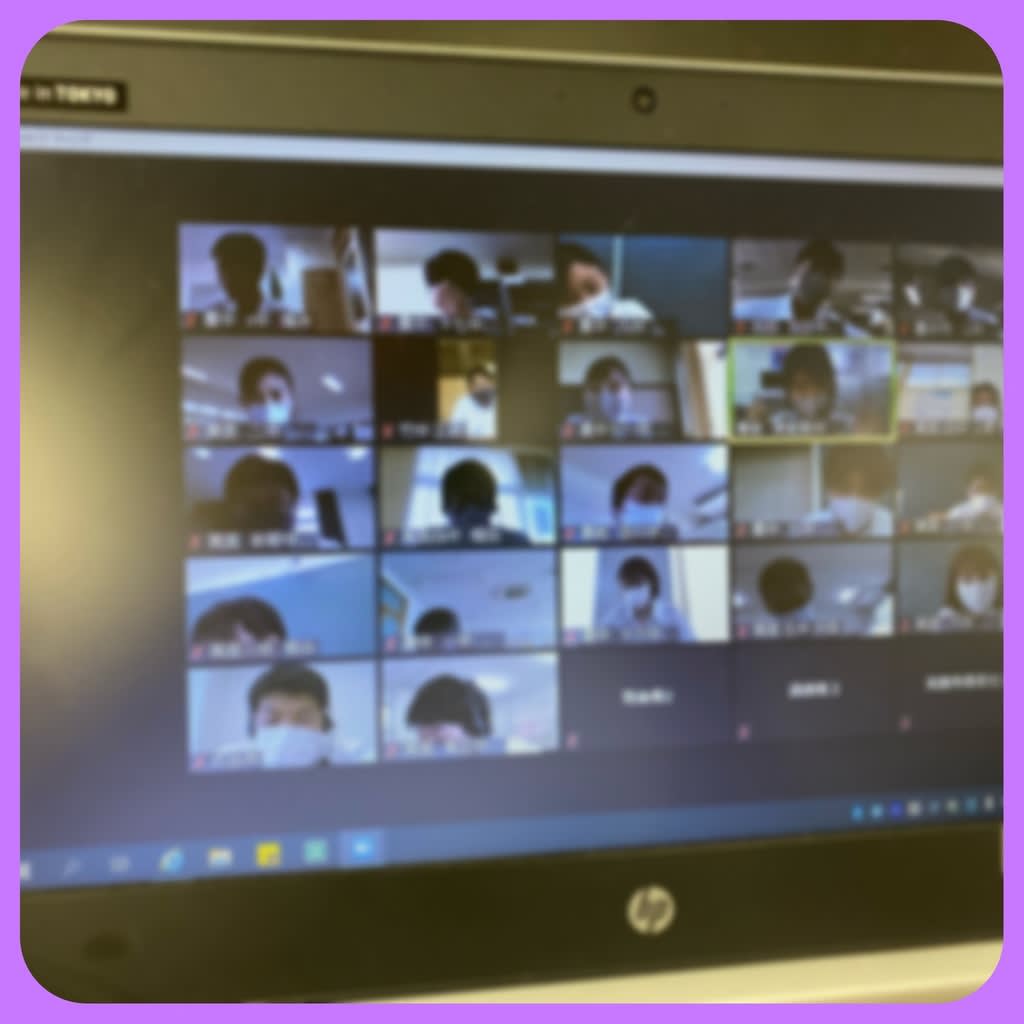
昨年から現在までで、リモートワークが進展しました。
ただし、国内の労働者の約6割はリモートワークができない仕事に就いています。
さらに労働者の約4割は非正規雇用であり、窓口業務や販売業に従事しています。
これらの仕事は対面でないとできないことが多いでしょう。
また、農業、林業、漁業はリモートでは成り立ちません。
ということで、去年から現在までで、リモートワークができる仕事とできない仕事の違いが明確になったのです。
今後は、リモートワークができる仕事は、さらにリモートが進展していくのではないかと思います。
さて、このブログがおもにテーマにしている教育に関しては、家庭学習と学校の学習のつなぐ点で、リモートが活躍していくでしょう。
何しろ、GIGAスクール構想で、ほぼ一人1台が行き渡るからです。
学校内でも端末を使い学習をしますが、それは対面授業の中で活用するのであり、リモートではありません。
一方、リモートが進んだ中でわかってきたことがあります。
それは職場への所属感が帰属感が薄くなるという弊害です。
特に新入社員にとっては、会社に行かないので、誰がいるかわからない、雑談する機会もないということが起こります。
雑談は無意味なように思えますがけっしてそうではありません。
雑談により、どんな人かがわかりますし、職場のコミニケーションが円滑になります。
会社になじめないという理由で、離職する人が増える心配があります。
こと教育に関しては、将来の労働環境を見据え、アナログにもデジタルにも対応できる人を育てる必要があります。
そのとき、アナログがデジタルかではなく、あるいは対面かリモートかではなく、状況や目的にあわせて使い分け、コミニケーションのとりかたを変革して、対面のよさを再認識できる。
そんな時代は目前に来ていると言えるでしょう。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます