1967-10/1に発行された信濃教育 第971号 のP68~93に『芥川龍之介作「庭」の解釈とその題材をめぐって』という評論が載っており、筆者の高林市治さんが、父や万福寺の金井正俊住職から聞き取った話が載っている。今まであまり知らなかった話や再発見の話がのっているので、「庭」に関する史料としてアーカイブしておく。
【あまり知られていなかった話】
①小穴隆一の父、小穴唯一郎は志村巌の三男ではあるが、後妻(松本市中町万藤家より嫁す)の初めての子。徴兵を逃れる為?架空?の小穴家への養子と言うにしたとの風説ありとのこと。
②「庭」に伝法肌(ヤンチャ)と描かれた志村巌は、岡谷の茶屋本陣の今井家から養子として志村家に入り、明治22年~29年まで宗賀村の初代村長であった。豪傑/傍若無人でいくつかの逸話がある。例えば小松家の婚礼の帰りに酩酊し、馬の用意を命じたが、無かったので大男に跨って家に帰った。葬儀の精進落としでお寺様を差し置いて上座に座った。村有林の調査の役人に、この沢の名前はと聞かれ、適当に名前を付けて返答した。等々、、、
③志村巌の長男志村勘一は経済的に破綻し、間口6間一杯に建てられていた脇本陣の建屋を売り払った。(現在も移築された建物が安曇野三郷に残っている)その後、三男の小穴唯三郎が家を再建、子の小穴隆一が相続したが、その建物は昭和7年の洗馬大火で焼け、家の無い土地は松本の万藤家が管理していた。
④大火の後、庭や屋敷跡は20年ほど放置され、近所の人が畑を作ったりした。
⑤20年間の放置の間に、ひょうたん池の西側は防火用水池を掘った土砂で埋められ、東側だけが残っている。
⑥ひょうたん池にはせんげから水が落ち、脇本陣に泊まった御岳修験者が荒行を行った。
⑦洗馬大火の後、石灯篭等の庭石の多くは葛家に移された。閑園神霊の石碑は庭に埋もれていたものを建て直した。
⑧志村家の墓所は2ヶ所あり、一つは百瀬守が引継ぎ、もう一つは尾沢橋の横にある。





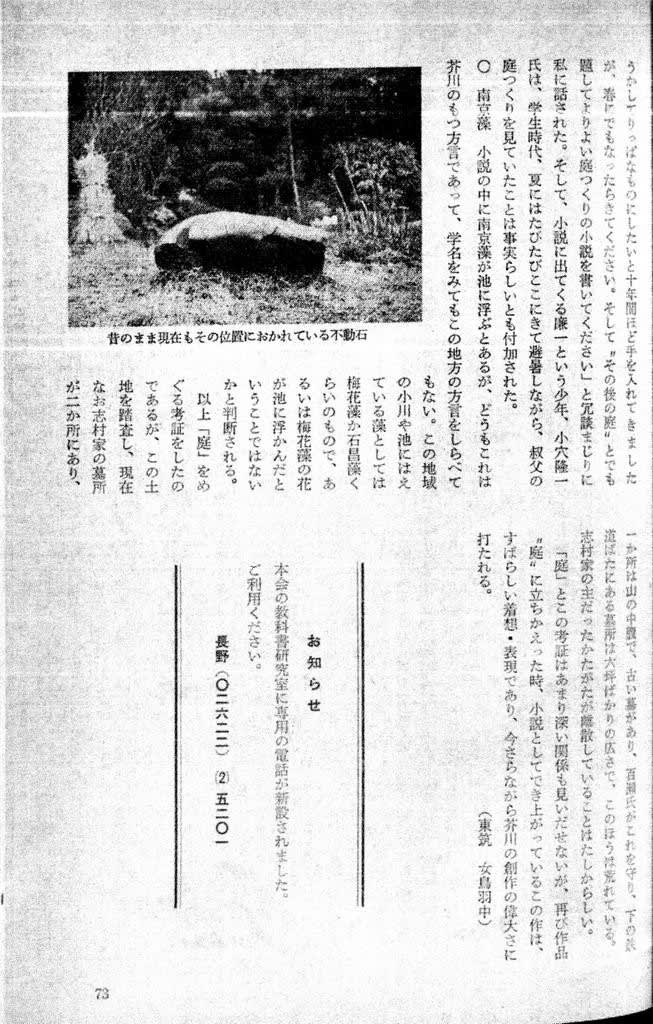
タグ 芥庭