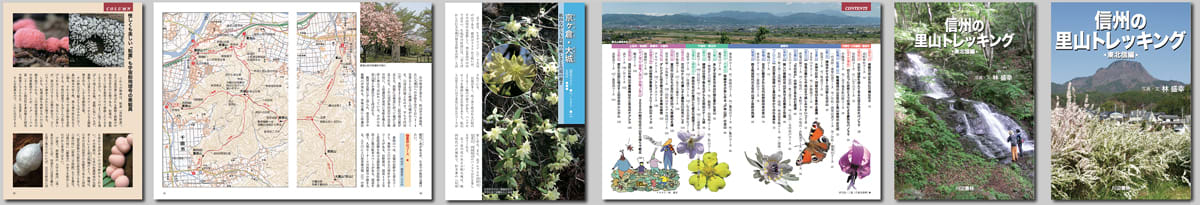前回の子檀嶺岳に続いて、また普通は読めない山に取材で登りました。もとどりやまと読みます。長野市北部の北国街道脇にあるリンゴ畑の中の里山。今回は単独です。

オオイヌノフグリとホトケノザ(これ間違いです。ヒメオドリコソウ。両方共シソ科ですが)の野原から髻山を撮影してみました。このロケーションを探すのにもっと苦労すると思いましたが、予め山頂から目星をつけておいたので、そう苦労せずにここに来られました。周囲がリンゴ畑なので、ここも昔はそうだったのかもしれません。所謂、耕作放棄地なのでしょうか。
髻というのは、ぴょこんと縦に伸びたちょんまげのことですが、本来はお釈迦様の頭に盛り上がった肉髻(にくけい)のことです。あの盛り上がった塊は、髪の毛ではなく、悟りを得た者だけにできる頭の上のたんこぶの様なものなのです。

リンゴ畑に囲まれています。標高は744.4mとそこそこあるのですが、登山口の標高が高いので、比高は170mぐらいとわずかです。このリンゴ畑の中の農道をゆるゆると登っていくのです。ゴールデンウィーク明けには、リンゴの白い花が咲き乱れるのですが、それは綺麗でしょう。

この山は、カタクリの山として有名です。南面を除く全ての面にカタクリの群生地があります。カタクリは、日本に200種類以上あるアリ散布植物のひとつ。アリがカタクリの胡麻より小さな種の先についているエライオソームという物質を餌とするため、種を巣に持ち帰ることが種蒔きになるわけです。
真ん中は、ウバユリとイノデでしょうか。ウバユリは山菜ですが、花を咲かせるまでに、6~7年かかります。決して全草を採ってはいけません。一株から葉を一枚ずつ採取するようにしましょう。それほど美味しい物でもないので私は採りませんが。カタクリも山菜です。春になると都内のスーパーなどにも並びますが、食べ過ぎると下します。便秘の人にはいいかもしれませんが。
山頂近くの登山道は、道の上にまでカタクリが咲いています。踏まないように注意して歩きましたが。それほど弱い植物でもありません。春だけ咲いて消えてしまう、所謂スプリング・エフェメラル、春の妖精、春の儚い命ですが、実は根が深くて球根の下にひげ根があり、傷めずに掘り出すのは結構大変。カタクリを盗掘しようなどと考えるのは愚か者。

山頂は、上杉謙信が築いた髻城跡。周囲は土塁で囲まれています。南面が伐採されて、善光寺平の展望が見事です。山頂には、長野県にはここにしかないという貴重な天文観測に使われた天測点があります。そして一等三角点も。山頂の西の端には、四角い穴が開いた石がふたつありました。城跡の門の跡でしょうか。

山頂から善光寺平を俯瞰したところ。長野市の中心街越しに、左から奇妙山、その奥に鏡台山から右へ妻女山、薬師山まで長い戸神山脈。奥は美ヶ原でしょうか。右へ大林山、冠着山、聖山が霞んでいました。

山の周囲には、たくさんの溜池があります。杉林を映す溜池には、誰が放したのか金魚が泳ぎ、アメンボがたくさんスイスイと滑っていました。周りには、猛毒のヤマトリカブトの群生地も。

原っぱに出ると、黒姫と妙高をバックに、数万本の土筆がニョキニョキと。子供の頃、祖母にこれを入れた玉子焼きを作ってもらって保育園に行った思い出があります。

原っぱの縁に、コブシの大木があり咲き誇っていました。コブシは、花の下に小さな葉があり、タムシバと区別がつきます。それで、タムシバの方が純白が映えるのですが、やや緑が入ったコブシも、これはこれで美しいものです。

林道の出口で振り返ると、残雪の飯縄山が見えました。手前はリンゴ畑です。あちこちの畑に農作業の人が出ていました。

帰りに撮影した、桜と髻山。カタクリの他には、フクジュソウやセリバオウレン、アズマイチゲやシャガも咲きます。髻山は、その歴史と共に地元の人が大切にしている花の山です。







オオイヌノフグリとホトケノザ(これ間違いです。ヒメオドリコソウ。両方共シソ科ですが)の野原から髻山を撮影してみました。このロケーションを探すのにもっと苦労すると思いましたが、予め山頂から目星をつけておいたので、そう苦労せずにここに来られました。周囲がリンゴ畑なので、ここも昔はそうだったのかもしれません。所謂、耕作放棄地なのでしょうか。
髻というのは、ぴょこんと縦に伸びたちょんまげのことですが、本来はお釈迦様の頭に盛り上がった肉髻(にくけい)のことです。あの盛り上がった塊は、髪の毛ではなく、悟りを得た者だけにできる頭の上のたんこぶの様なものなのです。

リンゴ畑に囲まれています。標高は744.4mとそこそこあるのですが、登山口の標高が高いので、比高は170mぐらいとわずかです。このリンゴ畑の中の農道をゆるゆると登っていくのです。ゴールデンウィーク明けには、リンゴの白い花が咲き乱れるのですが、それは綺麗でしょう。

この山は、カタクリの山として有名です。南面を除く全ての面にカタクリの群生地があります。カタクリは、日本に200種類以上あるアリ散布植物のひとつ。アリがカタクリの胡麻より小さな種の先についているエライオソームという物質を餌とするため、種を巣に持ち帰ることが種蒔きになるわけです。
真ん中は、ウバユリとイノデでしょうか。ウバユリは山菜ですが、花を咲かせるまでに、6~7年かかります。決して全草を採ってはいけません。一株から葉を一枚ずつ採取するようにしましょう。それほど美味しい物でもないので私は採りませんが。カタクリも山菜です。春になると都内のスーパーなどにも並びますが、食べ過ぎると下します。便秘の人にはいいかもしれませんが。
山頂近くの登山道は、道の上にまでカタクリが咲いています。踏まないように注意して歩きましたが。それほど弱い植物でもありません。春だけ咲いて消えてしまう、所謂スプリング・エフェメラル、春の妖精、春の儚い命ですが、実は根が深くて球根の下にひげ根があり、傷めずに掘り出すのは結構大変。カタクリを盗掘しようなどと考えるのは愚か者。

山頂は、上杉謙信が築いた髻城跡。周囲は土塁で囲まれています。南面が伐採されて、善光寺平の展望が見事です。山頂には、長野県にはここにしかないという貴重な天文観測に使われた天測点があります。そして一等三角点も。山頂の西の端には、四角い穴が開いた石がふたつありました。城跡の門の跡でしょうか。

山頂から善光寺平を俯瞰したところ。長野市の中心街越しに、左から奇妙山、その奥に鏡台山から右へ妻女山、薬師山まで長い戸神山脈。奥は美ヶ原でしょうか。右へ大林山、冠着山、聖山が霞んでいました。

山の周囲には、たくさんの溜池があります。杉林を映す溜池には、誰が放したのか金魚が泳ぎ、アメンボがたくさんスイスイと滑っていました。周りには、猛毒のヤマトリカブトの群生地も。

原っぱに出ると、黒姫と妙高をバックに、数万本の土筆がニョキニョキと。子供の頃、祖母にこれを入れた玉子焼きを作ってもらって保育園に行った思い出があります。

原っぱの縁に、コブシの大木があり咲き誇っていました。コブシは、花の下に小さな葉があり、タムシバと区別がつきます。それで、タムシバの方が純白が映えるのですが、やや緑が入ったコブシも、これはこれで美しいものです。

林道の出口で振り返ると、残雪の飯縄山が見えました。手前はリンゴ畑です。あちこちの畑に農作業の人が出ていました。

帰りに撮影した、桜と髻山。カタクリの他には、フクジュソウやセリバオウレン、アズマイチゲやシャガも咲きます。髻山は、その歴史と共に地元の人が大切にしている花の山です。