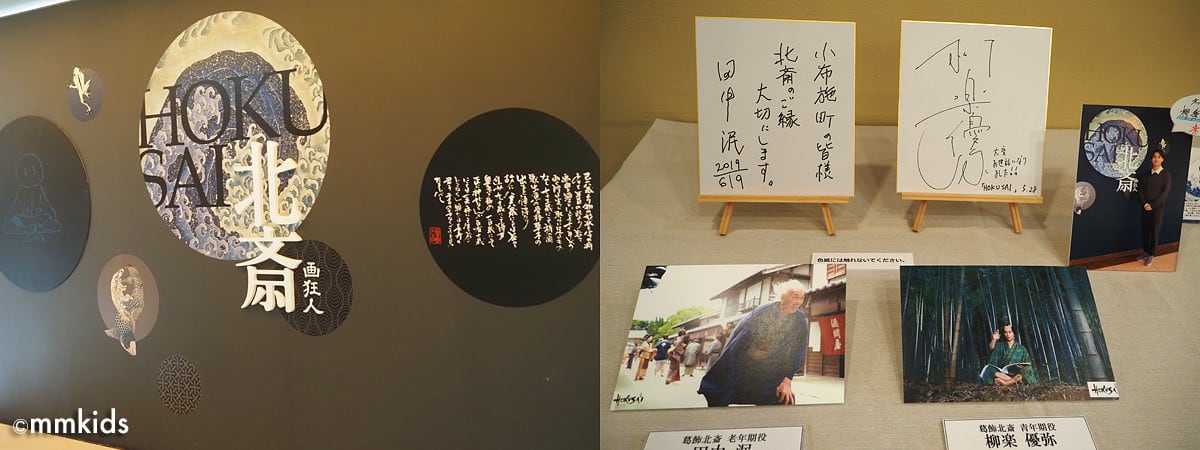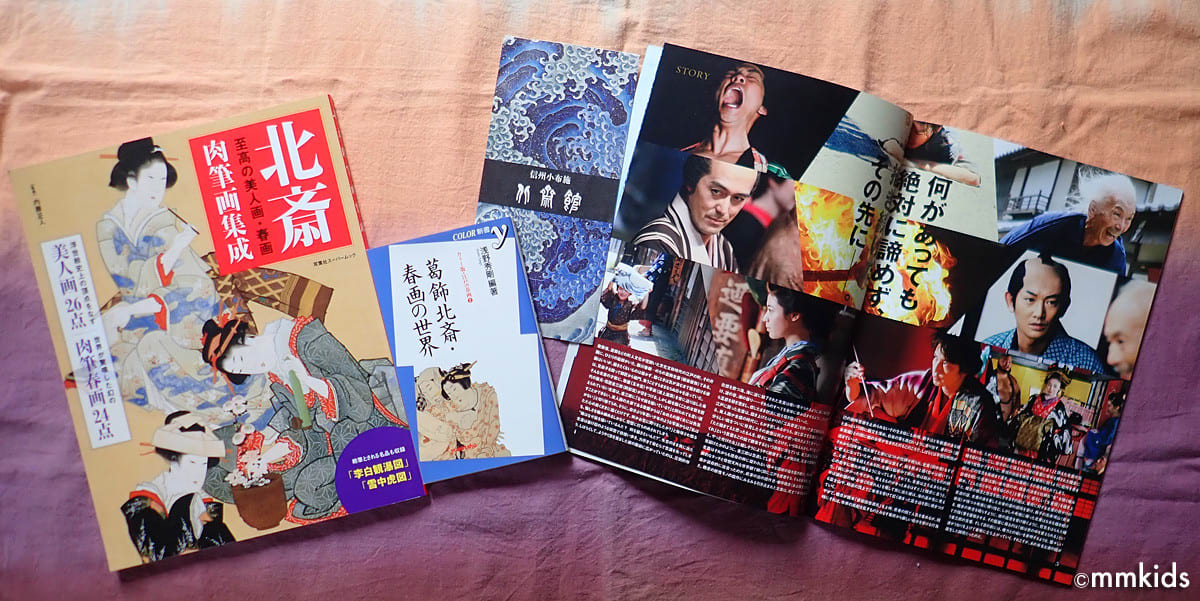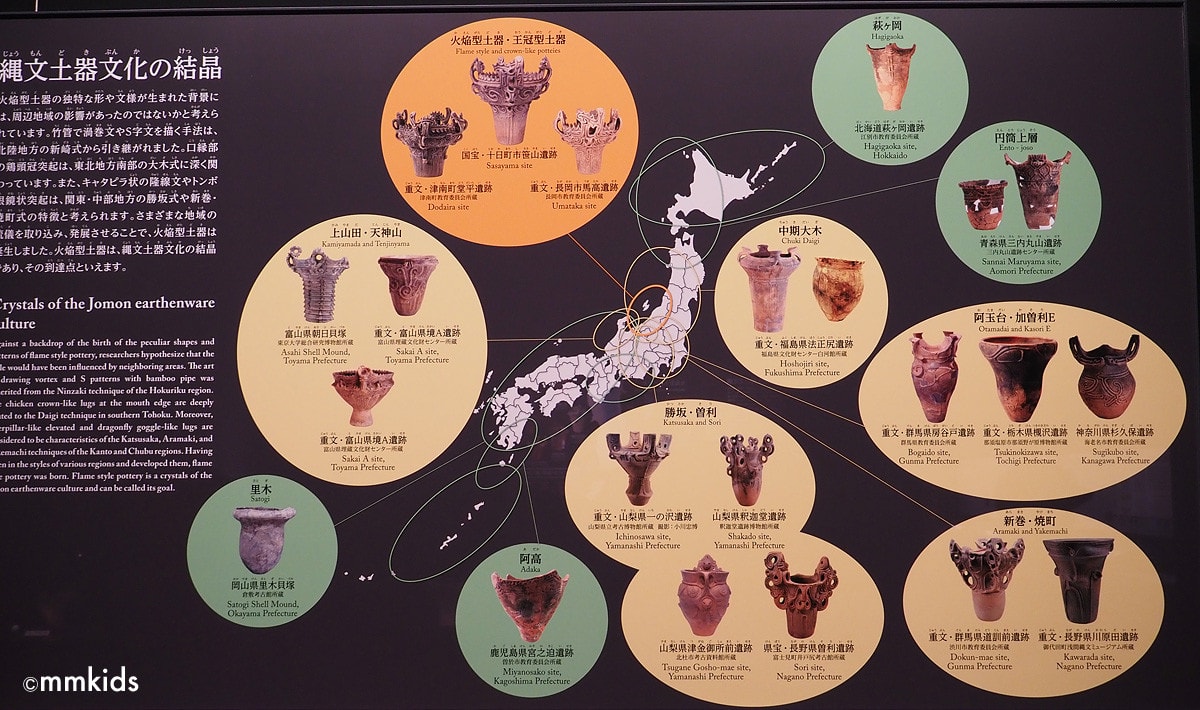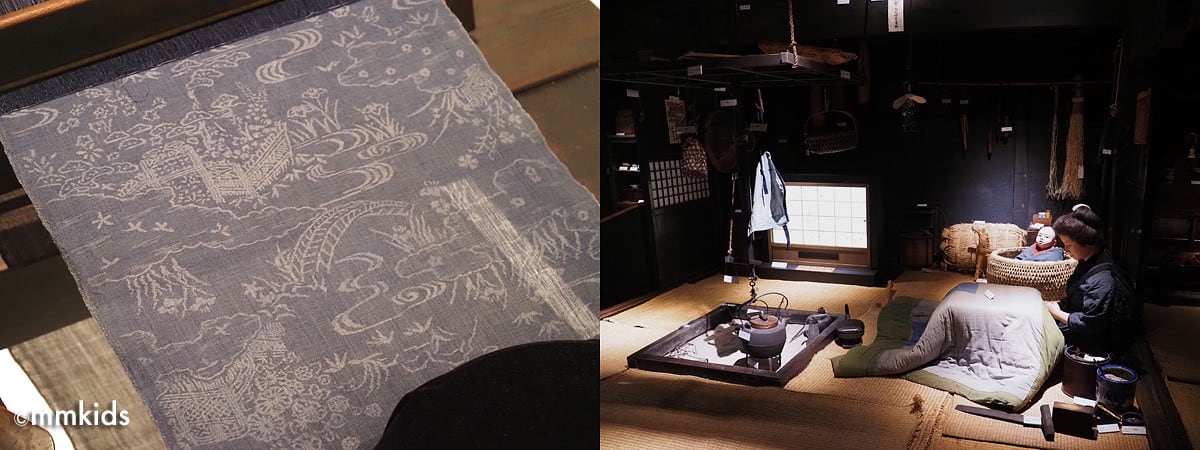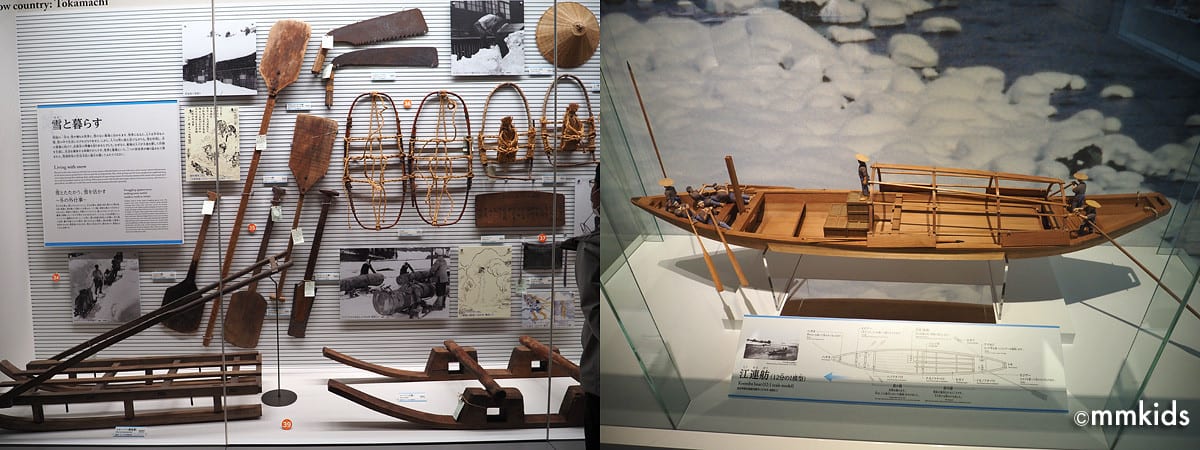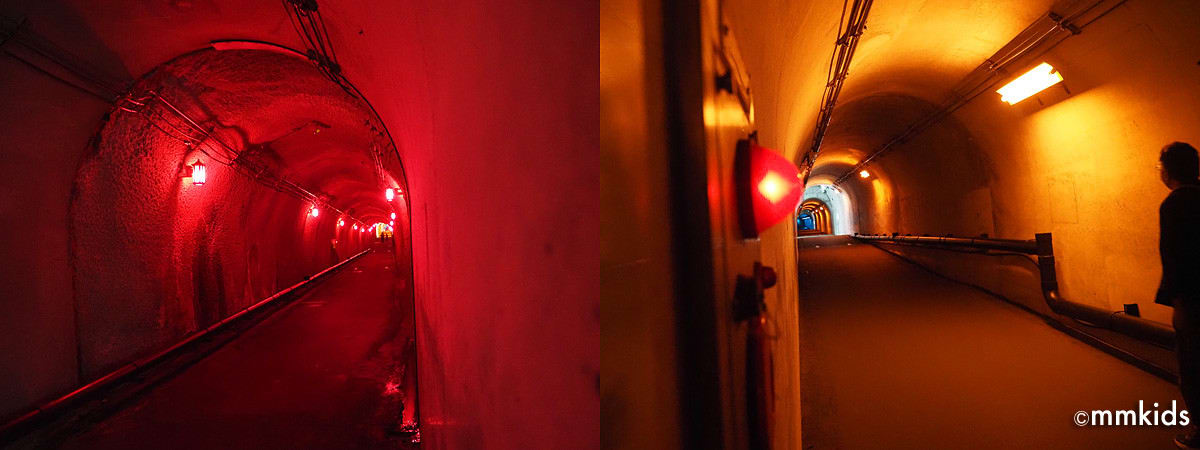今年の梅雨は信州には珍しくじとじとジメジメした陰性ですね。カラッとした梅雨晴れが少ないのでゼフィルス(シジミチョウ)の発生も少なめです。オオムラサキは24日に初見しましたが、その後見ていません。樹液バーにも昆虫は来ていません。
僅かな晴れ間を狙って妻女山山系のある場所へ。三箇所ほど出現する場所を知っているので向かいました。もちろん他にもあるはずですが、あまり離れていると撮影が間に合いません。それは出現する時間が午前中の9時から10時ぐらいと限られているからです。

ここにはオスが一頭しかいませんでした。僅かな日当たりの良い葉の上で翅を開いています。ターコイズブルーの翅がキラキラと輝いて美しい。構造色なので見る角度によって微妙に色が変化します。

幼虫の食樹は、コナラ、クヌギ、ミズナラ、カシワなど。翅を広げているのは、テリトリーを主張する占有行動です。

別の場所で。オス同士で占有行動するため、この後すぐに飛び立って三頭のオスでクルクルと回っていました。撮影はひたすらシャッターチャンスを待つが鉄則です。いつ来るか分からない彼女を待つ。そんな気分です。撮影するのはオスですけれどね(笑)。

そして日当たりの良い葉の上で開翅し占有行動をとります。今回は昨年と違って雨後で湿度が高く、地上付近まで下りてきませんでした。そのため撮影はマクロレンズでなく望遠マクロのみです。残念でした。
●森の宝石オオミドリシジミの復活。あんずの収穫の季節。オオムラサキ初見(妻女山里山通信):マクロレンズで最接近で撮影した2018年の少し腹の立つ、そして感動的な再会の記事です。

下山します。歩き疲れました。待ち疲れました。樹間から千曲川と上信越自動車道。右手前に松代PA。とろろご飯と蕎麦が名物。地元野菜も買えます。堤防の上はサイクルツーリングに最適。一部車道と併用なので要注意。

私が主宰する妻女山里山デザイン・プロジェクトが保護活動をしている貝母群生地のある陣場平へ。シオヤアブのオスが獲物をゲット。犠牲になったのはセイヨウミツバチの様ですね。シオヤアブは自分より大きな昆虫を捕獲することもあります。体液を吸ってる先でハエの仲間でしょうか、おこぼれをちょうだいしています(笑)。

(左)ナラハウラマルタマバチ(コナラフシバチ)が寄生して出来た虫こぶ(虫えい・ゴール)です。中に一匹の幼虫が入っていて内部を摂食し成長。2〜3週間で落下しその中で成長。10〜11月に羽化して成虫に。(右)ハラタケ科のカラカサタケ。食べられますが特別美味しくないし似ている猛毒のキノコがあるので私は一度食べましたが、それ以降食べません。キノコの判別は絶対に図鑑とかでしてはいけません。迷ったら保健所へ。どんな猛毒のキノコでも一度は食べられますが二度目はありません。
●コナラの木にリンゴをならすハチ!(妻女山里山通信):これも虫こぶです。

粘菌のツノホコリ(角埃)。正しくは原生粘菌類に属するツノホコリ科ツノホコリ属の粘菌。世界に三種、日本にあるのは一種。変種にはほかに、枝分かれしないエダナシツノホコリ、丸いタマツノホコリ、カンボクツノホコリ、ナミウチツノホコリなどがあります。高さは2ミリ前後。半透明で、触るとゼリー状につぶれます。ごく普通に見られる粘菌です。他とは違い、透明な棍棒状の子実体の周りに柄のついた白い胞子嚢をつけます。周りに白く粉状に見えるものがそうです。胞子嚢がまだ未完成のものは透明に見えます。

赤松の伐採木に粘菌。遠目で見るとまったく何か分かりません。ハイカーも気にもとめないでしょう。でも真っ赤な粘菌や黄色のアメーバー状の粘菌もあって、そういうのは何これ!って思うでしょうね。

タマツノホコリ(玉角埃)ツノホコリ科ツノホコリ属。ツノホコリの変種。別名はタマサンゴホコリ。担子体は群生し、外生胞子を作る変形菌はツノホコリ属のみです。おそらく午後には外生胞子を飛ばし始めるでしょう。変種の見分けは結構微妙で難しい。

下山中に見つけた蛾。ドアを開けると逃げられそうなので窓を開けて腕を一杯に伸ばして撮影。エダシャクの仲間でしょう。種名は不明ですがヒョウモンエダシャクかな。梅雨の里山なんて蒸し暑いしクロメマトイにまつわりつかれるしでほとんど人が来ませんが、実は生物が生き生きと活動する魅力的な季節なんです。雨中登山では、ブナの大木を流れ下る小さな川筋も見られます。

昔イノシシが泥をこすりつけて樹皮が剥けた落葉松から滲み出る樹液(ヤニ)。出たばかりは赤茶色なんですが、時間が立つとプルシャンブルーに変色し固まり樹脂になります。精油分(テレビン油)で工業用に古くから使われてきました。高校の美術班で油絵を描く時にも溶剤として使いました。家具や建築材に使う時は脱脂をします。春の芽吹き時にはヤニの細かな雨が降るので、落葉松林の近くには駐車しない方が賢明です。疲れたので温泉へ。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。
僅かな晴れ間を狙って妻女山山系のある場所へ。三箇所ほど出現する場所を知っているので向かいました。もちろん他にもあるはずですが、あまり離れていると撮影が間に合いません。それは出現する時間が午前中の9時から10時ぐらいと限られているからです。

ここにはオスが一頭しかいませんでした。僅かな日当たりの良い葉の上で翅を開いています。ターコイズブルーの翅がキラキラと輝いて美しい。構造色なので見る角度によって微妙に色が変化します。

幼虫の食樹は、コナラ、クヌギ、ミズナラ、カシワなど。翅を広げているのは、テリトリーを主張する占有行動です。

別の場所で。オス同士で占有行動するため、この後すぐに飛び立って三頭のオスでクルクルと回っていました。撮影はひたすらシャッターチャンスを待つが鉄則です。いつ来るか分からない彼女を待つ。そんな気分です。撮影するのはオスですけれどね(笑)。

そして日当たりの良い葉の上で開翅し占有行動をとります。今回は昨年と違って雨後で湿度が高く、地上付近まで下りてきませんでした。そのため撮影はマクロレンズでなく望遠マクロのみです。残念でした。
●森の宝石オオミドリシジミの復活。あんずの収穫の季節。オオムラサキ初見(妻女山里山通信):マクロレンズで最接近で撮影した2018年の少し腹の立つ、そして感動的な再会の記事です。

下山します。歩き疲れました。待ち疲れました。樹間から千曲川と上信越自動車道。右手前に松代PA。とろろご飯と蕎麦が名物。地元野菜も買えます。堤防の上はサイクルツーリングに最適。一部車道と併用なので要注意。

私が主宰する妻女山里山デザイン・プロジェクトが保護活動をしている貝母群生地のある陣場平へ。シオヤアブのオスが獲物をゲット。犠牲になったのはセイヨウミツバチの様ですね。シオヤアブは自分より大きな昆虫を捕獲することもあります。体液を吸ってる先でハエの仲間でしょうか、おこぼれをちょうだいしています(笑)。

(左)ナラハウラマルタマバチ(コナラフシバチ)が寄生して出来た虫こぶ(虫えい・ゴール)です。中に一匹の幼虫が入っていて内部を摂食し成長。2〜3週間で落下しその中で成長。10〜11月に羽化して成虫に。(右)ハラタケ科のカラカサタケ。食べられますが特別美味しくないし似ている猛毒のキノコがあるので私は一度食べましたが、それ以降食べません。キノコの判別は絶対に図鑑とかでしてはいけません。迷ったら保健所へ。どんな猛毒のキノコでも一度は食べられますが二度目はありません。
●コナラの木にリンゴをならすハチ!(妻女山里山通信):これも虫こぶです。

粘菌のツノホコリ(角埃)。正しくは原生粘菌類に属するツノホコリ科ツノホコリ属の粘菌。世界に三種、日本にあるのは一種。変種にはほかに、枝分かれしないエダナシツノホコリ、丸いタマツノホコリ、カンボクツノホコリ、ナミウチツノホコリなどがあります。高さは2ミリ前後。半透明で、触るとゼリー状につぶれます。ごく普通に見られる粘菌です。他とは違い、透明な棍棒状の子実体の周りに柄のついた白い胞子嚢をつけます。周りに白く粉状に見えるものがそうです。胞子嚢がまだ未完成のものは透明に見えます。

赤松の伐採木に粘菌。遠目で見るとまったく何か分かりません。ハイカーも気にもとめないでしょう。でも真っ赤な粘菌や黄色のアメーバー状の粘菌もあって、そういうのは何これ!って思うでしょうね。

タマツノホコリ(玉角埃)ツノホコリ科ツノホコリ属。ツノホコリの変種。別名はタマサンゴホコリ。担子体は群生し、外生胞子を作る変形菌はツノホコリ属のみです。おそらく午後には外生胞子を飛ばし始めるでしょう。変種の見分けは結構微妙で難しい。

下山中に見つけた蛾。ドアを開けると逃げられそうなので窓を開けて腕を一杯に伸ばして撮影。エダシャクの仲間でしょう。種名は不明ですがヒョウモンエダシャクかな。梅雨の里山なんて蒸し暑いしクロメマトイにまつわりつかれるしでほとんど人が来ませんが、実は生物が生き生きと活動する魅力的な季節なんです。雨中登山では、ブナの大木を流れ下る小さな川筋も見られます。

昔イノシシが泥をこすりつけて樹皮が剥けた落葉松から滲み出る樹液(ヤニ)。出たばかりは赤茶色なんですが、時間が立つとプルシャンブルーに変色し固まり樹脂になります。精油分(テレビン油)で工業用に古くから使われてきました。高校の美術班で油絵を描く時にも溶剤として使いました。家具や建築材に使う時は脱脂をします。春の芽吹き時にはヤニの細かな雨が降るので、落葉松林の近くには駐車しない方が賢明です。疲れたので温泉へ。
◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。
★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。
インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。シニア大学や自治体などで好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。大学や市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。


































































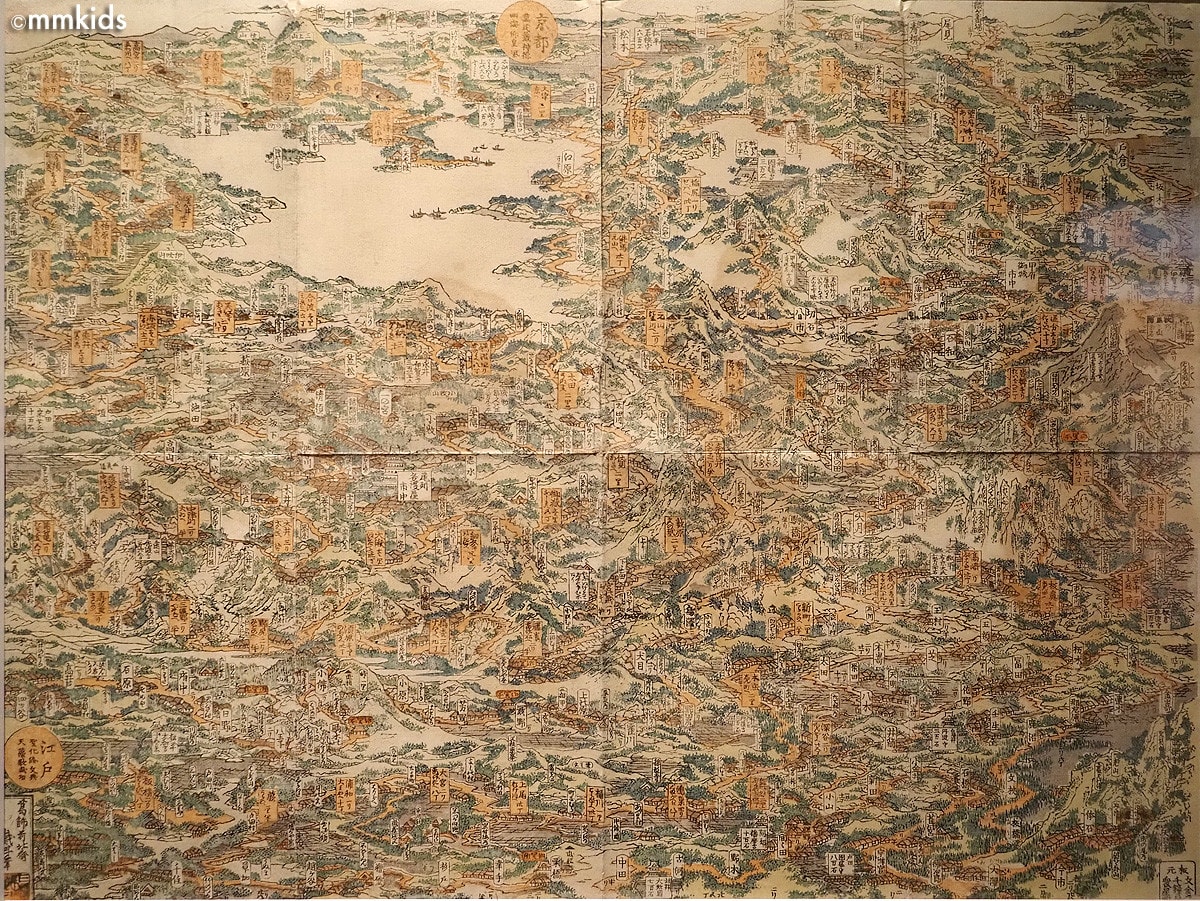



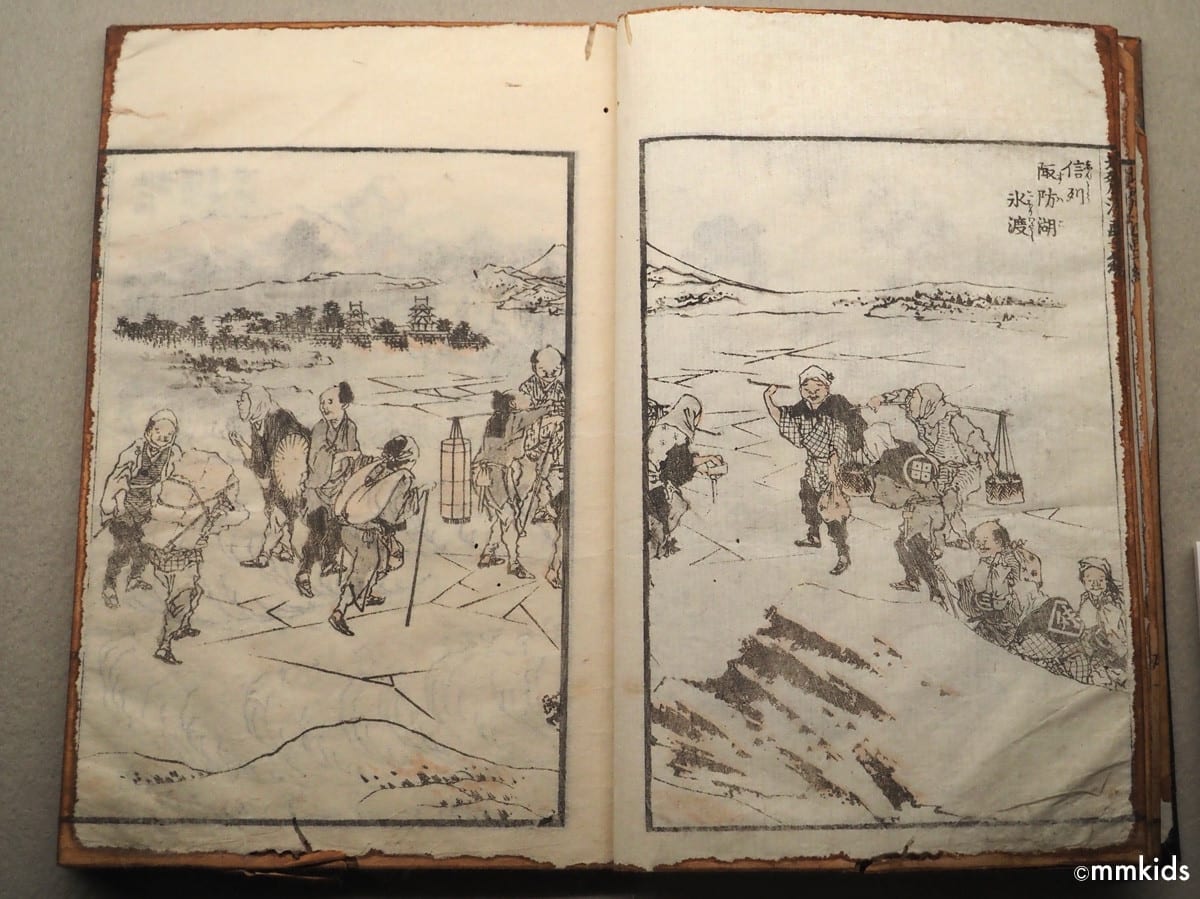



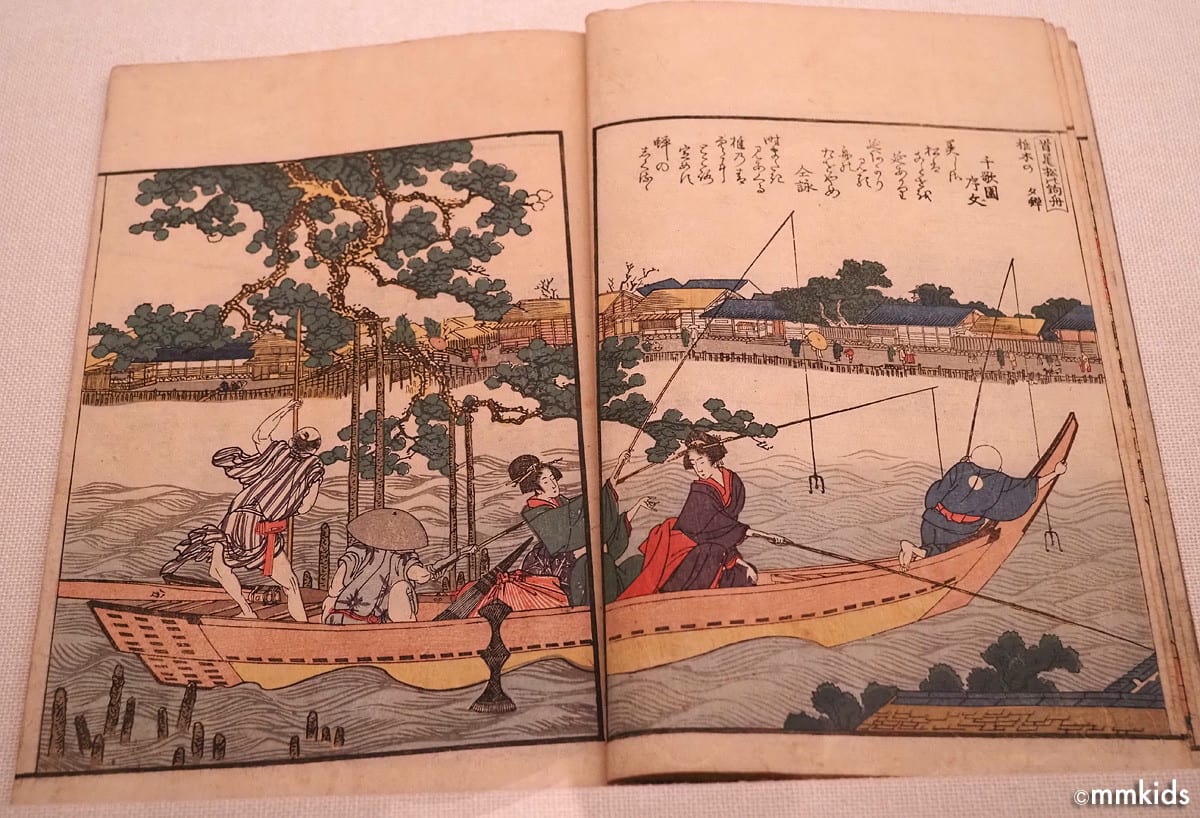
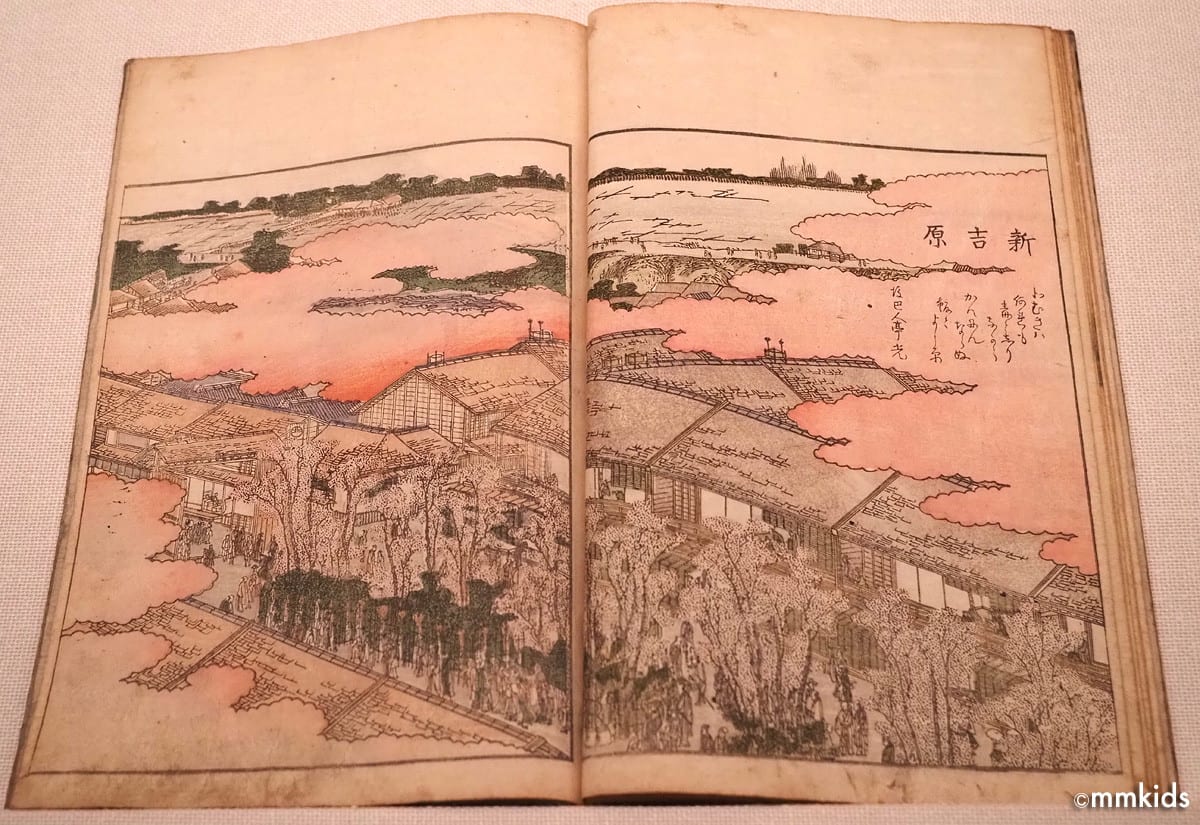

 wiki
wiki