 はじめての学芸会
はじめての学芸会
覚えていないだけかもしれないけれど、学芸会というものを体験した記憶がない。運動会、卒業生を送る会、合唱コンクール、学年劇…そんな記憶はあるものの、「学芸会」という形ではなかったように思う。そういうわけで、「学芸会」に対するイメージが真っ白なまま、小・中学校の学芸会を見ることになった。
・・・
まずびっくりしたのは演目の多さ。どの学年も2つ以上の演目があり、どれも簡単なものではなかった。それをたった2・3週間の間に取り組んでここまでマスターしていることに驚いた。それも、普通の授業もある中での取り組みだ。それを支える先生たちの苦労はどれほどのものなのか、と思いながら見ていた。
・・・
「学芸会の準備がんばってるね」と声をかけたら、「がんばってるのは練習!」と答えてきた子どもたち。そりゃそうだ、子どもたちにとっては練習だよなぁと、自分のうっかりな言葉選びを思い出しながら、小学生・中学生ってここまでできるんだと思った、「はじめて」の学芸会だった。











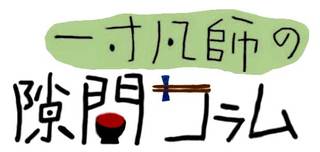 ふくろう
ふくろう で読む回数の方が多い!)
で読む回数の方が多い!) 心残り
心残り
 「
「





