 公式裏ブログで紹介した『パンとスープとネコ日和』(4/14「5度目の『面白いドラマ』」)。その続編と続々編にあたる小説『優しい言葉』、『福も来た』(群ようこ著:ハルキ文庫)。ドラマの面白さをもう少し長く味わいたくて。ドラマの登場人物が活字で動いている感じで読む。
公式裏ブログで紹介した『パンとスープとネコ日和』(4/14「5度目の『面白いドラマ』」)。その続編と続々編にあたる小説『優しい言葉』、『福も来た』(群ようこ著:ハルキ文庫)。ドラマの面白さをもう少し長く味わいたくて。ドラマの登場人物が活字で動いている感じで読む。
メニューの工夫、お客さんの変化、働く様子、主人公の「やってみる精神」、どれも波風食堂店主に興味あることだが、エッセー風の薄味小説だから腹の足しにはなりずらい。
ドラマでほんの脇役の猫が、小説では準主役。猫好きには堪らないだろうなあ。猫の愛らしさを学ぶ2冊。まだ『パンとスープとネコ日和』を読んでいないので何とも言えないが、ドラマ(脚本と配役)はかなり上手く出来てる感じ。
仕事で迷う主人公に、お寺のお内儀が「他の人よりも目立って褒めてもらおうっていう人が多くなったけれど、地道にまじめにやっていれば、見てくれている人は必ずいるんです。…(略)…残念ながら愚かしい人もいるけれど、そうでない人も間違いなくいます。自分に不利益を与えようとする人たちとは、彼らを謝らせようとか反省させようとは思わないで、関わらないようにするのが一番。生きていく上での基準が異なっているので、同じ土俵で仲良くしていくのは難しい。犯罪はいけないですが、百人いれば百通りの生き方があります」(『福も来た』134頁)の一言。続けて「お寺は人と人とのつながりが一番大切。妙な噂話やありもしないことを言われたりしましたけど、根っこをぐらつかせないで、淡々と過ごしていくしかないですね」のアドバイス。薄味小説2冊で立ち止まった箇所。
読書交流『第8回 ほんのおつきあい』の記録は今週中にブログで紹介予定 そこで紹介された漫画『寄生獣』のリアル版を『帰省中ではなくて』で裏ブログにて紹介。
そこで紹介された漫画『寄生獣』のリアル版を『帰省中ではなくて』で裏ブログにて紹介。










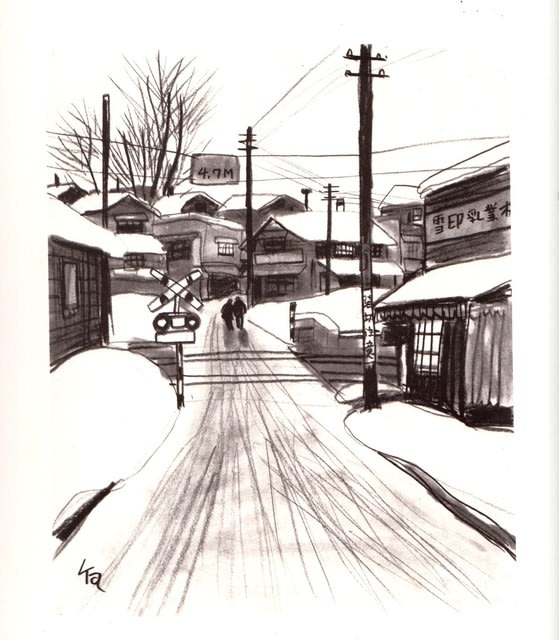

 花壇の樹の添え木を外し、外水栓使えるようにする。日中21度。
花壇の樹の添え木を外し、外水栓使えるようにする。日中21度。
 散歩、読書、食堂、調理。手つかずは絵と工作。
散歩、読書、食堂、調理。手つかずは絵と工作。







