自宅のメインパソコンをようやく更新し、Linux(Ubuntu) を中心として、快適に使えるようになりましたが、一週間のうち週末以外の大半を過ごす単身赴任のアパートでは、Windows2000 で動作する古いパソコンを使っています。ところが、フリーのアンチウィルスソフトが悪さをしているのか、やけに性能が悪いように感じられてしかたがありません。かといって、アンチウィルスソフトを入れないで Windows を使うなど、なんとも不安です。
そこで、今まで自宅でメインに使っていた、VineLinux で動作するパソコン FMV-6450CL3 を、単身赴任のアパートで使うことにしました。比較してみると、CPU のクロック周波数では劣っているのに、実際の動作は Linux機(FMV)のほうがずっとスムーズです。これなら、ウィルスの心配もまずありませんし、どちらかが壊れても、もう一台の方で対応することができます。


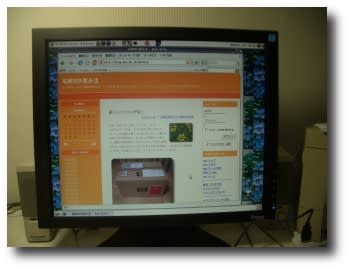
【追記】
2台のパソコンは、机がわりのテーブルの下に、並べて置きました。1組のキーボードとマウスとディスプレイで使えるように、パソコンの上に見える、Aten の CPU 切替器を使っています。これは、CTRLキーを連打すると、Windows パソコンと Linux パソコンを切り替えることができますので、なかなか便利なものです。ついでに、キーボードとマウスも、交換しました。
--
ところで、今回購入したパソコンの選択にあたっては、国内メーカーのものは余計な付属ソフトを満載し、ほとんど使いもしない機能をうたって価格を維持しているものが多く、はじめから却下していました。
ノート型は、小型(B5)で長時間運用が可能な携帯用をすでに使っておりますので、ディスプレイの広々とした大きさとキーボードの置き方の自由さで、ふだん使うものとしては、デスクトップ型と決めております。
その他には、次のような基準で、選択をしました。
周辺機器やソフトウェアの操作性の継承などを考え、WindowsVista に触れる機会を残しつつ、Linux 中心の選択としたものです。hp の s3540jp/CT は、実用的な選択でした。
ただし、使ってみてわかったことですが、Ubuntu は文字コードが UTF-8 (Unicode) で、TeX/LaTeX には適したディストリビューションではなかったようです。もしかすると、WindowsVista のほうに、vmware+VineLinux を仮想環境で試すという手段もあるかな。使い慣れた VineLinux のほうは、TeX/LaTeX 環境としては素晴しいものがあります。
そこで、今まで自宅でメインに使っていた、VineLinux で動作するパソコン FMV-6450CL3 を、単身赴任のアパートで使うことにしました。比較してみると、CPU のクロック周波数では劣っているのに、実際の動作は Linux機(FMV)のほうがずっとスムーズです。これなら、ウィルスの心配もまずありませんし、どちらかが壊れても、もう一台の方で対応することができます。


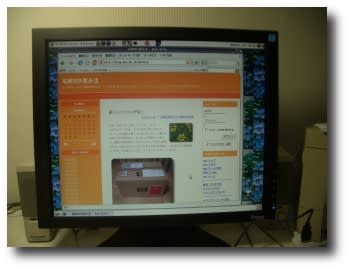
【追記】
2台のパソコンは、机がわりのテーブルの下に、並べて置きました。1組のキーボードとマウスとディスプレイで使えるように、パソコンの上に見える、Aten の CPU 切替器を使っています。これは、CTRLキーを連打すると、Windows パソコンと Linux パソコンを切り替えることができますので、なかなか便利なものです。ついでに、キーボードとマウスも、交換しました。
--
ところで、今回購入したパソコンの選択にあたっては、国内メーカーのものは余計な付属ソフトを満載し、ほとんど使いもしない機能をうたって価格を維持しているものが多く、はじめから却下していました。
ノート型は、小型(B5)で長時間運用が可能な携帯用をすでに使っておりますので、ディスプレイの広々とした大きさとキーボードの置き方の自由さで、ふだん使うものとしては、デスクトップ型と決めております。
その他には、次のような基準で、選択をしました。
今なら、CPU性能よりもメモリの搭載量が重要。必要と言われている値の倍にしておけば、なんとか実用になる。WindowsVista なら 1GB が必要と言われているので、2GB を搭載するもので、価格がそこそここなれているデスクトップ。
周辺機器やソフトウェアの操作性の継承などを考え、WindowsVista に触れる機会を残しつつ、Linux 中心の選択としたものです。hp の s3540jp/CT は、実用的な選択でした。
ただし、使ってみてわかったことですが、Ubuntu は文字コードが UTF-8 (Unicode) で、TeX/LaTeX には適したディストリビューションではなかったようです。もしかすると、WindowsVista のほうに、vmware+VineLinux を仮想環境で試すという手段もあるかな。使い慣れた VineLinux のほうは、TeX/LaTeX 環境としては素晴しいものがあります。
















