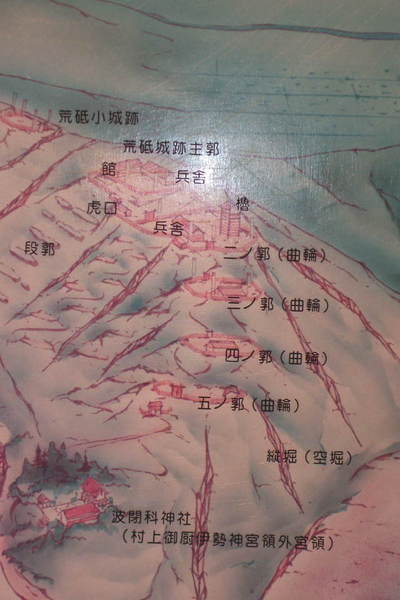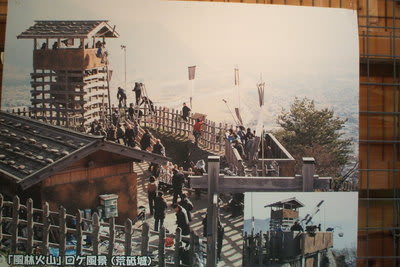信州日帰り旅行、荒砥城の後の話です。

荒砥城のそばまできたなら、お勧めスポット。荒砥城入口からほど近い場所にある「にしざわ貯金箱かん」です。(午前9時~午後5時半。年末年始・月曜休み。入館料600円)

オープンしたのが2008年4月1日とあってかなり建物も新しい。貯金箱ってみるもんなの?と最初は半信半疑だった私だが、妻の「行こうよぉ~」の声に押されて入館。入るや結構おもしろい。タレント貯金箱や明治時代や戦中の貯金箱など色々な貯金箱があって意外とおもしろかった。子どもも結構楽しめる。さらに館長の古銭の趣味で、日本や世界のお金がいろいろあってこれもおもしろかった。

信州と言えば清流があり水がうまい。だから「元祖豊年屋」という店に「おしぼりそば」を食べに行く。「おしぼり」とは地元産の「ねずみ大根」のおろしのことで、辛味大根だけにぴりカラで超うまい。つゆに味噌の付け合せもあり、味噌の甘さで好みの味に変えられるのもグー。
お腹がいっぱいになったところで、鉄道好きとしてはやはり気になる「しなの鉄道」へ。しなの鉄道は長野新幹線ができたことで、JRにとってお荷物となった在来線の信州本線を第3セクター化したものです。1997年に誕生したからもう12年も前のことになります。荒砥城がある上山田温泉から一番近いのが「戸倉駅」。駅の周辺は一般的な地方の温泉街という感じ。

しかし驚くべきことは構内の大きさ。さすが元JRだけあって、構内には列車の接近を警告する電光掲示板や首都圏と同じ発車メロディーがあった。ホームもすこぶる長かった。しなの鉄道の車両は通勤系車両の115系と郊外系車両の169系がある赤と銀の車体がなかなかセンスいい。
その走る姿を見たくてわざわざ発車時間に合わせて駅にいったのだが、残念ながら来た列車は乗り入れしているJR塗装色(水色+白)でした。残念。

駅のベンチにはすべてゴザがひいてありました。寒い国で第3セクターならではのならでのちょっと心配りに、感動!


さて、坂城町方面に戻ると「村上義清」の看板が!これは行かなきゃと思い。車を止めて看板をチェック。何々…。村上義清の居館跡?「現在は満泉寺かぁ。居館跡の石碑でもあるかも…行ってみるか!」

「…。寺が工事中…。石碑も何もない…。帰るか…。う~ん納得がいかない!何か村上関係のものをみなきゃ気がすまない!ネットで検索!ん?村上義清公墓所?行ってみるか。」

墓所は小規模な公園として整備されており、駐車場も整備されていた。しかも村上の家紋が!こんなこだわりが結構嬉しい。墓所ののぼり旗には「信州希代の名称 村上義清 生誕の地」があった。こんなところもこだわりがみれて嬉しいですね。
後世に建てた供養塔でしたか、訪れる価値があります。坂城町の町おこしとして村上義清をクローズアップしているんですね。あと村上系の博物館とかあればよかったのですが。

墓所を訪れた後、同じ坂城町にある「びんぐし湯さん館」で温泉に浸る。ここのお土産物スペースで売ってました「村上義清ののぼり旗」。予算の都合で買いませんでしたが…。
関越道の帰り、埼玉県の高坂SAのレストランで「洋食プレート」を食べて帰りました。スパゲティー・エビフライとサラダ・カレーと3つ入っていて950円はオススメ。

すっかり楽しめた日帰り旅行でした。高速1000円を利用して家族とプチ歴史旅行。なかなかいいもんです。今度は夏休み家族で、春日山城を含む新潟一泊旅行か、月山富田城を含む山陰一泊旅行か画策中。
ETC休日1000円割引はお得ぅ~!

荒砥城のそばまできたなら、お勧めスポット。荒砥城入口からほど近い場所にある「にしざわ貯金箱かん」です。(午前9時~午後5時半。年末年始・月曜休み。入館料600円)

オープンしたのが2008年4月1日とあってかなり建物も新しい。貯金箱ってみるもんなの?と最初は半信半疑だった私だが、妻の「行こうよぉ~」の声に押されて入館。入るや結構おもしろい。タレント貯金箱や明治時代や戦中の貯金箱など色々な貯金箱があって意外とおもしろかった。子どもも結構楽しめる。さらに館長の古銭の趣味で、日本や世界のお金がいろいろあってこれもおもしろかった。

信州と言えば清流があり水がうまい。だから「元祖豊年屋」という店に「おしぼりそば」を食べに行く。「おしぼり」とは地元産の「ねずみ大根」のおろしのことで、辛味大根だけにぴりカラで超うまい。つゆに味噌の付け合せもあり、味噌の甘さで好みの味に変えられるのもグー。
お腹がいっぱいになったところで、鉄道好きとしてはやはり気になる「しなの鉄道」へ。しなの鉄道は長野新幹線ができたことで、JRにとってお荷物となった在来線の信州本線を第3セクター化したものです。1997年に誕生したからもう12年も前のことになります。荒砥城がある上山田温泉から一番近いのが「戸倉駅」。駅の周辺は一般的な地方の温泉街という感じ。

しかし驚くべきことは構内の大きさ。さすが元JRだけあって、構内には列車の接近を警告する電光掲示板や首都圏と同じ発車メロディーがあった。ホームもすこぶる長かった。しなの鉄道の車両は通勤系車両の115系と郊外系車両の169系がある赤と銀の車体がなかなかセンスいい。
その走る姿を見たくてわざわざ発車時間に合わせて駅にいったのだが、残念ながら来た列車は乗り入れしているJR塗装色(水色+白)でした。残念。

駅のベンチにはすべてゴザがひいてありました。寒い国で第3セクターならではのならでのちょっと心配りに、感動!


さて、坂城町方面に戻ると「村上義清」の看板が!これは行かなきゃと思い。車を止めて看板をチェック。何々…。村上義清の居館跡?「現在は満泉寺かぁ。居館跡の石碑でもあるかも…行ってみるか!」

「…。寺が工事中…。石碑も何もない…。帰るか…。う~ん納得がいかない!何か村上関係のものをみなきゃ気がすまない!ネットで検索!ん?村上義清公墓所?行ってみるか。」

墓所は小規模な公園として整備されており、駐車場も整備されていた。しかも村上の家紋が!こんなこだわりが結構嬉しい。墓所ののぼり旗には「信州希代の名称 村上義清 生誕の地」があった。こんなところもこだわりがみれて嬉しいですね。
後世に建てた供養塔でしたか、訪れる価値があります。坂城町の町おこしとして村上義清をクローズアップしているんですね。あと村上系の博物館とかあればよかったのですが。

墓所を訪れた後、同じ坂城町にある「びんぐし湯さん館」で温泉に浸る。ここのお土産物スペースで売ってました「村上義清ののぼり旗」。予算の都合で買いませんでしたが…。
関越道の帰り、埼玉県の高坂SAのレストランで「洋食プレート」を食べて帰りました。スパゲティー・エビフライとサラダ・カレーと3つ入っていて950円はオススメ。

すっかり楽しめた日帰り旅行でした。高速1000円を利用して家族とプチ歴史旅行。なかなかいいもんです。今度は夏休み家族で、春日山城を含む新潟一泊旅行か、月山富田城を含む山陰一泊旅行か画策中。
ETC休日1000円割引はお得ぅ~!