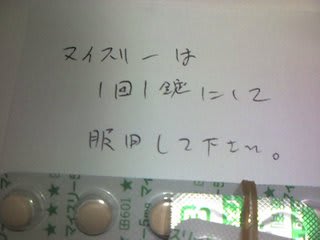私はクリスマスがあまり好きではない。
就職してからというもの、毎年販売応援があり、この時期になると暗い気持ちになる。
昔はあんなに好きだったのに。
なんてたって、サンタを中学1年生まで信じていた私。
それぐらい巧妙に、両親はサンタに扮してくれていた。
父が無理をして草書体で書いたであろうクリスマスカードがいつも添付されていた。
私、妹、弟が目覚める。
「あ!サンタさん来た!ぎゃ~」
歓声を上げ、冷たい廊下を素足で飛びはねた私たち。
各々に贈呈されたおもちゃを抱えて寝ている両親に報告。
「よかったね」
そう言いつつ、彼等は二度寝をするのだった。
いつからか親サンタは現金を渡すようになり、ついには来なくなり…逆に私がボーナスの一部を渡すようになった。
私がサンタになろうとは…。
母はいまだにクリスマス大好き人間だ。
足尾の山奥で育った少女は、バターケーキに頬を落とし、サンタにもらった人形を可愛がった。
大人になり、父と恋をし、毎年二人で過ごした。
私たち子供が産まれてからは、母は必死でケーキを焼き、父はプレゼントを調達した。
明け方まで残業する父も、イヴの日ばかりは早く帰ってきてくれた。
疲れ気味の父から放たれたオーディコロンの香り、
適当に卵をガバガバ入れて作られたペシャンコのケーキの味(母は分量の計測をしない)、
クリスマスツリーの電飾、
石油ストーブの臭い、
クリスマス用の変な帽子
クリスマスソングの熱唱
…あの冬の出来事は幻だったのだろうか。
ときどきそう思う。
「ママね、クリスマスって、んもぅ、大っ好きっ!」
今日も母は電話でそう述べていた。
好きだと言えない私は、また罪悪感を持ってしまう。
好きになれずにすまぬって。
その理由すら考えられぬほど疲れている。
でも、あの幻のクリスマスは大好きだった。
画像は中学1年生のクリスマスプレゼント。ちびまる子ちゃんのオルゴールだ。
実家に置いてはこれず、連れてきてしまった。
今日久々に螺子を回したら、「おどるポンポコリン」が軽快に流れた。
就職してからというもの、毎年販売応援があり、この時期になると暗い気持ちになる。
昔はあんなに好きだったのに。
なんてたって、サンタを中学1年生まで信じていた私。
それぐらい巧妙に、両親はサンタに扮してくれていた。
父が無理をして草書体で書いたであろうクリスマスカードがいつも添付されていた。
私、妹、弟が目覚める。
「あ!サンタさん来た!ぎゃ~」
歓声を上げ、冷たい廊下を素足で飛びはねた私たち。
各々に贈呈されたおもちゃを抱えて寝ている両親に報告。
「よかったね」
そう言いつつ、彼等は二度寝をするのだった。
いつからか親サンタは現金を渡すようになり、ついには来なくなり…逆に私がボーナスの一部を渡すようになった。
私がサンタになろうとは…。
母はいまだにクリスマス大好き人間だ。
足尾の山奥で育った少女は、バターケーキに頬を落とし、サンタにもらった人形を可愛がった。
大人になり、父と恋をし、毎年二人で過ごした。
私たち子供が産まれてからは、母は必死でケーキを焼き、父はプレゼントを調達した。
明け方まで残業する父も、イヴの日ばかりは早く帰ってきてくれた。
疲れ気味の父から放たれたオーディコロンの香り、
適当に卵をガバガバ入れて作られたペシャンコのケーキの味(母は分量の計測をしない)、
クリスマスツリーの電飾、
石油ストーブの臭い、
クリスマス用の変な帽子
クリスマスソングの熱唱
…あの冬の出来事は幻だったのだろうか。
ときどきそう思う。
「ママね、クリスマスって、んもぅ、大っ好きっ!」
今日も母は電話でそう述べていた。
好きだと言えない私は、また罪悪感を持ってしまう。
好きになれずにすまぬって。
その理由すら考えられぬほど疲れている。
でも、あの幻のクリスマスは大好きだった。
画像は中学1年生のクリスマスプレゼント。ちびまる子ちゃんのオルゴールだ。
実家に置いてはこれず、連れてきてしまった。
今日久々に螺子を回したら、「おどるポンポコリン」が軽快に流れた。