10月6日、署名国介護3日目が最終日。
SDCCのプレゼンテーションは昼食時間。
何人が参加してくれるか。
緊張して会議場に向かった。
長文になりましたが、お許しください。


午前9時まだ誰も来ない。
最終日のため帰り支度で集まりが遅れる。
9時40分から、議長がフィリピンで始まる。

ジュゴン保護を進めるために、
二人の研究者から報告。
日本とメキシコを回遊している海ガメが網に絡まって死亡。
日本海ガメ協会と協力して網の改善検討をしているとの報告。
ヘレン・マーシュ教授はそのレポートにすぐに突っ込む。
「意義は分かるが、ジュゴンが少ない状況では現実的ではない」と。

休憩後、マーシュ教授がワークショップを提案。
8人から10人で、6グループに分かれる。


手渡された6つのシナリオには
二つの国にまたがってジュゴンが生息していて、
生活レベルが違う国(ジュゴン保護に使える予算)で、
どのように保護を進めるのかを問うている。
予算を活用する道具としてプリントには、
教育、漁民への網改善の援助、保護区、罰則などがあげらていれる。
ジュゴン保護を進めるうえでの重要な問題提起だ。
短なる規制ではなく、漁師や住民の動機づけも重要な課題だ。

40分の議論をふまえて
各グループから合意が取れたことを報告。
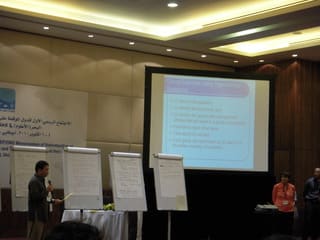
ジュゴン保護について置かれた状況の違いから
議論が白熱するグループも出た。
5年ほど前に参加した沖縄県での混獲対策会議を思い出した。
沖縄県、漁協組合、学者研究者、NGOなどが参加して
レスキュー対策を論議したが、
議論で行き詰ったのが、
レスキューで網をばらした時の網の費用と漁業補償だ。
予算が絡み、国の姿勢が問われる。

昼食休憩。
パソコンの設置やプロジェクターも準備、
IUCN決議など準備した資料の配布など
SDCCプレゼンの準備に追われる。
ところが、プロジェクターが突如動かず、
別の機器と取り換えるために、会議終了後まで
プレゼンが延期。


午後から、議長はアラブ首長国連邦(UAE)。
ワークショップをふまえて次回会議までに、
統一性のある漁師への混獲のアンケートづくりや、
分かりやすい言葉でいくつかの管理計画案を
発表することなどを確認した。
また、多くの国でのジュゴン保護政策を援助するための
専門家グループの立ち上げも確認された。
最後に、第2回署名国会議を2012年に
UAEで開催することを確認した。

午後3時に会議が終了。
事務局への感謝や、個々に記念撮影。
プレゼンがなかなか始まらない。

午後3時25分からサイドイベントの
SDCCプレゼンテーションが始まる。
マーシュ教授をはじめ、
代表や事務局長、すべての事務局員、
タイ、インドなど30人が参加した。
予想以上の集まりだ。

沖縄のジュゴンの生息状況と混獲。
赤土や米軍の訓練などによる海草破壊。
米軍基地建設のための環境アセスの非科学性。
「辺野古にジュゴンがいない」との結論の問題点。
ゼロオプションがない事業推進のアセス。
沖縄ジュゴン保護の地道な取り組みと
IUCN決議とジュゴン訴訟。
沖縄のジュゴンの未来をつくるために、
科学を活用して頑張るとの決意を明らかにした。

次々と質問が出る。
日本の環境アセスの現状、種の保存法の実態、
ジュゴン訴訟の現状など、
日本政府のジュゴン保護の取り組み姿勢に疑問が集中した。
2008年IUCN決議が
UNEP(国連環境計画)とボン条約事務局を動かした。
日本のジュゴン保護運動とジュゴン保護を進める国々とが結びついた。
大きな前進だ。

名古屋のCO10、
10月23日午後1時からのフォーラム
(名古屋学院大学体育館2階会議室)で会いましょう。

ジュゴンの保護者より



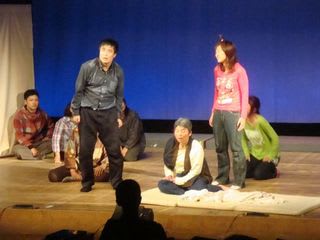



















 どしゃぶりがウソのように いいお天気になった10日
どしゃぶりがウソのように いいお天気になった10日
 月桃の花歌舞団主催のエイサーまつり
月桃の花歌舞団主催のエイサーまつり にブース参加してきました
にブース参加してきました
 焼き鳥など模擬店やバザーもでて
焼き鳥など模擬店やバザーもでて 美味しいモノを食べながらエイサーや三線が聞けるお祭りです
美味しいモノを食べながらエイサーや三線が聞けるお祭りです


 ギター演奏でロックな歌あり
ギター演奏でロックな歌あり 非正規労働廃止や基地問題に取り組んでいる団体からのアピールもありました
非正規労働廃止や基地問題に取り組んでいる団体からのアピールもありました
 2010年国際ジュゴン年&生物多様性年
2010年国際ジュゴン年&生物多様性年

 ストラップやマスコットが人気です
ストラップやマスコットが人気です

 。
。 気持ちの良い天気のせいか
気持ちの良い天気のせいか のせいか良い気分で
のせいか良い気分で








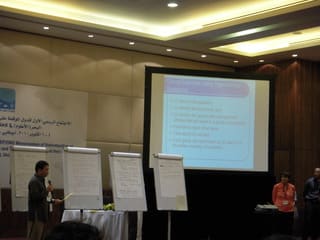








 2010年国際ジュゴン年&国際生物多様性年
2010年国際ジュゴン年&国際生物多様性年



 」と
」と
 「名古屋でCOP10があるの知ってますか?」
「名古屋でCOP10があるの知ってますか?」 「知ってる!“この会議が地球の未来を決める”んやで」
「知ってる!“この会議が地球の未来を決める”んやで」 「よー知ってんなあ。いつから知ってんの?」
「よー知ってんなあ。いつから知ってんの?」 (真ん中の人物)
(真ん中の人物)


 南西インド洋からの報告
南西インド洋からの報告





















