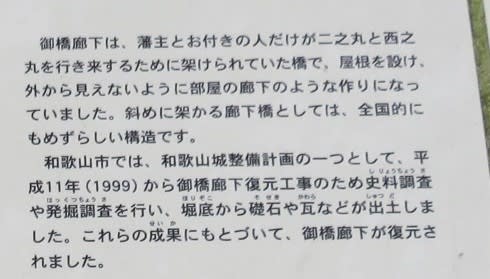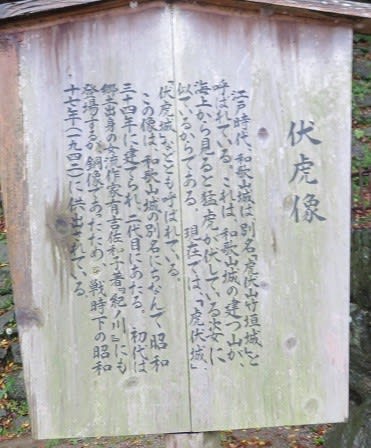和歌山城は和歌山市の中心部に位置する標高48.9mの虎伏山(とらふすやま)に建造され、北部を流れる紀の川を天然の堀し、本丸の北側に二の丸、その外に大きく三の丸が配された梯郭式平山城です。
天正13年(1585)に紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に築城させたのが始まりで、その築城を担当したのが、藤堂高虎でした。
まず、秀長の城代として桑山重晴が入り、慶長5年(1600)には、関ヶ原の戦いで功をたてた浅野幸長が入城。
元和5年(1619)には徳川家康の第10男・頼宣(よりのぶ)が入城し、紀州55万5千石の城となりました。
一の橋・大手門

浅野・徳川時代を通して和歌山城の表門であった一の橋南詰に建つ大手門。

明治42年(1909)に自然倒壊しましたが、昭和58年(1983)一の橋とともに再建工事により復元されました。




伏虎像

江戸時代、和歌山城は別名「虎伏竹垣城」と呼ばれました。
これは、和歌山城の建つ山が虎の伏した姿に似ていたためと言われています。
この像は、和歌山城の別名にちなんで、昭和三十四年に作られました。
(現在の像は二代目にあたり、初代の像は銅製であった為、第二次大戦中、供出させました。)
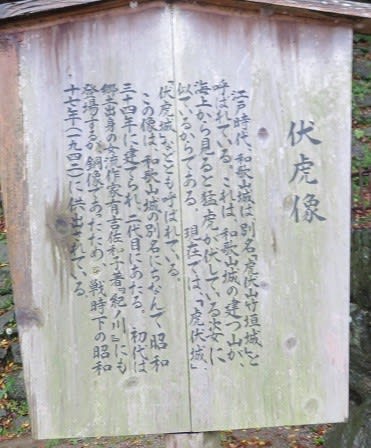
和歌山城の石垣
和歌山城の石垣から時代の移り変わりを感じることができます。
二の丸庭園前には創建期と思われる「野面積み」の石垣。
大手門をくぐって城内に入った所に大きな石の間に小石を詰めた「打ち込みハギ」、さらに歩くと江戸時代の美しく積み上げられた「切り込みハギ」の石垣があります。
また、石垣には紀州特産の青石(緑泥片岩)が多く使われており、転用石や、豊臣・浅野時代の刻印を見ることができます。






 にほんブログ村
にほんブログ村
 神社・仏閣 ブログランキングへ
神社・仏閣 ブログランキングへ


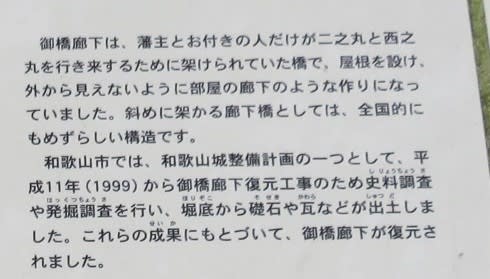


 にほんブログ村
にほんブログ村 神社・仏閣 ブログランキングへ
神社・仏閣 ブログランキングへ