
 ⇒最初にクリックお願いします
⇒最初にクリックお願いします
愛媛新聞社説
2011年04月24日(日)
作家大江健三郎さんの「沖縄ノート」などの記述をめぐり、旧日本軍関係者が出版差し止めなどを求めた訴訟で、最高裁は上告を退ける決定をした。「集団自決」に軍が関与したことを認め、名誉毀損(きそん)を否定した大江さん側勝訴の一、二審判決が確定した。
極めて妥当な決定である。
名誉棄損は判例上、表現に公共性と公益性が認められ、真実の証明か、真実と信じるに相当な理由(真実相当性)があれば責任は問われない。最高裁が、表現の自由の重さを再確認した意義は大きい。
太平洋戦争末期の沖縄戦の際、座間味や渡嘉敷島などで多数の住民が手りゅう弾などを使って集団で自決した。軍による命令が通説とされてきたが、島の元守備隊長らが2005年に「誤った記述で非道な人物と認識される」として大阪地裁に提訴した。
裁判では、軍や元隊長らによる住民への命令の有無などが争われた。
二審判決などは、集団自決に軍の関与があったことは認めたが、元隊長らが直接住民に命令したかどうかは断定できないというものだった。
その上で、沖縄ノートの発刊当時は、隊長命令説が学会の通説といえる状況であり、真実相当性があったと認定。また、記述は高度な公共の利害にかかわり、公益を図る目的だったとした。
一、二審は史実論争に一石を投じた。が、最高裁は「原告側の上告理由は事実誤認などで、民事訴訟で上告が許される場合に該当しない」と判断を避けた。
史実の認定が、法廷に持ち込まれたことには違和感がある。今後とも学会などで論議を深めていくことが必要だ。
この訴訟は教科書検定にも大きな影響を及ぼした。
文部科学省は07年、軍による自決強制の記述の削除・修正を求める教科書検定意見を公表した。係争中が理由の一つだった。
突如、歴史が塗り替えられる。沖縄県民の無念さ、怒りは理解できる。
その後、軍の関与を示す記述への訂正申請を認めたものの検定意見はそのままだ。文科省はこの際、最高裁決定を真摯(しんし)に受け止め、検定意見を撤回すべきである。
歴史教育は時々の為政者や政治情勢に左右されるようなことがあってはならない。この事も確認しておきたい。
二審判決は、批判と再批判の繰り返しの過程を保障することが、民主主義社会の存続基盤である、と述べている。そして仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する、とも。
表現の自由が民主主義の基盤であることを痛感させられる訴訟でもあった。
☆
集団自決訴訟の最高裁判断に関して、愛媛新聞の社説は、軸足は左派ながら、比較的冷静な分析ができている。保存資料として引用した。
この問題を一番熟知しているはずの沖縄2紙の社説よりはるかに裁判の本質をつかんでいる。
>史実の認定が、法廷に持ち込まれたことには違和感がある。今後とも学会などで論議を深めていくことが必要だ。
裁判の核心が「軍命の有無」であることはいうまでもないが、社説が指摘するように、史実の認定を争うのは裁判にはなじまない。 したがって原告側は名誉毀損で提訴し、その名誉を毀損している出版物の出版差し止めを請求し、同時に名誉回復を図るというのがこの裁判の本質である。
■被告大江側「言論(出版)の自由」vs原告元隊長側「人権保護」
言い換えれば被告側の「言論(出版)の自由」に対して、出版(言論)に「よって踏みにじられたに原告側の「人権保護」の対決ということもできる。
結局『沖縄ノート』の内容に間違いがあっても、表現の自由を守るためには「寛容さ」をもって我慢せよ、というのが最高裁の判断ということになる。
人権保護には喧しいはずの日本の司法が両隊長の人権を踏みにじってでも、ノーベル賞作家の表現の自由を守れと判断したのだ。
大阪高裁が、尊敬するノーベル賞作家の「表現の自由」と 侮蔑すべき元軍人の「人権保護」を秤にかけたらどうなるか。
大阪交際が、判決を下した経緯はこのエントリーに詳しい。
⇒ノーベル賞作家への配慮が裁判官を萎縮させた!秦郁彦氏
大江健三郎氏が40年前に『沖縄ノート』を書くにあたって真実と信じ込んだ『鉄の暴風』は、その後の検証により伝聞と風評のみのデタラメな本だということが分かっている。 当然それを引き写した『沖縄ノート』に間違いがあることは最高裁も認めるところである。
だが、最高裁が次のように「無価値でない」と決め付けることで、大江氏が増長して「高校生にも読ませたい」みたいな思い上がった発言をすることに危惧を覚える。
>仮に後の資料から誤りとみなされる主張も言論の場で無価値とはいえず、これに対する寛容さこそが自由な言論の発展を保障する
大江氏の意味不明な文体で書かれ、しかも事実誤認の入り交じった『沖縄ノート』が、『鉄の暴風』と並んで沖縄戦記のバイブルとなることを危惧する。
沖縄紙に識者として頻繁に登場する小牧薫氏は、被告側支援団体の事務局長でありながら『沖縄ノート』の内容に問題があることを認めているくらいだ。
小牧氏がやしきたかじんの「そこまでいって委員会」に高嶋伸欣琉球大学名誉教授と二人で出演したときの様子を、過去エントリーから次に抜粋引用する。
小牧さんの反論。
「私たち沖縄戦裁判支援連絡会は、大江さんや岩波書店を支援しているのではありません。あの裁判が不当な沖縄戦の事実の歪曲をしてるから。沖縄戦の真実を明らかにして広めたいと活動してる。だから勝谷さんが大江さんの『沖縄ノート』をどう思われるかは、それは勝手なことで」
辛坊さんが「じゃあ小牧さんは『沖縄ノート』についてはどうお考えですか?」とGJツッコミ。
すると小牧さん、「内容については一定の批判があります」。(ぼやきくっくりさん)











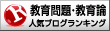


 クリックお願いします
クリックお願いします









