(修行 六)
ある日のことだ。
鍛錬を終えて噴き出た汗を拭き取ろうとしていた折に、読経の時間であるはずにも関わらず辺りを見回しながら一人の小坊主近づいてきた。
大きく盛り上がった肩の三角筋にうっとりとした表情を見せられては、さすがのごんすけも声を荒げるしかなかった。
「読経の時間ではありませぬか」
「いや、そうなのだ。用足しのついでに……」
そそくさと立ち戻る小坊主の背を見ながら、居心地の良い生活に慣れることに違和感を感じるごんすけだった。
「このままでいいさ」という思いに対して「いやだめだ」と霞がかった抗う気持ちがどうしても消えないでいた。
ごんたに対する敬慕の念が消えぬのも、その一つの因かもしれない。
久しぶりに立ち寄った沢庵和尚に「おとうはどうしてる」
と問いかけても、答えは
「お前が安穏な生活を送ることが、ごんたの喜びとなるのじゃ」と無碍がない。
ごんたの日々については、一切口にしなかった。
五年目を過ぎた頃には背も伸び五尺ほどとなり、他の小坊主の中に有っても見劣りはしない。
いや、筋骨隆々となったごんすけでは、遠く離れた場所からでもひと目で確認できた。
遠くから声をかけられることもしばしばだった。
しかしそれがゆえに、一挙手一投足を監視されているようで、息苦しさを感じ始めていた。
門前には毎日のように村の若い娘たちが集まっている。
掃き掃除で竹箒を動かすだけで大歓声があがる。
その声の方に顔を向ければ、今度は嬌声があがる。
右に歩を進めれば右に移動し、左へと戻れば今度は左にと娘たちも動く。
門の陰になり姿が見えなくなると、裏手に回る者やら禁を破って中に入ろうとする者すら出てくる。
何度叱っても、娘たちは動じない。
それどころか、その小言を言う小坊主にあからさまな嬌態さえ見せる始末だった。
















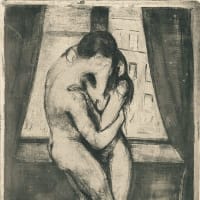








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます