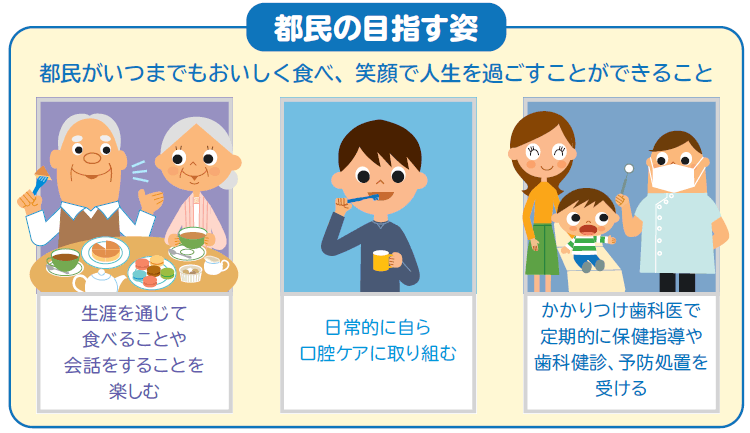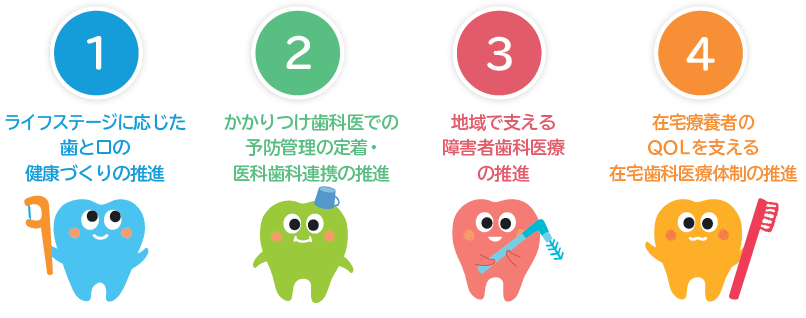「働き方改革」から取り残された教師たち
文春オンライン
2018/05/01 内田 良さん
先週、毎日新聞の調査により、教員の過労死がこの10年間で63人に上ることが明らかとなった。
ただしこれは、「少なくとも」と言わなければならない。
なぜなら職員室では、過労死認定の重要な根拠となるはずの労働時間が、そもそも把握されてこなかったからだ。
「働き方改革」を掲げている政府は、これまで教員の過労死の数を把握しておらず、認定された数が公になるのはこれが初めてのことだ。
二つのブラック 「長時間労働」と「不払い労働」
学校という職場には、二つのブラックとそれを支える一つの法律がある。ブラックの一つ目は、「長時間労働」である。
文部科学省が2016年度に公立校の教員を対象に実施した「教員勤務実態調査」では、「過労死ライン」(月80時間以上の時間外労働)を超える教員が小学校で3割、中学校で6割ということが明らかになっている。
ブラックの二つ目は、時間外労働の対価が支払われていない、すなわち「不払い労働」である。これは「本当は残業代が出るはずなのに、会社側が支払わない」といったブラック企業の話とは事情がまったく異なる。
公立校の教員はそもそも残業をしていないことになっている。学校に夜遅くまでいるのは、単に「好きで残っている」という位置づけだ。
約半数が「過労死ライン」を超える
一点目の「長時間労働」について、10年ぶりに実施された前出の「教員勤務実態調査」(速報値)は、教育関係者の予想を裏切ることなく、改めて学校現場の過酷な勤務状況を明らかにした。
2006年度に実施された前回調査と比較すると、2016年度は、公立校の学校内での労働時間は、小学校で平日43分、土日49分、中学校で平日32分、土日109分の増加となった。労働時間が週60時間以上だった教諭は小学校で33.5%、中学校では57.7%に達した。また週65時間以上は、小学校で17.1%、中学校で40.7%にのぼった。
2016年度の文部科学省「「教員勤務実態調査」をもとに筆者が作図。(1)よりも下方が一ヶ月あたり80時間、(2)よりも下方が一ヶ月あたり100時間の時間外労働に該当する
2
労働時間が週60時間というのは、おおよそ月80時間の残業に換算でき、週65時間の労働は月100時間の残業に換算できる。多くの教員がいわゆる「過労死ライン」(1ヶ月間に約100時間以上、または2~6ヶ月間に毎月約80時間以上の残業)を超えている。
なお、これらのデータには、持ち帰り仕事の時間は含まれていない。教員は、授業の準備や試験問題の作成などを自宅でこなすことも多い。それらの仕事を含めるならば、過労死ラインを超える教員はさらに増えることになる。
給特法下では「自主的に残っている」!?
二点目の「不払い労働」について、これは昨今話題になっている高度プロフェッショナル制度や裁量労働制と同じで、教員の給与制度は「定額働かせ放題」となっている。
公立学校の教員には、サラリーマン同様に、労働基準法が適用される。だが、1971年に制定された給特法(正式には「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)によって、時間外労働や休日労働については、割増賃金(残業代)を支給しなければならないことを定めた労働基準法第37条の適用外とされている。
すなわち給特法のもとでは、基本的に教員の労働には残業(代)が発生しない(詳しくは拙稿「残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度」)。
いま全国の先生たちは、過労死ラインを超えるほどに働いている。だけれど、それはみずからの趣味として自主的に学校に居残っているだけであって、それは残業ではないし、もちろん残業代が支払われる必要もない、というのが給特法の規定である。
これにより、学校現場では労働時間をカウントする必要性がなくなってしまった。過労死認定においては具体的な残業時間が重要な根拠となるはずなのだが、そもそも労働時間がわからないのだ。
ブラック労働に無自覚な教師たち
職員室は、ブラック企業も真っ青なほどに異常な労働環境である。
だからこそマスコミは、連日のように教員の異常な働き方を報道している。また教育行政の対応も進み、昨年12月26日には、ついに文部科学省は「学校における働き方改革に関する緊急対策」を発表するに至った。
ところが、どうにも職員室にいる先生たちが、この盛り上がりに付いてきているように見えない。むしろいまも、夜遅くまで働き続ける教員を讃える声や、部活動をもっと充実させようという声が聞こえてくる。
よくよく考えれば、それも無理はない。職員室には、「教員は子どものために献身的に尽くすものである」「部活動指導してこそ一人前」という文化がある。労働時間や給料に関係なく、子どもに向き合う姿が美化される。
いつも自分の時間を削って遅くまで仕事を頑張り、それが翌日に子どもの楽しそうな表情や真剣なまなざしとなって返ってきたとき、教員はその苦労が報われる。それをマスコミやあるいは私のような外野が、「ブラック」と呼んでいるのだ。
上限規制のなかで「教師冥利」を
子どもからそうしたポジティブな反応を得られるのは、まさに教職の大きな魅力の一つである。それは、私自身も大学教員として同じことを感じる。私が出した課題に対して、学生が熱心に取り組む姿、それを讃えたときに学生が返してくれるうれしそうな表情は、何にも代えがたい充実感を私に与えてくれる。
だが、そうだとしても、私はその「教師冥利」とも言える充実感は、一定の上限規制がかかった時間内で得られるのが最善だと考える。そのなかで、子どもの楽しそうな表情や真剣なまなざしに出会えることこそを目指すべきである。
教員というのは「教育者」である前に「労働者」である。労働者として健全な環境のもとで仕事ができてこそ、教育者としてじっくりと子どもに向き合えるのではないだろうか。











![[山名美和子]の列島縦断 「幻の名城」を訪ねて (集英社新書)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51VzvZoa49L.jpg)