【新証言】日本人も標的に「私たちの値段は540万円」中国系犯罪組織が“数千人”監禁「殴られるのは全く珍しくない」偽の求人で連行された被害者語る ミャンマー
ミャンマーで、中国系犯罪組織が外国人数千人を監禁し、特殊詐欺実行役を強要しているという。アメリカの調査機関によると、中国系犯罪組織による特殊詐欺の被害は、年間10兆円近くに上り、その拠点は東南アジアで急拡大しており、日本人も拉致の対象になっているという。
きっかけは「偽の求人広告」…中国系犯罪組織が数千人を監禁
軍によるクーデターから4年を迎えたミャンマーで、混乱に乗じて中国系犯罪組織が勢力を拡大している。
ターゲットには、日本人もいるという。
ミャンマーの中国系犯罪組織は、今も外国人など数千人を監禁しているとみられている。新たな証言からその姿が見えてきた。
1月、訪問先のタイで中国人俳優の男性が行方不明となり、その後、隣国ミャンマーで丸刈りの姿で保護された。 男性は、SNSで映画の仕事があると騙されてタイを訪問した。
そこで犯罪組織に拉致され、特殊詐欺に加担するよう強要されていたという。アメリカの調査機関によると、中国系犯罪組織による特殊詐欺の被害は、年間10兆円近くに上り、その拠点は東南アジアで急拡大している。
内戦で混乱が続くミャンマーでは特に活動が活発で、タイの市民団体によると、男性の拉致に関わった組織では、日本人26人を含む、23カ国の約6500人が「掛け子」などの詐欺の実行役をさせられている可能性があるという。
知られざる組織の実態を語ったのは、中国・上海に住む許博淳さんだ。許さんは2023年、3カ月間に渡ってミャンマーで監禁されていた。そのきっかけは「偽の求人広告」だった。 特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: その頃(2023年)私は失業中で、SNSのグループで日払いのアルバイトを探していました。
そこで「月給21万5千円(1万元)のエキストラ俳優」という募集を見つけました。
今思い出してみても、特に違和感はありませんでした。
許さんが誘い出されたのは、中国・雲南省にあるミャンマーとの国境の街シーサンパンナだった。
指定されたマンションを訪れると、3人の若い男が待っていたという。
特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: 携帯電話と身分証を(男たちに)預けるように言われました。
脅す様子はなく、「後でホテルに送る際に返す」と…。(出演するのは)超大作の映画なので、機密を守る必要があるとのことでした。 しかし、案内されて向かった山の中で、許さんは初めて自分が騙されていたことに気付いた。
特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: 木々の間から10人以上の迷彩服を着た男たちが現れたんです。
山を下りたところで振り返ると、他の山々からも同じように迷彩服の人たちが騙された人たちを連れてくるのが見えました。
私たち以外に何十人も…。 脅されながら許さんが連れて行かれたのは、ミャンマー北部に位置するラウカイ県だ。
この地域は、中国系犯罪組織がいくつも拠点を構える特殊詐欺の中心地として知られ、中国の国営メディアによると、2024年だけで5万3千人以上の中国人が逮捕されている。
ここで許さんは、人身売買の「商品」として、特殊詐欺を扱うグループに「買い取られた」という。 特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: 私たちの値段は540万円(25万元)だと言われました。
「紅蓮ホテル」の看板が見え、「紅」と「蓮」の字が書かれていました。ここが(詐欺グループの)拠点でした。
この一つの建物に約1400人が住んでいます。建物全体がひとつの詐欺グループです。私たちのチームは、主に東南アジアの中国人をターゲットにしていて、それぞれ机にはパソコンと4台のiPhoneがありました。
監禁され、特殊詐欺の「掛け子」をさせられる毎日だったという。「成績」が悪いと、恐ろしい罰が待っていた。
中国系の詐欺グループで撮影された映像では、何人もの被害者が激しい暴行を受けている。 特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: こんなふうに殴られるのは、全く珍しくありません。
いつものことです。お尻から下ばかりを殴られ、腰は殴られませんでした。腰(腎臓)は「売れる部分」で、口は電話をかけるため、手は文字を打つために必要だからです。
2150万円もの身代金を払い解放
24時間、銃を持った組織のメンバーに監視され、脱出が不可能な監禁生活を余儀なくされた。死と隣り合わせの許さんを救い出したのは、家族が支払った多額の身代金だった。
特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: ある民間団体が詐欺グループとの交渉に成功し、まず1330万円(62万元)の現金を支払いました。
母親とビデオ通話がつながった瞬間、自然と涙がこぼれ落ちました。それまでは泣くこともできなくて…。 最終的に支払った金額は、日本円で2150万円(100万元)だ。家族がマンションを手放し、さらに借金をして工面した。
許さんは、日本人も既に被害にあっていると警鐘を鳴らす。 特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: たくさんの日本人や韓国人が騙されて送られたと聞きました。
日本人が入っている部屋には、数十人が閉じ込められていたそうです。
さらにタイの市民団体によると、犯罪組織では、日本人を拉致すると5000ドルの報酬が支払われるという話が新たに出ているという。
特殊詐欺グループに拉致された許博淳さん: 詐欺グループは支配する全ての人の携帯電話をコントロールしていて、SNSのグループやチャットにまで深く入り込んでいます。自分の街に来て直接会うことができない人は、絶対に信用してはいけません。
現地の日本大使館では、犯罪に巻き込まれないよう注意喚起している。 (「イット!」2月6日放送より)










 </picture>
</picture>

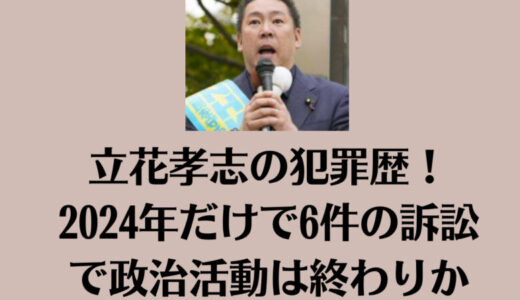




 </picture>
</picture> </picture>
</picture> </picture>
</picture>
 </picture>
</picture>