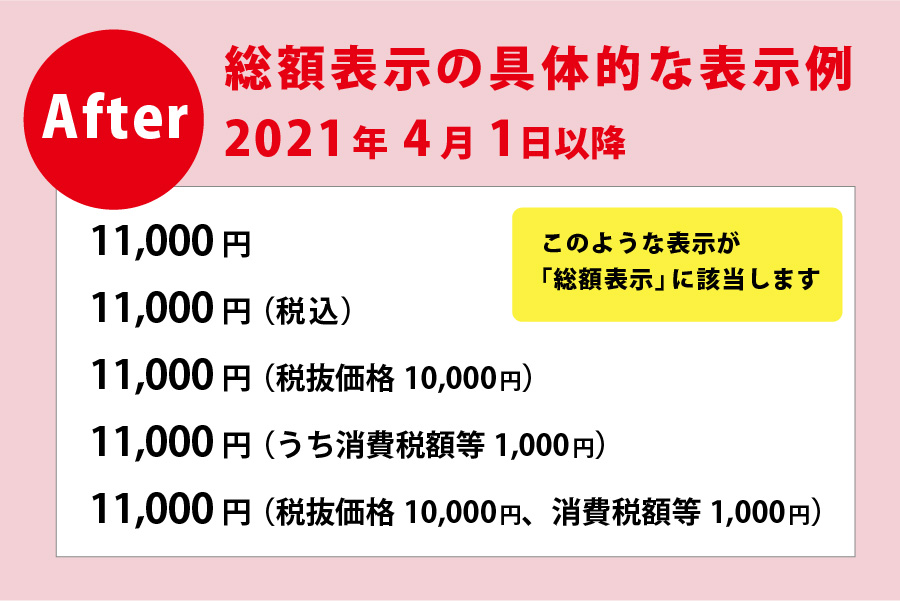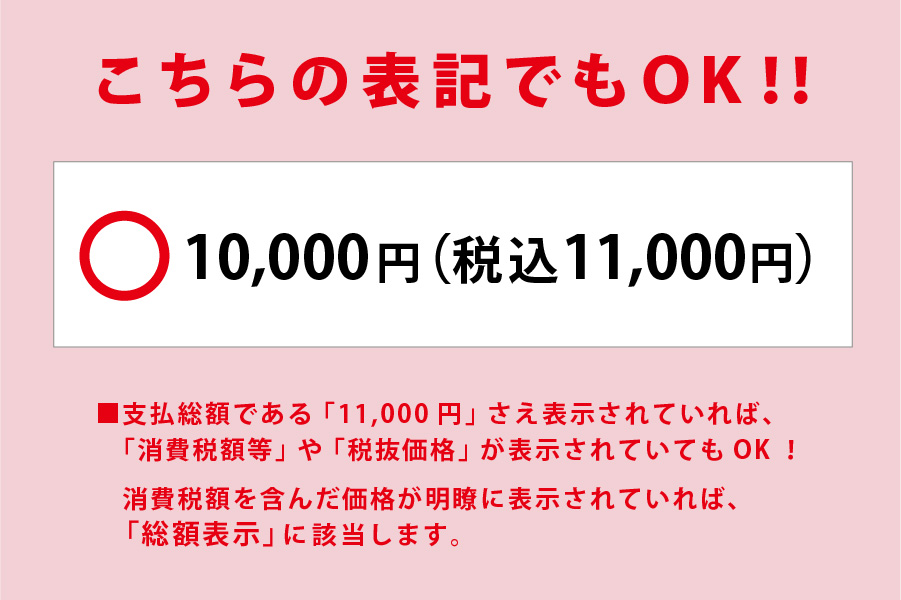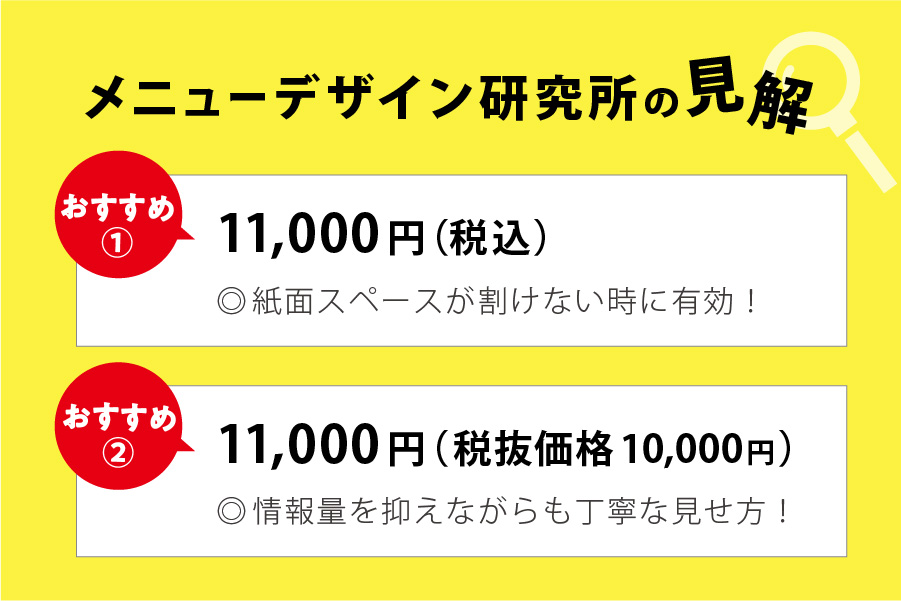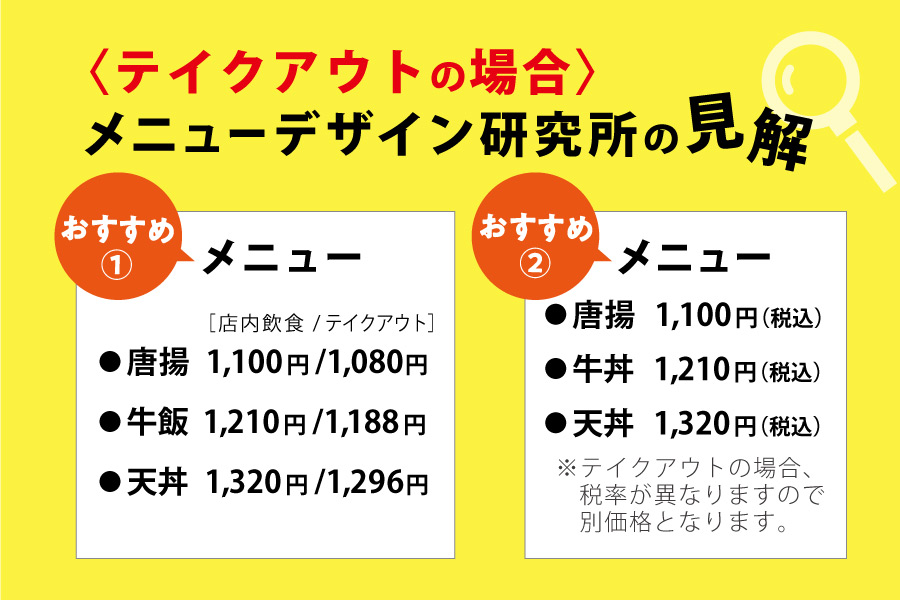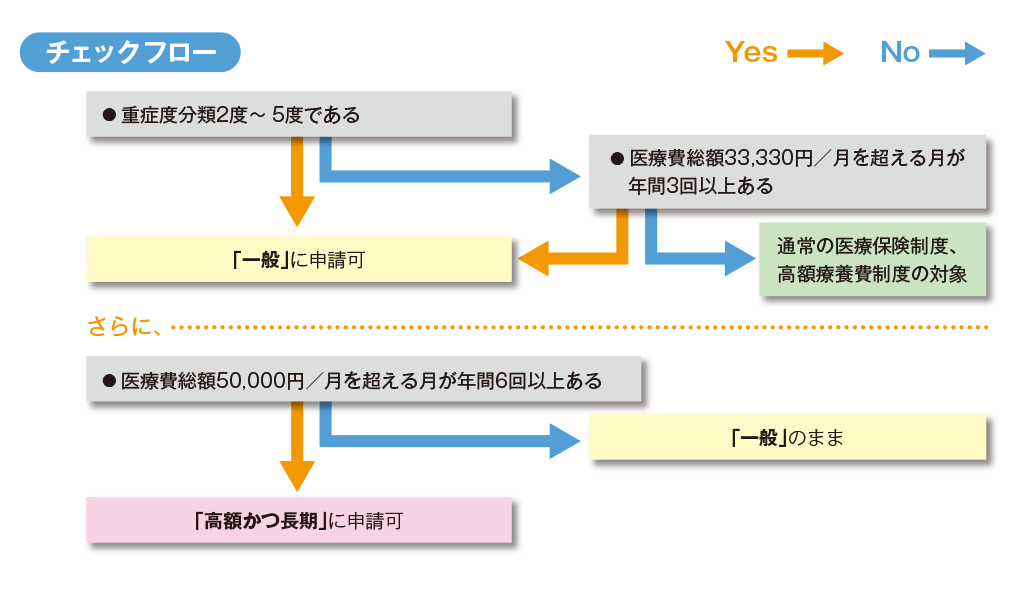働く方
ご家族の方
支援する方
1 自殺予防対策の施策の経過
年月日 施策の内容 備考
昭和33年度(1958) 厚生白書が「青少年の自殺者数が急増し自殺死亡率が世界一になった」ことに言及 自殺対策白書平成19年度版
昭和45年(1970) 「自殺予防行政懇話会」発足 日本自殺予防学会の前身
昭和46年(1971)10月 「いのちの電話」開設(東京) 民間
昭和52年(1977) 「日本いのちの電話連盟」結成 民間
昭和58年(1983)「日本自殺予防学会」発足
昭和59年(1984)2月 設計技師の過労自殺(未遂)を労災認定 精神障害の初認定
平成8年(1996)3月 電通事件東京地裁判決。仕事と自殺の因果関係認定 民事訴訟
平成12年3月最高裁判決
平成10年(1998)自殺者数が31,755人。前年比35.2%の増加。以後3万人台継続
平成12年(2000)年厚生省が「健康日本21(21世紀における国民健康づくり運動)」で自殺予防対策に言及。平成16年度までに17都道府県が取組
平成12年(2000)年8月 労働省が「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を通達 平成18年の指針策定に伴い廃止
平成13年度(2001)厚生労働省がいのちの電話の相談活動に補助金の交付開始
平成13年(2001)厚生労働省が12月1日を「いのちの日」と定める。
平成13年(2001)12月 厚生労働省が「職場における自殺の予防と対応」を作成 平成19年10月改訂
平成14年(2002)12月厚生労働省の「自殺防止対策有識者懇談会」が「自殺予防に向けての提言」
平成15年(2003)世界保健機関(WHO)の国際自殺予防学会が毎年9月10日を「世界自殺予防デー」と定める。
平成17年(2005)12月自殺対策関係省庁連絡会議が「自殺予防に向けての政府の総合的な対策について」をとりまとめ
平成18年(2006)3月 厚生労働省が都道府県知事等に対し、「自殺予防に向けての総合的な対策の推進について」を通知 3月31日付け障発第0331010号
平成18年(2006)3月 労働者の心の健康の保持増進のための指針 平成27年11月改正
平成18年(2006)6月自殺対策基本法公布(6月21日。同年10月28日施行)
平成18年(2006)10月国立精神・神経センター精神保健研究所に「自殺予防総合対策センター」を設置
平成18年(2006)11月「自殺総合対策会議」開催(第1回)
内閣府が「自殺総合対策の在り方検討会」開催。平成19年4月「総合的な自殺対策の推進に関する提言」をとりまとめ
平成18年(2006)12月厚生労働省が自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会開催
平成19年(2007)4月内閣府に「自殺対策推進室」を設置
平成19年(2007)6月 「自殺総合対策大綱」を閣議決定
同大綱において9月10日〜16日を自殺予防週間と定める。
平成19年(2007)11月 「いきる・ささえる相談窓口」を開設 平成28年4月「自殺総合対策推進センター」の発足に伴い、「いのち支える相談窓口」へ
平成19年(2007)12月自殺予防総合対策センターが「自殺対策ネットワーク協議会」を開催
平成20年(2008)2月内閣府が「自殺対策推進会議」を開催
平成20年(2008)3月自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書
平成20年(2008)自殺予防総合対策センターが「自殺予防と遺族支援のための基礎調査」を実施
平成20年(2008)10月自殺対策加速化プランの決定にあわせ、自殺総合対策大綱の一部を改正
平成21年(2009)1月 厚生労働省が「現下の経済情勢を踏まえた緊急の自殺予防対策について」を通知 地発第0130005号・基監発第0130001号・基安労発第0130001号・職総発第0130001号
平成21年(2009)1月 厚生労働省が「現下の経済情勢を踏まえた自殺予防対策について」を通知 健総発第0130005号・社援総発第0130001号・障精発第0130001号
平成21年(2009)1月 自殺に傾いた人を支えるために-相談担当者のための指針- -自殺未遂者、自傷を繰り返す人、自殺を考えている人に対する支援とケア- 20 年度厚生労働科学研究費補助金 こころの健康科学研究事業
自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究
平成21年(2009)1月 自死遺族を支えるために〜 相談担当者のための指針〜自死で遺された人に対する支援とケア 平成20年度厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業
自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究
平成21年(2009)3月 自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会報告書 厚生労働省・自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検討会
平成21年(2009)3月日本臨床救急医学会が「自殺未遂患者への対応 救急外来(ER)・救急科・救命救急センターのスタッフのための手引き」を策定
平成21年(2009)4月 厚生労働省、「自殺防止対策事業の実施について」を通知 4月1日付け障発第0401006号
平成21年(2009)11月
自殺対策100日プラン〜年末・年始に向けた「生きる支援」の緊急的拡充へ〜 11月27日、内閣府・自殺対策緊急戦略チーム
平成22年(2010)5月
自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて 5月28日 自殺・うつ病等対策プロジェクトチーム
平成22年(2010)7月自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて(政策レポート)
平成22年(2010)9月 内閣府が「自殺対策タスクフォース」を開催 平成24年9月廃止
平成23年(2011)11月 内閣府が、新たな自殺総合対策大綱の案の作成のため、「官民が協働して自殺対策を一層推進するための特命チーム」を開催 全8回
平成24年(2012)5月「平成23年度自殺対策に関する意識調査」報告
平成24年(2012)8月内閣府が、地域自殺対策緊急強化基金を活用した事業に関し検証及び評価を行うため、「地域自殺対策緊急強化基金検証・評価チーム」を開催
平成24年(2012)8月 「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」を閣議決定 8月28日
平成24年(2012)9月内閣府が自殺総合対策会議の下に「自殺対策の機動的推進のためのワーキングチーム」を設置し、開催
平成28年(2016)4月 「自殺対策基本法」改正 (4月1日施行)
平成28年(2016)4月 「自殺総合対策推進センター」設立 「自殺予防総合対策センター」を改組
平成28年(2016)4月自殺総合対策を推進する所管が「内閣府」から「厚生労働省」に変更
平成29年(2017)7月 「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」を閣議決定 28年の法改正を踏まえて(7月25日)
2 「職場における自殺の予防と対応」
最近の自殺予防対策が極めて大切であることから、「職場における自殺の予防と対応」がとりまとめられて公表されています。掲載されている項目は、次のとおりです。
第1章 自殺の実態
1 自殺者数の推移
2 事業所における自殺既遂者調査の概要
(1) 精神障害による自殺で労災認定された51例調査結果
(2) 長時間労働と自殺
3 家族、職場が気づいた自殺の兆候
第2章 産業精神保健の動向
1 精神障害等の労災認定
(1) 精神障害等による労災補償の動向
(2) 自殺の労災認定
2 職場の精神保健に関連する法的側面
(1) 労働安全衛生法に基づく健康管理
(2) 労働衛生分野を中心とした行政の流れ
(3) 企業と安全配慮義務
3 企業におけるリスクマネジメント
(1) 事例の概要
(2) 本事例のストレス評価と就業上の措置
第3章 自殺の予兆(どのような人に自殺の危険が迫るのか)
1 自殺予防の十箇条
2 自殺の直前のサイン
第4章 日常の配慮と相談対応
1 日常からの配慮
2 自殺の予兆が見られる人への対応
3 心の病気で治療中の人へのかかわり
4 自殺未遂者への長期的なかかわり
5 同僚や部下のことで相談に来た人への対応
参考判例
第5章 相談体制
1 企業における心の健康相談体制
(1) 心の健康相談体制
(2) 相談窓口
(3) 電話、E-mail などの活用
(4) 相談先の表示と相談のためのツール
(5) 健康診断の問診を充実しよう
2 中小事業場における相談体制づくり
(1) 中小事業場のメンタルヘルス対策の現状
(2) 地域の社会資源の活用
(3) コンソーシアムEAP(複数事業場が集まって外部EAPと契約する方法)
(4) 中小事業場におけるメンタルヘルスの対策事例
第6章 自殺後に遺された人への対応
1 自殺のポストベンション(事後対応)
2 職場でのポストベンションの原則
3 遺族への対応
第7章 自殺への予防対応の事例
「職場における自殺の予防と対応Q & A」
3 自殺対策基本法
近年、年間約3万人の方が自殺で亡くなられていることは、誠に痛ましい事態であり、深刻に受け止める必要があります。
自殺は、個人的な問題としてのみとらえるべきものではなく、その背景に様々な社会的要因があることを踏まえ、総合的な対策を早急に確立すべき時期にあります。
このため、平成18年に自殺対策基本法が制定されました(平成18年法律第85号)。その概要は、次のとおりです。
項 目 内 容
目的 自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与すること。
1 自殺対策の基本理念
(1) 自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならないこと。
(2) 自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならないこと。
(3) 自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならないこと。
(4) 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならないこと。
2 国、地方公共団体、事業主、国民のそれぞれの責務
3 政府による自殺対策大綱の策定と、国会への年次報告
4 国・地方公共団体の基本的施策
(1) 自殺の防止等に関する調査研究の推進並びに情報の収集、整理、分析及び提供の実施並びにそれらに必要な体制の整備
(2) 教育活動、広報活動等を通じた自殺の防止等に関する国民の理解の増進
(3) 自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上
(4) 職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備
(5) 自殺の防止に関する医療提供体制の整備
(6) 自殺する危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための体制の整備
(7) 自殺未遂者に対する支援
(8) 自殺者の親族等に対する支援
(9) 民間団体が行う自殺の防止等に関する活動に対する支援
5 内閣府に、関係閣僚を構成員とする「自殺総合対策会議」を設置
出典:自殺対策白書平成20年版
4 自殺総合対策大綱
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法第8条に基づいて、平成19年6月8日に閣議決定されて定められました。さらに、自殺対策加速化プランの決定にあわせて、平成20年10月31日の閣議決定により一部が改正されましたが、初めて全体的な見直しが行われ、平成24年8月28日に「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。
その概要は、次のとおりです。
国、地方公共団体、関係団体、民間団体等が緊密な連携を図りつつ、国を挙げて自殺対策に取り組み、一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指すものとしています。
自殺総合対策における基本認識として、
〈自殺は、その多くが追い込まれた末の死〉
〈自殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問題〉
〈自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い〉
を示しています。
自殺総合対策の基本的な考え方としては、
(1) 社会的要因も踏まえ総合的に取り組む
(2) 国民一人ひとりが自殺予防の主役となるよう取り組む
(3) 段階ごと、対象ごとの対策を効果的に組み合わせる
(4) 関係者の連携による包括的な生きる支援を強化する
(5) 自殺の実態に即した施策を推進する
(6) 施策の検証・評価を行いながら、中長期的視点に立っ て、継続的に進める
(7) 政策対象となる集団毎の実態を踏まえた対策を推進 する
(8) 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国 民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する
という八つの基本的考え方を示しています。
また、当面、特に重点的に取り組むべきものとして、9の施策を設定しています。
さらに、自殺対策の数値目標を自殺死亡率の減少割合で設定し、平成28年までに、自殺死亡率を17年と比べて20%以上減少させることを目標としています。
出典:自殺総合対策大綱(見直し後の全体像)
5 国・地方公共団体等の自殺予防対策の推進体制
自殺対策基本法の制定を受けて、平成18年10月に国立精神・神経研究所に自殺予防総合対策センターの設置、平成18年11月に内閣府に「自殺総合対策会議」の設置、平成19年4月に内閣府に自殺対策推進室の設置などの体制が整えられたほか、都道府県における自殺問題担当部署の明確化、自殺対策連絡協議会の設置などが進められた。
自殺対策の推進体制
出典:自殺対策白書平成20年版
6 自殺総合対策推進センター
自殺総合対策推進センターは、平成28年4月1日に施行された改正自殺対策基本法の新しい理念と趣旨に基づき、学際的な観点から関係者が連携して自殺対策のPDCAサイクルに取り組むためのエビデンスの提供及び民間団体を含め地域の自殺対策を支援する機能を強化することを使命としています。
センターには4つの研究室があります。
地域連携推進室
都道府県及び市区町村における「いのち支える自殺対策行動計画」策定の支援を、地域自殺対策推進センター(都道府県・指定都市に設置)とのネットワークを活用して進めます。また、地域特性に応じた「いのち支える自殺対策」パッケージ提案の基礎となる、先進的な取り組みの調査・分析研究を行います。
自殺未遂者・遺族支援等推進室
自殺未遂者は命を取り留めた後の複雑な心境に、自死遺族は死別に伴う強い悲嘆に見舞われながら、様々な困難を抱えて日常生活を送っています。こうしたことを踏まえ、自殺未遂者・遺族支援等推進室では、個別の複雑な背景を十分に理解した上で、多様な側面から支援し、心理的影響を緩和することを目的としています。
自殺総合対策研究室
国及び地方公共団体の自殺対策に資する調査研究と研究機関、大学、民間団体等との連携・支援に係わる調査研究を行い、自殺総合対策推進に関する全般的な研究開発につなげます。
自殺実態・統計分析室
国の政策および民間団体を含む地方自治体レベルの取組をより推進するため、各種の研究成果や統計情報に基づき、地域の自殺の実態を把握しやすくする情報提供と自殺対策の改善に資する政策評価に関する事業および研究開発を行います。
詳しくは、自殺総合対策推進センターホームページをご覧ください。
7 都道府県等における自殺対策
都道府県における自殺対策は、平成18年の自殺対策基本法の制定・施行から急速に進められつつあります。
各都道府県等のホームページをご覧ください。
自治体 運営 名称
北海道 北海道立精神保健福祉センター 北海道地域自殺予防情報センター
青森県 青森県立精神保健福祉センター 自殺対策
岩手県 岩手県精神保健福祉センター 自殺対策
秋田県 健康福祉部 健康推進課 調整・地域保健・自殺対策班 心のセーフティーネット「ふきのとうホットライン」
福島県 保健福祉部自立支援総室 障がい福祉課 こころの健康や自殺対策
茨城県 保健福祉部障害福祉課 自殺対策
栃木県 障害福祉課精神保健福祉担当 自殺総合対策
群馬県 群馬県こころの健康センター 自殺予防に向けた取り組み
埼玉県 保健医療部疾病対策課 総務・精神保健担当 埼玉県の自殺対策について
さいたま市 保健福祉局保健部健康増進課 保健係 さいたま市の自殺対策について
東京都 福祉保健局保健政策部保健政策課 自殺総合対策東京会議
東京都 東京都立中部総合精神保健福祉センター 自殺予防コーナー
東京都 東京都立多摩総合精神保健福祉センター センターホームページ
神奈川県 自殺対策の概要 かながわ自殺対策推進センター
川崎市 川崎市精神保健福祉センター 自殺対策
新潟県 新潟県精神保健福祉センター センターホームページ
富山県 厚生部 健康課 精神保健福祉係 富山県自殺対策関連情報
石川県 石川県こころの健康センター センターホームページ
福井県 健康福祉部 障害福祉課 精神障害福祉グループ 福祉相談
長野県 長野県精神保健福祉センター 長野県自殺対策推進センター
岐阜県 岐阜県精神保健福祉センター 自殺予防のために
静岡県 静岡県精神保健福祉センター 静岡県自殺予防情報センター
愛知県 健康福祉部障害福祉課 自殺総合対策サイト(あいち自殺対策情報センター)
名古屋市 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課精神保健福祉係「こころの絆創膏」運営管理担当 こころの絆創膏
三重県 三重県自殺対策推進センター 三重県自殺対策推進センター
滋賀県 滋賀県立精神保健福祉センター 滋賀県内の自殺予防に関する相談窓口
京都府 京都府精神保健福祉総合センター センターホームページ
京都市 京都市こころの健康増進センター センターホームページ
大阪府 大阪府こころの健康総合センター 自殺対策のページ
堺市 健康福祉局健康部 精神保健福祉課 堺市 自殺対策のページ
兵庫県 健康福祉部 障害福祉局 障害福祉課 兵庫県自殺対策センターについて
鳥取県 福祉保健部健康政策課 鳥取県の自死対策
島根県 健康福祉部 障がい福祉課 島根県自死総合対策トップページ
広島県 広島県立総合精神保健福祉センター(パレモア広島) センターホームページ
山口県 健康福祉部 健康増進課 自殺対策総合ページ
徳島県 徳島県精神保健福祉センター とくしま自殺予防センター
香川県 健康福祉部 健康福祉総務課 健康づくりグループ 自殺予防対策ホームページ
愛媛県 保健福祉部健康衛生局健康増進課 自殺対策について
高知県 精神保健福祉課 自殺を防ぐために
福岡県 福岡県精神保健福祉センター 福岡県地域自殺予防情報センター
佐賀県 佐賀県健康福祉本部 精神保健福祉センター 自殺総合対策
長崎県 長崎こども・女性・障害者支援センター 自殺対策
熊本県 健康福祉部 障がい者支援課 熊本県自殺対策情報サイト
大分県 障害福祉課 自殺予防対策
宮崎県 宮崎県精神保健福祉センター センターホームページ
鹿児島県 保健福祉部障害福祉課 自殺対策・うつ対策に関する取組
8 労災補償
不幸にも仕事によって精神障害にかかり、また、これにより自殺された場合には、労災補償制度により一定の補償がなされます。
労災補償を受けるには、病気にかかったご本人、自殺された場合にはご遺族が請求することになります。会社はその手続きを支援することが望まれます。
1 労災補償の内容等
給付を受けることができる場合 給付の種類 給付の内容
医療機関で療養を受けるとき。 療養補償給付 無料で療養又は全額給付
傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 休業補償給付 休業1〜3日の間は事業主の支払い
休業4日目以降給付基礎日額の60%給付。別に特別支給金
療養開始後1年6ヶ月たっても傷病が治ゆしないで障害の程度が傷病等級に該当するとき。 傷病補償年金 傷病等級 第1級:給付基礎日額の313日分の年金
傷病等級 第2級:給付基礎日額の277日分の年金
傷病等級 第3級:給付基礎日額の245日分の年金
傷病が治ゆして障害等級に該当する身体障害が残ったとき。 障害補償給付 障害等級 第1級〜第 7級:障害補償年金
(給付基礎日額の313日分〜131日分)
障害等級 第8級〜第14級:障害補償一時金
(給付基礎日額の503日分〜56日分)
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の一定の障害により現に介護を受けているとき。 介護補償給付 常時介護:支出額(上限104,960円/月。下限56,930円/月)
随時介護:支出額(上限52,480円/月。下限28,470円/月)
労働者が死亡したとき。 遺族補償給付 遺族補償年金:給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻は175日分。遺族1人)〜245日分(遺族4人以上)
遺族補償一時金(年金受給資格者がない場合等):給付基礎日額の1,000日分など
葬祭料 315,000円+給付基礎日額の30日分(この合計額が給付基礎日額の60日分に満たないときは給付基礎日額の60日分)
2 労災認定
労災補償を受けるためには、所轄の労働基準監督署にご本人又はご遺族が請求しますが、その後、その労働基準監督署が仕事との因果関係などを検討するため、種々の調査を行います。事業場関係者、医療機関関係者、ご家族、ご本人などはこの調査に協力することが必要です。
調査の結果に基づいて、専門家の意見を聴くなどにより、次の基準によって、仕事との因果関係などを検討します。
(1) 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について(平成11年9月14日付け基発第544号)
(2) 精神障害による自殺の取扱いについて(平成11年9月14日付け 基発第545号)
なお、(1)に関連する通知があります。
(3)これらの基準を満たす事例は、次の業務上疾病に該当するものと認定され、必要な保険給付がなされます。
「9.人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」(労働基準法施行規則別表第1の2第9号)










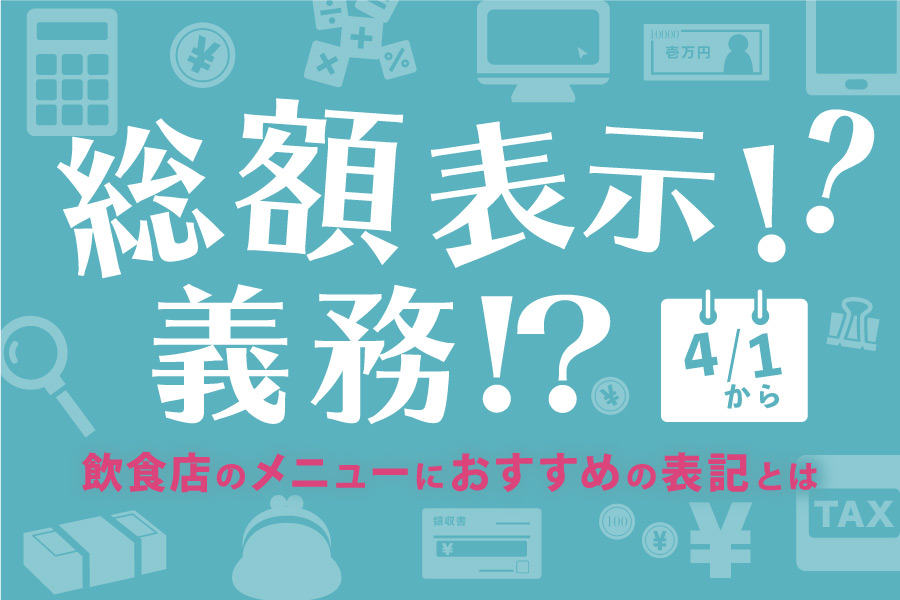
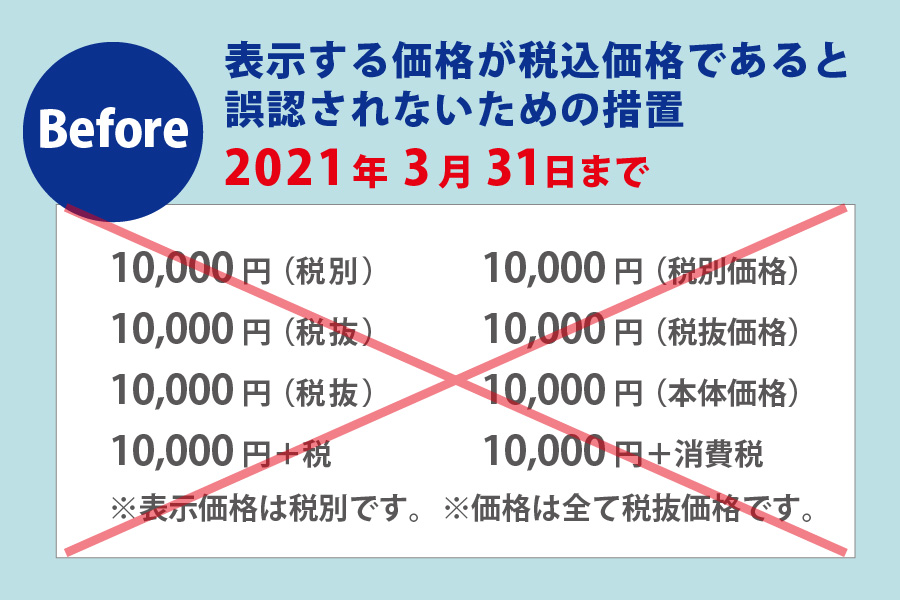 ※令和
※令和