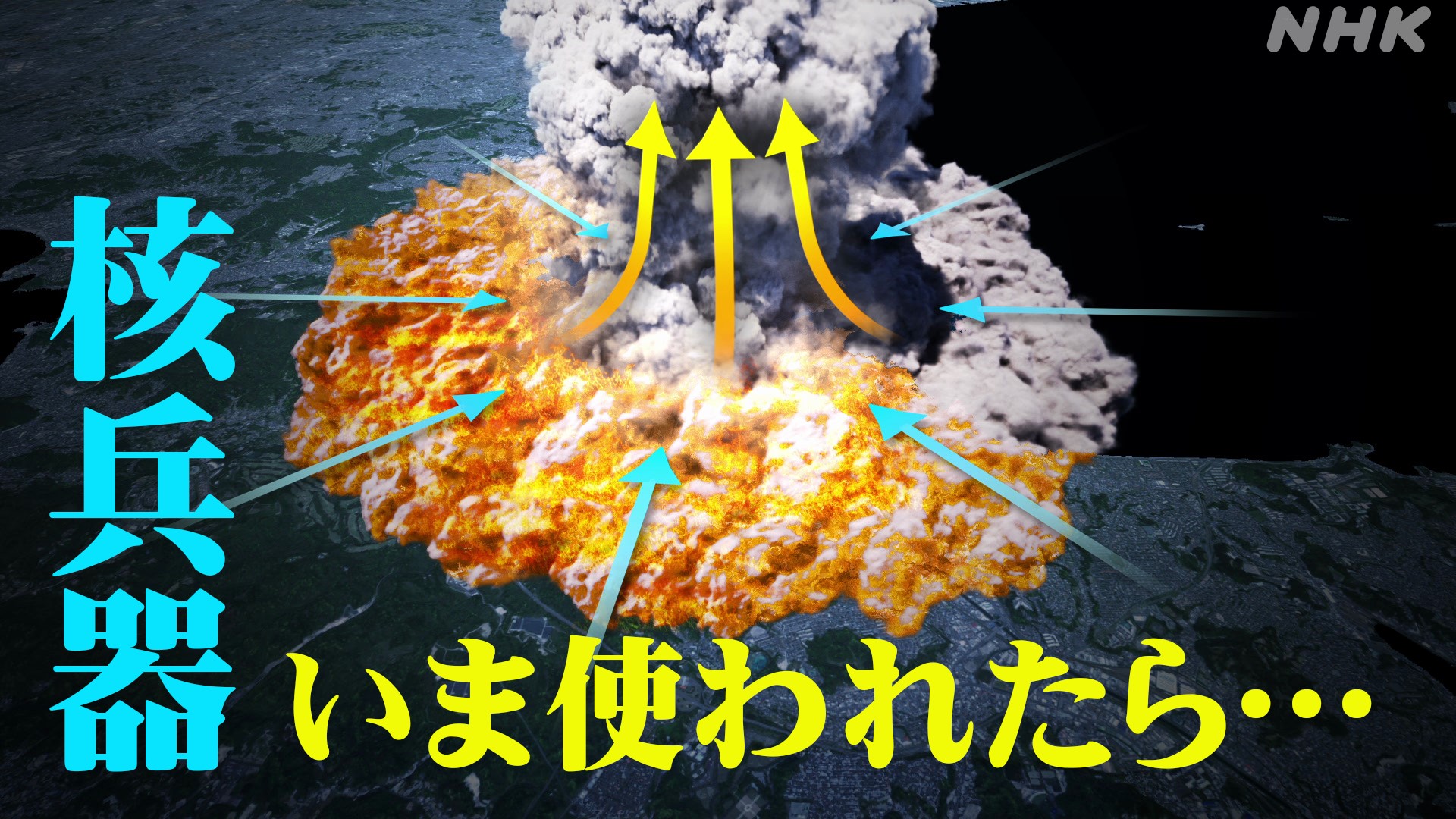子育ての目的は「子どもが自分自身で成長できるのうになること」だ思います。
子どもが自分を奮い立たせ、困難にぼつかっても乗り越え、自分で自分を成長させることです。
それが、その子の幸福につながります。
ただし、何に幸福を感じるかは、子ども自身にしかわからないものです。
親が子どもに、幸福自体を与えることはできないと思います。
けれども、幸福を得るためのスキルを育てることはできます。
何かをやりたいと思う心、そして困難に立ち向かう心を育てることはできます。
子どもが、自分でやりたいことを見つけ、その道で試行錯誤を繰り返し、人間的に成長していく―そうした本当の意味での自己実現が、最終的には重要になるのではないかと思います。
やりたいこと成し遂げるために、さまざまな能力が必要です。
読み書きや知能などの「認知能力」と、人間力や生きる力にもつながる「非認知能力」、それらの前提になる「健康・体力」が相互に関連します。
今、世界は激変し、将来の予測がつかない<不確実な時代>になっています。
こうした時代において、子ども幸福のために必要な力を考えことが、本来の意味で<子どものためになる>子育てにつながるはずです。
子ども自身が安全を感じられる、自分にとっての「安全基地」を持っている感覚が、アタッチメント。
主に「愛着」と訳され、子どもの心の状態を指す言葉です。
それは、自分の全存在を肯定してくれる、帰るべき「母港」であり、よって立つ「大地」があるといういうことです。
例えば、赤ちゃんが泣いたら、親がそれに応えミルクをあげる。
こうしたやりとりを重ねて、アタッチメント「愛着」が形成されます。
アタッチメントができると、探索行動つまり「遊び」が始まり、子どもは自分でやりたいことに向けて動き出せるようになります。
アタッチメントは、ストレスに強い性質や多少のリスクを取って行動できる能力につながるのです。
さらにアタッチメント形成によって、子どもは人を信頼できるようになります。
ケアを求めたら、相手が応答してくれたという経験を重ねると、他者の行動が予測できるようになるからです。
さらに養育者から肯定されることで、自分自身を信じることができるようになります。
甘えなどの子どもの求めに対し、親などが必要なケアを行う、こうしたやりとりをテニスに例えて、「サーブ・アンド・リターン」とも呼びます。
けれど、全ての要求に気付き、完璧なリターンすることは不可能です。
実際には、親として正解が分からないながらも、泣いている子どもの様子を観察して、いろいろ試してみるしかありません。
逆説ですが、甘えさせることで、甘えなくなって自立できるのです。
ただし、適切な甘えと「過保護」は違います。
「ケアされたい」という求めがある時は、甘えさせることが必要です。
根本的な人間力
アタッチメント「愛着」という土台の上に、どのような力を育むのか?
一つは、衝動性を抑える「セルフコントロール」です。
これは単に<我慢する力>ではなく、<自らを使いこなす力>のことで、特に他者との関係性において必要になります。
自分の思いや行動をコントロールすることが求められているのです。
二つ目は「モチベーション」です。
自分の内側から駆動させ、引っ張っていく動機付けは、生きていく上でのエンジンのようなものです。
さらに、多様性が増すこれからの時代において、自分とは異なる人を理解して思いやる「共感力」も求められます。
大切なのは、自分に関わる<具体的な人>を思いやることだとおもいます。
最後に、困難や逆境を乗り越える「レジリエント」です。
これは外からの圧力であるストレスに対し、元に戻ろうとする復元力のことです。
ゴムのようにストレスを受け止めて変形しつつ元に戻る、<しなやかな>対処がレジリエンスです。
そのレジリエンスを育むには、1)思いやりを持つ、2)あいさつをする、3)野菜から食べる、4)歯磨きをする、5)模範となる人をい持つ、6)家庭と学校以外の<第三の場所>があることなどが効果的です。
特に、あいさつは「他者をきちんと認識する」ことであり、「ちょっと勇気を要する」ことであるため、レジリエンスにつながる。
子育てはバランスが大切です。
全てに口を出す「過干渉」は良くないですが、反対に「放置」も問題です。
偏りのないバランスを支えるのは、子どもに対する「心からの信頼」ではないでしょうか。
意識的に子どもとコミュニケーションを取ることから、全てが始まります。
それが、子どもを一人の人格として尊重すること、心から信じること、肯定することにつながると感じます。
東京医科歯科大学 藤原武男教授