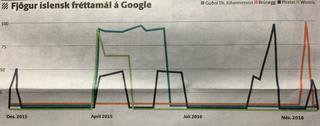まずは Merry Christmas! ですね。こちらではGledileg jol!です。きちんと発音するとグレージィレーグ·ヨウルとなるのですが、そう言うのは初心者?で、「グレリヨル」とくずれた発音が普通の挨拶となっています。
クリスマスは、もちろんキリストの誕生を祝う祭りで本来的に宗教的な意味を持っています。もっともその時代から祝われていた冬至の祭りにも関連してこの日が選ばれたようですから、その意味では文化的な要素も始まりから含まれていたとも言えます。
現代ではクリスマスは宗教的な意味を離れた文化的な祭りとしても浸透しています。別に悪い意味ではなくて日本のクリスマスなどはその典型的なものと思います。(もちろん日本のキリスト教徒の人のクリスマスはそれには当てはまりませんが)
アイスランドではクリスマスは宗教的な意味を失ってはいませんが、それなりに文化としても発展してきました。ここではクリスマスは家族が一堂に会する祭りなのですが、そこからごちそうを食べる、プレゼントを交換する、家をきれいに掃除し飾り付けをする、等々のしきたりが定着してきました。
その一方で、アイスランドの社会の中に「ヨウラ·クヴィージィ」というものにかかる人が一定の割合で出現してきてしまいました。これはクリスマス·ブルーとも言うべきもので、要するにクリスマスの故に気分が悪くなる、心配になる、落ち込む、というような現象です。
これについては以前にも書いたことがあると記憶していますが、その時は「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」というストレスからこのヨウラ·クヴィージィが生まれてきた、と説明したのではないかと思います。
それは別に間違いではないのですが、どうやらヨウラ·クヴィージィは直接そういうストレスからくるものだけではなく、単に「クリスマスに近着いた」というだけで不安や気分の低下をもたらすもののようです。
これ、単なる思い過ごしというようなものではなく、深刻なウツや不安に駆られて、病院に行かなければならなくなってしまうような人がかなりいるのです。
また、ヨウラ·クヴィージィとまではいかなくとも、家族の団欒を持てない環境にある人が、「普段よりも孤独感を感じる」と話すことはしばしばあります。実は家族のない移民の人たちにはかなり共通する感情なのです。

ヒャットラ教会
今年のクリスマスというか −アドヴェントからなのですが− に限って言うと、私自身も世間的な感覚での「クリスマスムード」はまったく持てないでいました。
私は「Seekers 難民の人たちとの祈りの集い」というグループを牧師としてお世話してきています。全員が毎週集まれるわけではなく、各回十人から十五人くらいが集まる小さな会です。
もう一年半以上やっていますので、名簿上は七十人以上の数になります。そのうち三分の一はすでに強制送還されています。送還されてはいても、私たちはいまだにメンバーとして覚え、祈ります。
さらに他の三分の一くらいは在留許可を得ることができて働いています。残りの三分の一くらいが、現在難民申請中でその結果を待っている最中なわけです。
そして先の十一月中旬あたりから、この申請中の人たちが次々と「最終的拒否」の回答を与えられてしまったのです。現時点でSeekersの中の九人が送還を待っています。
私としては、実際的な支援も含めて関わってきていますので、もちろん最後の最後まで法にかなう仕方でサポートは続けます。しかし、正直言ってこれはかなり精神的にしんどいプロセスです。
会の参加者は「クライアント」ではなく、家族のような存在です。人間として結びつきができている人が送還されるというのは、それなりにこちらの心も削られる思いなのです。
中のひとり、とりわけ教会での活動に積極的な青年が一週間前の月曜に強制送還されることになってしまい、「なんとか救済を」ということで相当な労力を費やすこととなりました。
ありがたいことに教会のビショップも相当頑張って内務省と交渉してくれましたし、一緒に大統領とも会談しました。
さて、このレベルになると私のような一介の町の牧師には見えてこない部分があり、送還直前の日曜の晩になって青年の送還は「とりあえず延期」となったのです。歓迎すべきドタキャンでした。
で、ようやくこの一週間ですよ、私自身が多少ホッとしてクリスマスのプレゼントとかを考えられるようになったのは。カーステもようやくクリスマスの曲に変えました。
今年のアドヴェントはずっとそんな感じのしんどい日々でした。ですが、逆に -というかだからこそなのですが- アドヴェントの間じゅう、クリスマスの根底にある意味、キリストの誕生を待ち望みそれを祝う、ということにしがみつくことができました。
「これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高い所からあけぼのの光が我らを訪れ、 暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く」(ルカ福音書1:78-79)

教会の子供たちの聖劇でのBaby Jesus
「クリスマスはパーティーを楽しめる人たちだけのものではない。それは第一に『暗きに座す者を照らす光』でることを心に留め、待ち望み、感謝しよう」と、手を替え品を替え?何度も何度もこのことを祈りの会で繰り返しました。
でも、そのことはSeekersの難民申請者の人たちだけに限られるものではありません。アイスランドで ヨウラ·クヴィージィに悩む人もそこには入りますし、日本や、あるいは世界のどこかで深刻な悩みの中にある人たちについても当てはまることです。
大層な話しと思われるでしょうが、神は偉大なのです。昨今「神は偉大なり」が、自爆テロのスローガンのようなイメージを与えてしまっていることには本当に辟易させられます。
神の偉大さは、そのような絶叫や暴力によって現せられるものではありません。神の偉大さは、厩の飼い葉桶の中で眠る、小さな赤ちゃんに現れているのです。それは静かで柔和なものです。柔和な愛の恵みなのです。
クリスマスのキャロルも素敵ですが、静けさの中に神の恵みを聴こうとしてみるのはどうでしょうか?決して損にはならないと思いますよ。
Gledileg jol!
応援します、若い力。Meet Iceland
藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com
Home Page: www.toma.is
クリスマスは、もちろんキリストの誕生を祝う祭りで本来的に宗教的な意味を持っています。もっともその時代から祝われていた冬至の祭りにも関連してこの日が選ばれたようですから、その意味では文化的な要素も始まりから含まれていたとも言えます。
現代ではクリスマスは宗教的な意味を離れた文化的な祭りとしても浸透しています。別に悪い意味ではなくて日本のクリスマスなどはその典型的なものと思います。(もちろん日本のキリスト教徒の人のクリスマスはそれには当てはまりませんが)
アイスランドではクリスマスは宗教的な意味を失ってはいませんが、それなりに文化としても発展してきました。ここではクリスマスは家族が一堂に会する祭りなのですが、そこからごちそうを食べる、プレゼントを交換する、家をきれいに掃除し飾り付けをする、等々のしきたりが定着してきました。
その一方で、アイスランドの社会の中に「ヨウラ·クヴィージィ」というものにかかる人が一定の割合で出現してきてしまいました。これはクリスマス·ブルーとも言うべきもので、要するにクリスマスの故に気分が悪くなる、心配になる、落ち込む、というような現象です。
これについては以前にも書いたことがあると記憶していますが、その時は「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」というストレスからこのヨウラ·クヴィージィが生まれてきた、と説明したのではないかと思います。
それは別に間違いではないのですが、どうやらヨウラ·クヴィージィは直接そういうストレスからくるものだけではなく、単に「クリスマスに近着いた」というだけで不安や気分の低下をもたらすもののようです。
これ、単なる思い過ごしというようなものではなく、深刻なウツや不安に駆られて、病院に行かなければならなくなってしまうような人がかなりいるのです。
また、ヨウラ·クヴィージィとまではいかなくとも、家族の団欒を持てない環境にある人が、「普段よりも孤独感を感じる」と話すことはしばしばあります。実は家族のない移民の人たちにはかなり共通する感情なのです。

ヒャットラ教会
今年のクリスマスというか −アドヴェントからなのですが− に限って言うと、私自身も世間的な感覚での「クリスマスムード」はまったく持てないでいました。
私は「Seekers 難民の人たちとの祈りの集い」というグループを牧師としてお世話してきています。全員が毎週集まれるわけではなく、各回十人から十五人くらいが集まる小さな会です。
もう一年半以上やっていますので、名簿上は七十人以上の数になります。そのうち三分の一はすでに強制送還されています。送還されてはいても、私たちはいまだにメンバーとして覚え、祈ります。
さらに他の三分の一くらいは在留許可を得ることができて働いています。残りの三分の一くらいが、現在難民申請中でその結果を待っている最中なわけです。
そして先の十一月中旬あたりから、この申請中の人たちが次々と「最終的拒否」の回答を与えられてしまったのです。現時点でSeekersの中の九人が送還を待っています。
私としては、実際的な支援も含めて関わってきていますので、もちろん最後の最後まで法にかなう仕方でサポートは続けます。しかし、正直言ってこれはかなり精神的にしんどいプロセスです。
会の参加者は「クライアント」ではなく、家族のような存在です。人間として結びつきができている人が送還されるというのは、それなりにこちらの心も削られる思いなのです。
中のひとり、とりわけ教会での活動に積極的な青年が一週間前の月曜に強制送還されることになってしまい、「なんとか救済を」ということで相当な労力を費やすこととなりました。
ありがたいことに教会のビショップも相当頑張って内務省と交渉してくれましたし、一緒に大統領とも会談しました。
さて、このレベルになると私のような一介の町の牧師には見えてこない部分があり、送還直前の日曜の晩になって青年の送還は「とりあえず延期」となったのです。歓迎すべきドタキャンでした。
で、ようやくこの一週間ですよ、私自身が多少ホッとしてクリスマスのプレゼントとかを考えられるようになったのは。カーステもようやくクリスマスの曲に変えました。
今年のアドヴェントはずっとそんな感じのしんどい日々でした。ですが、逆に -というかだからこそなのですが- アドヴェントの間じゅう、クリスマスの根底にある意味、キリストの誕生を待ち望みそれを祝う、ということにしがみつくことができました。
「これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって、高い所からあけぼのの光が我らを訪れ、 暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く」(ルカ福音書1:78-79)

教会の子供たちの聖劇でのBaby Jesus
「クリスマスはパーティーを楽しめる人たちだけのものではない。それは第一に『暗きに座す者を照らす光』でることを心に留め、待ち望み、感謝しよう」と、手を替え品を替え?何度も何度もこのことを祈りの会で繰り返しました。
でも、そのことはSeekersの難民申請者の人たちだけに限られるものではありません。アイスランドで ヨウラ·クヴィージィに悩む人もそこには入りますし、日本や、あるいは世界のどこかで深刻な悩みの中にある人たちについても当てはまることです。
大層な話しと思われるでしょうが、神は偉大なのです。昨今「神は偉大なり」が、自爆テロのスローガンのようなイメージを与えてしまっていることには本当に辟易させられます。
神の偉大さは、そのような絶叫や暴力によって現せられるものではありません。神の偉大さは、厩の飼い葉桶の中で眠る、小さな赤ちゃんに現れているのです。それは静かで柔和なものです。柔和な愛の恵みなのです。
クリスマスのキャロルも素敵ですが、静けさの中に神の恵みを聴こうとしてみるのはどうでしょうか?決して損にはならないと思いますよ。
Gledileg jol!
応援します、若い力。Meet Iceland
藤間/Tomaへのコンタクトは:nishimachihitori @gmail.com
Home Page: www.toma.is