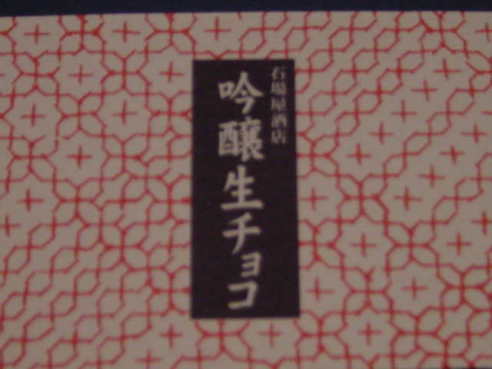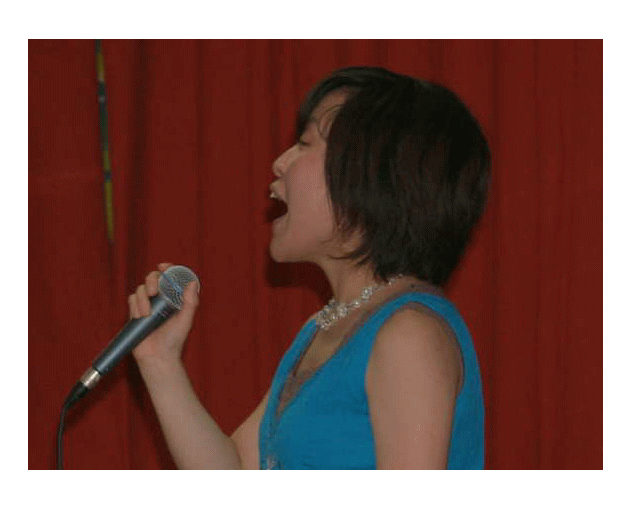チベット語になった『坊っちゃん』の感想を
トラックバックしたら
著者の方にコメントしていただき、
また、今日は本の中に登場するチベット人の学生さんから
著者のブログに、
日本に留学しているという書き込みがあり、
現在進行形で話が進んでいます。
わくわくする話です。
本の中に繰り広げられる光景は、
明治維新前後の日本のように、
新しい概念があれば、言葉を作ったりと、
作り出す楽しみがあふれています。
こう考えてくると、
今の日本にこれだけの熱気をもって
授業を受けている学生がどれだけいるかなども、
気になります。
辞書をひくことは、
日本語なら、「あかさたなはまやらわ」
それに「あいうえお」の組み合わせで、
言葉の出てくる順番を覚えて、
一文字、一文字探していくという作業ですが、
その、言葉の作りも似ているそうで、
そんなことも、翻訳作業がうまくいった一因ともいえるようです。
言葉の持つ力、文化を継承するための力、
いろいろと考えさせられる場面がでてきます。
一昨日だったか、拉致問題の横田めぐみさんのお母さんが
アメリカ議会の公聴会で、訴えたことばは、
聴く者の心に響く言葉でした。
今まで訴えつづけることによって、
伝えたいことを如何に表現したらいいか、
練られた言葉と感じました。
最近の犯罪の要因の1つに、
気持ちを言葉で表現する力を持たないために
直接行動に移ってしまうことがいわれていますが、
言葉の大切さを再確認させる本でもありました。

ことば、言葉、コトバ! クリック!
写真は、アガパンサスらしい。
誰も植えた覚えがないのに、一本だけ花がついた。
球根のものなのに、不思議です。
トラックバックしたら
著者の方にコメントしていただき、
また、今日は本の中に登場するチベット人の学生さんから
著者のブログに、
日本に留学しているという書き込みがあり、
現在進行形で話が進んでいます。
わくわくする話です。
本の中に繰り広げられる光景は、
明治維新前後の日本のように、
新しい概念があれば、言葉を作ったりと、
作り出す楽しみがあふれています。
こう考えてくると、
今の日本にこれだけの熱気をもって
授業を受けている学生がどれだけいるかなども、
気になります。
辞書をひくことは、
日本語なら、「あかさたなはまやらわ」
それに「あいうえお」の組み合わせで、
言葉の出てくる順番を覚えて、
一文字、一文字探していくという作業ですが、
その、言葉の作りも似ているそうで、
そんなことも、翻訳作業がうまくいった一因ともいえるようです。
言葉の持つ力、文化を継承するための力、
いろいろと考えさせられる場面がでてきます。
一昨日だったか、拉致問題の横田めぐみさんのお母さんが
アメリカ議会の公聴会で、訴えたことばは、
聴く者の心に響く言葉でした。
今まで訴えつづけることによって、
伝えたいことを如何に表現したらいいか、
練られた言葉と感じました。
最近の犯罪の要因の1つに、
気持ちを言葉で表現する力を持たないために
直接行動に移ってしまうことがいわれていますが、
言葉の大切さを再確認させる本でもありました。

ことば、言葉、コトバ! クリック!
写真は、アガパンサスらしい。
誰も植えた覚えがないのに、一本だけ花がついた。
球根のものなのに、不思議です。