2点の徳利の繕いの続きです。
弁柄漆に金の丸粉(3号)を蒔いて、湿気のある容器の中で2、3日かけて漆をしっかりと乾燥させます。
その後、生漆をテレビンでうんと薄めたもので粉固めの処理です。
消し粉などでは、この処理は必要ありません。
この操作を3回繰り返して。
 次の繕いの依頼
10ヶ月前
次の繕いの依頼
10ヶ月前
 次の繕いの依頼
10ヶ月前
次の繕いの依頼
10ヶ月前
 次の繕いの依頼
10ヶ月前
次の繕いの依頼
10ヶ月前
 次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
 次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
 次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
次の繕いの依頼 その3
10ヶ月前
 次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
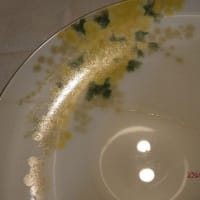 次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
 次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
 次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
次の繕いの依頼 その2
11ヶ月前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます