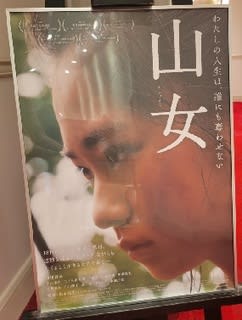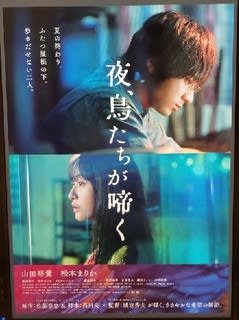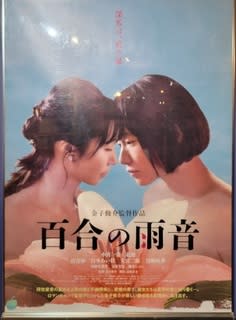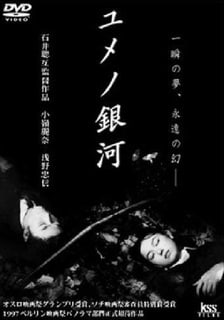(英題:FOR A FEW DOLLARS MORE)1965年作品。日本とアメリカでは1967年に公開された、言わずと知れたマカロニ・ウエスタンの代表作とされているものだ。今回4Kデジタルリマスター版が公開されたので鑑賞してみた。なお、私は有名なテーマ曲こそ知ってはいたが、本編をスクリーン上で観るのは初めてである。
札付きの悪党であるエル・インディオに1万ドルの賞金が賭けられたことを知った賞金稼ぎのダグラス・モーティマー大佐は、早速行動を起こす。同様に2千ドルの賞金首を仕留めたばかりの賞金稼ぎのモンコ(名無しの男)も、インディオ一味を狙っていた。モーティマーはモンコに、共闘して一味の賞金を山分けすることを提案する。承知したモンコは、顔馴染みの悪党グロッギーと共にエルパソ銀行を襲撃しようと企んでいたインディオの一党に潜入。外部で陽動作戦に当たるモーティマーと協力して、ターゲットを一網打尽にしようとする。
一応、主演はモンコに扮するクリント・イーストウッドということになっているが、圧倒的に目立っていたのはモーティマーを演じるリー・ヴァン・クリーフだ。黒装束に身を包み、振る舞いやセリフ回しも実に洗練されている。もちろん、ガンマンとしての腕も華麗に見せる。さらに言えば、インディオ役のジャン・マリア・ヴォロンテも儲け役だ。まさに非の打ち所の無い(?)悪党ぶりで、ラスボスとしての風格は大したものだ。それに引き換え、イーストウッドは垢抜けない小物としての存在感しか与えられておらず、あまり印象に残らない。
なお、脚本は大して上等とは言えない。特に敵役側に捕らえられた2人が、なぜか逃がしてもらうという展開は納得出来ない。シナリオ作りにも参加したセルジオ・レオーネの演出はこの頃はピリッとしない。新奇さを出そうとした挙げ句に話が冗長になり、132分というこの手のシャシンにしては長すぎる尺になってしまった。余計なモチーフは削って1時間半ぐらいに収めるべきではなかったか。
とはいえ、エンニオ・モリコーネのお馴染みの音楽が流れて荒野に銃声が響き渡ると、それらしい雰囲気にドップリと浸ることが出来る。ロケ地はスペインのアルメリア地方だが、アウトロー達が跳梁跋扈していたアメリカ西部の佇まいを再現していたと思う。なお、劇中に登場するエル・パソの町並みは本作のために沙漠の中に作り上げられたセットである。このセットは現存し観光名所になっているとか。マカロニ・ウエスタンが当時の映画界に与えた影響が垣間見える話だ。