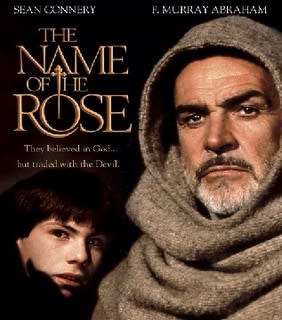(原題:DOWN BY LAW )86年作品。ジム・ジャームッシュ監督の第三作である。同監督は何といっても「ストレンジャー・ザン・パラダイス」(84年)で大ブレイクしたことを思い出す映画ファンも多いと思うが、いつまでもあのストイックなタッチを堅持するわけにはいかず、本作では早くも変化の兆しが見える。その意味では興味深いし、内容も楽しめるものになっている。
ニューオーリンズに住む無気力なラジオのDJは、あまりのだらしなさに恋人に逃げられる始末で、人生のどん底にいた。そんな彼に馴染みのワルが上手い話を持ちかけるが、うっかりそれに乗ったDJは犯罪に巻き込まれて逮捕されてしまう。一方、夢想家のポン引きはライバルの甘言に乗って女の品定めに出かけたところ、くだんの女は未成年者で、それが元でパクられる。かくして刑務所で同室になった2人だが、そこに英語もロクにしゃべれないイタリア野郎が放り込まれて、奇妙なトリオが結成される。意気投合した3人は脱獄し、南部のジャングルの中をさまよう。
このトリオは仲が良いが、妙に沈んで達観したような空気が流れるのが面白い。DJもポン引き、ともに理不尽な状況で逮捕されたことをあまり悔やんでいないし、塀の中だろうと外だろうと、自分たちの不自由さは変わりがないことを知っている。沼地を越えて3人がたどり着いた小屋が、刑務所の内装とそっくりであることがそれを象徴している。
これらはまさしく「ストレンジャー・ザン・パラダイス」の劇中に漂っていた沈んだ空気と共通するものであるが、主人公たちを演じているのがトム・ウェイツとジョン・ルーリーであることが前作と雰囲気を異にしている。言うまでもなくこの2人はミュージシャンで、彼らがメロウなブルースを歌う際の、その絶妙のアンサンブルが楽しく感心してしまう。
加えて、イタリアの著名なコメディアンであるロベルト・ベニーニが割って入るのだが、そのコラボレーションの妙に、優れた喜劇映画を見るようなエンタテインメント性が垣間見える。ニューオーリンズという舞台は、黒人文化に興味を持つ同監督に相応しく、ウェイツとルーリーの起用といい、改めてこの監督の音楽のセンスの良さには唸ってしまう。
ロビー・ミュラーのカメラによるモノクロ映像が素晴らしく、地の果てのような南部の風景が登場人物たちの漂白ぶりをうまく表現している。エレン・バーキンにニコレッタ・ブラスキ、ビリー・ニール、ロケッツ・レッドグレアなど、脇の面子も良い。