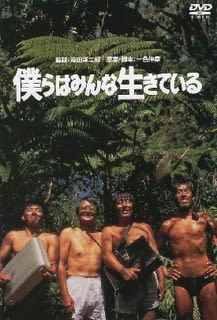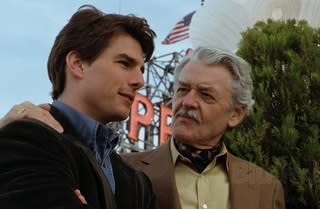(原題:DANGAL)正統派のスポ根映画。あまりにストレートで捻りがほとんど無いのは欠点にも思われるが、これがインド映画というフィルターを通すと、違和感を覚えずに楽しめる。しかも、彼の地における社会的因習に対するプロテストも適度に取り入れられ、鑑賞後の満足度は高い。インド映画史上、興収1位になったのも頷ける出来映えだ。
マハヴィルはレスリングの国内チャンピオン。80年代末に現役を引退した彼は、今度は世界王者になる夢を自分の子供に託そうとする。ところが、生まれてきたのは4人とも女の子ばかり。落ち込むマハヴィルだったが、ケンカで男の子をボコボコにした長女と次女を見て、娘たちを女子レスリングの選手として国際大会に出場させることを思い付く。
指導方法は徹底したスパルタ式で、娘たちは幾度となく反発や“逃走”を試みるが、そのたびに父親に押し切られる。月日は経ち、長女のギータと次女のバビータは遠方にある体育大学に進むが、現代的な指導をおこなう大学側と、昔ながらの父親の教えとの間で彼女たちは揺れ動く。やがてギータはいくつかの国際大会に出るが、結果が出ない。見かねたマハヴィルは一計を案じて勝手に試合会場のバックヤードに乗り込み、娘を指導する。実話の映画化だ。
前半は少女たちの成長物語のスタイルを取るが、見逃せないのは今も残る彼の地の封建的な空気がクローズアップされていることだ。女の子はスポーツどころか学校にもロクに行かせてもらえず、ちょっと大きくなると直ちに縁談が周囲からセッティングされ、一回も会ったことが無い男の元に嫁がねばならない。本作の上映後も関係者は宗教団体から“リベラルに過ぎる”と批判を受けたらしい。しかし、ドラマツルギーとしては“障害が多いほど盛り上がる”というのは自明の理であり、本作も序盤から終盤までヴォルテージは右肩上がりである。
レスリングの場面は素晴らしい。カメラが選手に寄っているので、プレーヤーの俊敏な動きや技の掛け合いが鮮明に映し出され、観ていて引き込まれる。選手を演じる役者たちの身体能力はあきれるほど高く、特にギータに扮するファーティマー・サナー・シャイクは美しさと力強さを兼ね備えた逸材で、出てくるだけでワクワクした。
マハヴィル役のアーミル・カーンはさすがの貫禄。今回は役作りのために27キロ太って撮影後に27キロ戻すという、かつてのロバート・デ・ニーロを思わせる離れ業もやってのけ、それだけに画面全体から気合いが感じられるようだ。ニテーシュ・ティワーリーの演出もソツがない。
それにしても、映画のクライマックスがオリンピックでもアジア大会でもなく、コモンウェルスゲームズと呼ばれる英連邦競技大会だというのは興味深い(恥ずかしながら、この大会の存在を今回初めて知った)。4年に1回開かれるらしく、イギリス連邦に属する国の住民にとっては特別な意味があるのだろう。