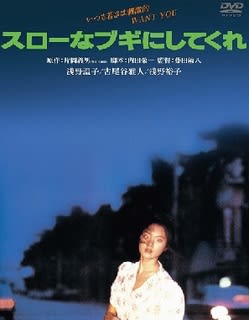(原題:THE FAREWELL)まあまあ面白かった。興味深いネタは扱っているが、それほど突っ込んだアプローチは成されていない。観ている者が重苦しい気持ちにならないように、ほどほどのレベルに留めている。だから出来の方も“ほどほど”なのだが、語り口は悪くないので最後までスンナリとスクリーンと対峙していられた。
ニューヨークに暮らす中国系アメリカ人女性のビリーと家族は、中国に住む祖母がガンで余命幾ばくも無いという知らせを受け、急遽故郷の吉林省の長春に向かう。ただし本人には病気のことは一切知らせておらず、親戚一同が集まるのはビリーの従兄弟の結婚式という名目だ。ビリーは祖母にはちゃんと告知すべきだと訴えるが、本国の親族は本人がショックを受けて悲しむとの理由で反対する。彼女はモヤモヤとした気分のまま、結婚式当日を迎えるのだった。
幼いときに中国を離れてアメリカに移住したビリーには、欧米流の合理主義が身に付いている。だから、祖母に真実を伝えない親族の様子に戸惑うばかりだ。しかし彼女は、周囲から東洋と西洋との死生観の違いを教えられる。西欧では、命は個々人のものだ。だから、運命を受け入れてどう対応するかは自分自身の問題である。一方東洋では、命は家族ひいては社会の一部と認識される。コミュニティの一部である生命を担っている者を無駄に悲しませることは、タブーなのだ。この指摘には興味を引かれる。
とはいえ、海外で生活する中国人も増えた昨今、中国社会にもビリーのような考え方を持つ者がいることも示される。さらに従兄弟はいつもは日本に住んでいて、結婚相手も日本人なのだ。グローバル化は避けようがない。また、ビリーが子供の頃に住んでいた住宅はとっくの昔に取り壊され、あたりに過去の面影は無い。ドラスティックな都市計画が罷り通る中国の現状も紹介されている。ただし、奥深い問題提示はスルーしており、そこは物足りない。
中国で生まれアメリカで育ったルル・ワン監督の仕事ぶりは、派手なケレンこそ無いがテンポ良くドラマを進めている。挿入されるギャグも効果的だ。主演のオークワフィナは演技はまずまずだと思うが、ルックス面での訴求力は乏しい(笑)。ツィ・マーやダイアナ・リン、チャオ・シュウチェンといった脇の面子の方が良い味を出している。しかしながら、ラストの“オチ”にはびっくりした。それまでの展開は一体何だったのだと思うほどの、いわば“掟破り”だ。鑑賞後はビリーに代わって、観ているこちらがモヤモヤとしてしまった(爆)。