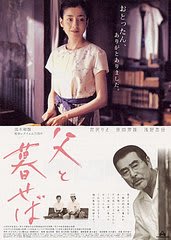(原題:Transformers)基本的にお子様向けの映画であるが、それに専念していないところに居心地の悪さがある(-_-;)。
冒頭、中東のカタールの米軍基地が突如突然二足歩行ロボットに変形した軍用ヘリコプターにより壊滅させられる場面があるが、このシークエンスはかなり怖い。なぜならこの“油断しているとやられる”という構図は現在のイラクなんかの状況(自爆テロなど)と変わらないからだ。そして、生き残った米兵がサソリ型のロボットに追われて小さな村に行き着くと、そこは反政府ゲリラの巣窟だと思われても仕方がないほど武器が満載だったというのも相当キツい。もちろん宇宙からの強大な敵を前にしてはアメリカだアラブだと言っていられる余裕はなく、共同して何とか撃退はするのだが、こういう現実を照射したようなモチーフには全編に渡るハードな展開を期待させるものがあった。
が、面白かったのはそこまでだ。気弱な男子高校生(シャイア・ラブーフ)と、学園のアイドル的存在の女学生(ミーガン・フォックス)とのラブコメに移行すると一気に映画は失速。そして彼が父親に買ってもらったポンコツ車が“善玉のトランスフォーマー”たる正体を現すシーンからは、子供だましのおちゃらけにレベルダウンしてしまう。あとはテレビのロボットアニメのごとく、組んずほぐれつのバトルが延々と続くのみ。
元はタカラの人形シリーズであり、それが低年齢層用のテレビアニメに移行したシロモノの実写映画化なので、幼稚な作りになっても仕方ないのかもしれないが、一応大人の観客も劇場に足を運ぶのだから、もうちょっと話を練り上げるべきではなかったか。
異星からの侵略に右往左往しているのがアメリカだけという不思議、ストーリーの鍵を握る“キューブ”とかいう物体の位置づけの曖昧さ、重要な小道具になっているはずの“星間座標が焼き付けられた骨董品のメガネ”についても扱いが尻切れトンボだし、何より侵略の“主要メソッド”である地球上のあらゆる機械をトランスフォームさせるという企みが中途半端に終わっているのが痛い(描きようによっては高インパクトの展開になったはず)。
肝心のロボット同士のアクション場面も“ああ、しょせんCGね”と軽くあしらわれるような芸の無さだし、第一ガチャガチャとうるさいだけで何がどうなっているのかよく分からない。少しは引きのショットを多用して情勢を具体的に示すような工夫をしろと言いたい。このあたり、マイケル・ベイ監督&スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮という、脳天気コンビの資質が全開していると言えよう(爆)。子供を連れての夏休みの家族サービスには向いているが、少しでもマジメに接するとバカを見る映画だ。