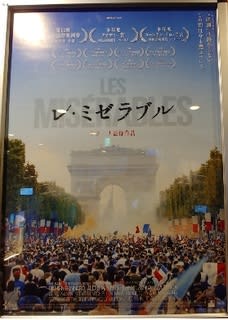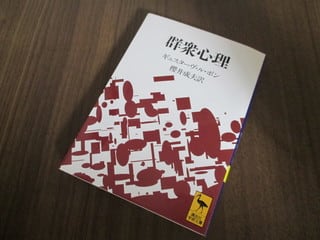(原題:OUR SOULES AT NIGHT )2017年9月よりNetflixにて配信。実に味わい深いヒューマンドラマであり、鑑賞後の満足感は大きい。また、ロバート・レッドフォードとジェーン・フォンダというスターを配していながら、どうしてネット配信の扱いで終わってしまったのか解せない。全国拡大公開は無理でも、このクォリティならばミニシアター系での粘り強い興行は可能だったと想像する。
コロラド州の田舎町に住むルイス・ウォーターズは、妻を亡くしてから一人で老後の日々を送っていた。ある日の晩、近所に住む未亡人のエディーが彼を訪ねてくる。彼女もまた夫に先立たれてから長らく一人で暮らしていた。エディーはルイスに“ときどき、うちに来て一緒に寝てくれないか”と頼むのだった。もっとも、それはあくまでプラトニックな関係で、孤独を癒すために語り合う相手が欲しかったらしい。唐突な申し出に面食らうルイスだが、結局はその提案を受け入れる。だが、周囲の者は2人が懇ろな関係になったのではないかと、いらぬ詮索をするのだった。
ある日、エディーの息子ジーンが7歳になるジェイミーを連れてくる。彼は妻に逃げられ、慣れない育児に窮しており、母親に助けを求めたのだ。エディーはジェイミーを預かることにするが、ルイスも子守を担当する。だが、エディーとルイスの関係を知ったジーンは、すぐさまジェイミーを引き取りに来るのだった。ケント・ハルフが2015年に上梓した小説の映画化だ。
主人公2人の逢瀬は、単に“独居老人同士が、たまたま近くに住んでいたので急接近してみた”という下世話なレベルの話ではない。エディーとルイスには、それぞれ拭いきれない過去への悔恨がある。そして今も家族に対する屈託を抱えている。一人きりでは押し潰されてしまうような懊悩の中で、価値観を共有する“仲間”を求めた結果なのだ。過去及び家族に今一度向き合い、何とか残りの人生を乗り切るためのモチベーションを見つけるため、2人はあらためて困難な道を歩み出す。その見事な決意表明には感服するのみである。
印象的なシークエンスはいくつもあるが、その中でもエディーとルイス、そしてジェイミーがキャンプに出掛けるくだりは素晴らしい。心を閉ざしていたジェイミーが自然の中で自分を取り戻し、祖母たちと新たな関係性を見出すシーンは、美しい映像も相まって大いに共感した。もちろん、これはレッドフォードとJ・フォンダという華のあるスターが演じているからこそ説得力があるのだが、たとえ一般の市井の者でも年を取ってから斯くの如き“転機”を迎える可能性があるのではないかと思い至り、観ていて表情が緩んでしまう。
主演の2人は言うこと無し。老いても存在感は失っていない。マティアス・スーナールツやジュディ・グリア、ブルース・ダーンといった脇のキャストも手堅い。エリオット・ゴールデンサールの音楽とスティーヴン・ゴールドブラットの撮影は見事だ。監督のリテーシュ・バトラは現時点で40歳そこそこだが、それでいて人生のベテランたちを動かす術に長けているのには感心する。演出力も「めぐり逢わせのお弁当」(2013年)の頃よりもアップしているようだ。