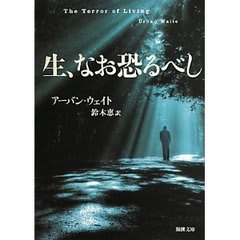(原題:Moneyball )醒めているようで実は熱く、一歩引いているように見えて実は肉迫しているという、主人公の野球に対する絶妙の距離感が強い印象を残す辛口のドラマだ。野球好きならば思わず身を乗り出し、そうじゃない者でも引きつけられる、見応えのある作品と言えよう。
本作の主人公ビリー・ビーンは、オークランド・アスレティックスのGM(ゼネラル・マネージャー)である。現役時代は何とかメジャーでプレイしていたが、大した実績も残さずに引退した。しかし彼は努力の末に球団を支える裏方として名を挙げ、選手の去就を左右するほどの権限を手にする。
彼は若い頃にスカウトの甘言に乗って実力を身につけないままにプロ入りした苦い経験があり、既存の球団フロントに対して猜疑心を抱いている。だが内実は誰よりも野球が好きで、チームを勝たせたいという熱意は人一倍だ。このアンビバレンツな興味深い人物像を取り上げた時点で、この映画の成功はある程度約束されたようなものである。
そんな一種屈折した感性の持ち主であるビーンが選んだ方法論が、セイバーメトリクスと呼ばれる統計学的なアプローチだ。監督やコーチの勘と経験を無視し、厳格に出塁率を査定して選手を起用する。自分がチームに招いた選手が試合にあまり出られないことが分かると、レギュラー選手を無理矢理トレードに出してポジションを確保させる。また、欲しい選手を手に入れるためには権謀術数を駆使し、まさに手段を選ばない。
そもそも彼がブレーンとして起用したのが、有名大学で計量経済学を専攻していたが野球の経験がないピーター・ブランド(ジョナ・ヒル)である。ビーンは数理的背景に則った徹底してドライなシステムを組み上げ、異論を許さぬ体制を作り出す。
しかし“自分が試合を見ると負ける”という、実に“非・論理的”なジンクスを信じ込んでいたり、高額のギャラを提示されたレッドソックスからのオファーを蹴ってしまうのも、他でもない彼自身なのだ。冷徹さ一辺倒にはなりきれない、血の通ったキャラクター。演じるブラッド・ピットはそんな複雑な内面を上手く表現している。ビーンと対峙する監督役のフィリップ・シーモア・ホフマンも好演だ。
ベネット・ミラーの演出はこの手の映画にありがちな典型的スポ根路線を回避し、クールな展開に終始する。これ見よがしのケレン味を抑える代わりに、テンポ良くモチーフを繰り出していく。
ビーンの奮闘によりアスレチックスは快進撃を続けるが、いまだワールドシリーズを制覇するには至っていない。ビーンのやり方は精神論が幅を利かせるスポーツの現場にはなかなか受け入れられないし、またセイバーメトリクスだけでも壁にぶち当たってしまうことは想像に難くない。でも、主人公のチャレンジはまだまだ続くのだ。彼の活躍を注視したい。