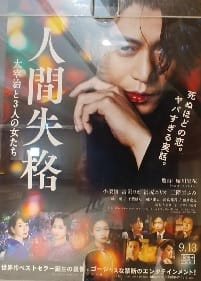企画および製作側には、クラシック音楽を理解していない者、それどころかロクに聴いたことも無い者が多数派を占めるのではないか。そう感じるほど、この映画はサマになっていない。もとより日本映画は音楽を題材に扱うことは不得手であり、ましてや筋書きや段取りの吟味や練り上げを怠ったまま、原作が有名であるという理由だけでゴーサインを出したと思しき状況では、良い映画が出来るはずもないのだ。
3年に一度開催される、若手の登竜門とされる国際ピアノコンクールを舞台に、トップを目指す4人の男女の挑戦と成長を描く。著名なコンクールの制覇を目指す参加者は、間違いなく天才クラスであるはずだ。本作でも映画の中では主人公達は周囲から天才と呼ばれている。しかし、いずれも劇中では一度も天才らしい輝きを見せることは無いし、天賦の才能を授かったからこそ陥る苦悩や屈託を示すことも無い。単に、普通の俳優がピアノが弾けるキャラクターを演じたというレベルに留まっている。

加えて、演奏シーンの酷さは目を覆うばかりだ。どの演者も、音楽に没入していない。つまりは全然スイングしていないのだ。本番では俳優が直接鍵盤を叩く場面も見当たらず、それどころか、音源と身体の動きが合っていないショットも散見される。コンクールの式次第に関しても噴飯物で、審査員がコンクール中に寝ていたり、パンを頬張っていたり、挙句の果ては隣りの者と私語を交わすなど、絶対にありえない。ステージマネージャーが“今からカデンツァに入る”と関係者に連絡するなど、ナンセンスの極みだ。ピアニストがオーケストラの楽器の位置を独断で動かすというケースも、まるで考えられない。
松岡茉優に松坂桃李、森崎ウィン、鈴鹿央士といった主要キャストは、とてもピアノが弾けるようには見えない。鹿賀丈史が演じるキャラクターが世界的な指揮者とは思えないし、斉藤由貴が審査委員というのはタチの悪い冗談だし、ブルゾンちえみや片桐はいりが出てくる場面に至っては、明らかに観客をバカにしている。
デビュー作「愚行録」(2017年)で卓越した映像センスを見せた石川慶の演出は、本作ではびっくりするほど凡庸だ。テンポが冗長であるばかりではなく、得意のヴィジュアル処理も不発。特にヒロインの心象風景はイマジネーションが不足しており、J-POPのMVにも及ばない。水に濡れた黒い馬が幾度も登場するのも意味不明(ひょっとして、音楽用語“ギャロップ”の暗喩か?)。
何しろ“蜜蜂”も“遠雷”も、きちんとモチーフとして提示していない有様だ。原作は読んでいないが、かなりの長編であり、映画で不満に思えたことが詳説されているのかもしれないが、いずれにしても生半可なスタンスで映画化できるものではないことは確かである。
なお、手練れの映画ファンならば、本作はアメリカ映画「コンペティション」(80年)を意識していることを見抜くだろう。舞台設定はもちろん、ヒロインの演目がプロコフィエフの3番であることも共通している。だが、ヴォルテージは圧倒的に「コンペティション」の方が高い。これはスタッフやキャストの質以前に、音楽(特にクラシック)に対する認識が邦画と欧米作品とでは懸け離れていることが大きな要因だろう。
たとえばカーステン・シェリダン監督の「奇跡のシンフォニー」(2007年)では、本作で説明的なセリフと舌足らずの映像で何とか表現しようとしている事柄を、ファースト・ショットで全てクリアしてしまう。果たして、日本映画がこのような芸当が出来るようになるのに、今後どの程度の年月を要するのだろうか(暗然)。
3年に一度開催される、若手の登竜門とされる国際ピアノコンクールを舞台に、トップを目指す4人の男女の挑戦と成長を描く。著名なコンクールの制覇を目指す参加者は、間違いなく天才クラスであるはずだ。本作でも映画の中では主人公達は周囲から天才と呼ばれている。しかし、いずれも劇中では一度も天才らしい輝きを見せることは無いし、天賦の才能を授かったからこそ陥る苦悩や屈託を示すことも無い。単に、普通の俳優がピアノが弾けるキャラクターを演じたというレベルに留まっている。

加えて、演奏シーンの酷さは目を覆うばかりだ。どの演者も、音楽に没入していない。つまりは全然スイングしていないのだ。本番では俳優が直接鍵盤を叩く場面も見当たらず、それどころか、音源と身体の動きが合っていないショットも散見される。コンクールの式次第に関しても噴飯物で、審査員がコンクール中に寝ていたり、パンを頬張っていたり、挙句の果ては隣りの者と私語を交わすなど、絶対にありえない。ステージマネージャーが“今からカデンツァに入る”と関係者に連絡するなど、ナンセンスの極みだ。ピアニストがオーケストラの楽器の位置を独断で動かすというケースも、まるで考えられない。
松岡茉優に松坂桃李、森崎ウィン、鈴鹿央士といった主要キャストは、とてもピアノが弾けるようには見えない。鹿賀丈史が演じるキャラクターが世界的な指揮者とは思えないし、斉藤由貴が審査委員というのはタチの悪い冗談だし、ブルゾンちえみや片桐はいりが出てくる場面に至っては、明らかに観客をバカにしている。
デビュー作「愚行録」(2017年)で卓越した映像センスを見せた石川慶の演出は、本作ではびっくりするほど凡庸だ。テンポが冗長であるばかりではなく、得意のヴィジュアル処理も不発。特にヒロインの心象風景はイマジネーションが不足しており、J-POPのMVにも及ばない。水に濡れた黒い馬が幾度も登場するのも意味不明(ひょっとして、音楽用語“ギャロップ”の暗喩か?)。
何しろ“蜜蜂”も“遠雷”も、きちんとモチーフとして提示していない有様だ。原作は読んでいないが、かなりの長編であり、映画で不満に思えたことが詳説されているのかもしれないが、いずれにしても生半可なスタンスで映画化できるものではないことは確かである。
なお、手練れの映画ファンならば、本作はアメリカ映画「コンペティション」(80年)を意識していることを見抜くだろう。舞台設定はもちろん、ヒロインの演目がプロコフィエフの3番であることも共通している。だが、ヴォルテージは圧倒的に「コンペティション」の方が高い。これはスタッフやキャストの質以前に、音楽(特にクラシック)に対する認識が邦画と欧米作品とでは懸け離れていることが大きな要因だろう。
たとえばカーステン・シェリダン監督の「奇跡のシンフォニー」(2007年)では、本作で説明的なセリフと舌足らずの映像で何とか表現しようとしている事柄を、ファースト・ショットで全てクリアしてしまう。果たして、日本映画がこのような芸当が出来るようになるのに、今後どの程度の年月を要するのだろうか(暗然)。