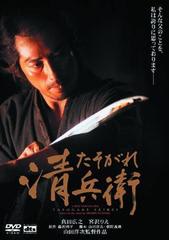2012年の個人的映画ベストテンを発表する。2012年は個人的事情により鑑賞本数が減り、全ての注目作をカバーしているとはとても言えないが、とりあえず10本は選ぶことが出来た。

日本映画の部
第一位 ヒミズ
第二位 希望の国
第三位 わが母の記
第四位 僕達急行 A列車で行こう
第五位 苦役列車
第六位 鍵泥棒のメソッド
第七位 綱引いちゃった!
第八位 任侠ヘルパー
第九位 ロボジー
第十位 しあわせのパン
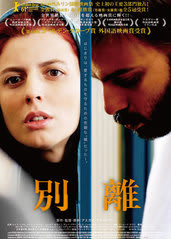
外国映画の部
第一位 別離
第二位 家族の庭
第三位 ヘルプ 心がつなぐストーリー
第四位 哀しき獣
第五位 ファミリー・ツリー
第六位 サラの鍵
第七位 少年と自転車
第八位 ゴモラ
第九位 007/スカイフォール
第十位 アベンジャーズ
邦画は東日本大震災を題材にした2本が上位を占めた。やはり、日本映画にはこのテーマを扱う義務がある。どう描いても明るい映画になるはずもないが、だからといってこのシビアな素材から逃げていては、カツドウ屋の名がすたるというものだ。
洋画の一位は2011年にアジアフォーカス福岡映画祭で観ているのだが、やはり傑作であることには間違いない。イラン映画として初の米アカデミー賞を獲得したことも含めて、要チェックの作品である。
なお、以下の通り各賞も選んでみた。まずは邦画の部。
監督・脚本:園子温(ヒミズ)
主演男優:夏八木勲(希望の国)
主演女優:二階堂ふみ(ヒミズ)
助演男優:香川照之(鍵泥棒のメソッド)
助演女優:梶原ひかり(希望の国)
音楽:田中ユウスケ(鍵泥棒のメソッド)
撮影:芦澤明子(わが母の記)
新人:三吉彩花、能年玲奈(グッモーエビアン!)
次に洋画の部。
監督:アスガー・ファルハディ(別離)
脚本:マイク・リー(家族の庭)
主演男優:ジョージ・クルーニー(ファミリー・ツリー)
主演女優:ヴィオラ・デイヴィス(ヘルプ 心がつなぐストーリー)
助演男優:クリストファー・プラマー(人生はビギナーズ)
助演女優:ジェシカ・チャステイン(ヘルプ 心がつなぐストーリー)
音楽:ジョン・ウィリアムズ(戦火の馬)
撮影:ロジャー・ディーキンス(007/スカイフォール)
新人:シャイリーン・ウッドリー(ファミリー・ツリー)
例年ならばワーストテンも選ぶところだが、正直言って今回は思い出したくもない映画を俎上にのせるのは遠慮したい(笑)。
さて、11月に北九州市で開催されたAVフェアでは140インチのスクリーンを使用したシステムがデモされていたが、これは本当に凄いと思った。3D機能搭載なのは当たり前として、(通常、ディスプレイの下にセットされたスピーカーから出る)センターの音像をヴァーチャルで画面の高さにまで持ってくるという技術には舌を巻いたものだ。ここまでくるとミニ・シアターの設備とあまり変わらない。
昨今のミニ・シアターの斜陽化と家庭用AVシステムのイノベーションとが直接リンクするわけでもないが、映画という娯楽がある意味で非・日常的体験をさせてくれるものである以上、劇場の規模が大きくモノを言うのは間違いないだろう。今後の展開を注視したい。

日本映画の部
第一位 ヒミズ
第二位 希望の国
第三位 わが母の記
第四位 僕達急行 A列車で行こう
第五位 苦役列車
第六位 鍵泥棒のメソッド
第七位 綱引いちゃった!
第八位 任侠ヘルパー
第九位 ロボジー
第十位 しあわせのパン
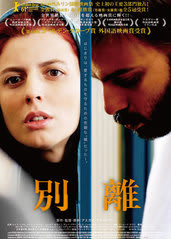
外国映画の部
第一位 別離
第二位 家族の庭
第三位 ヘルプ 心がつなぐストーリー
第四位 哀しき獣
第五位 ファミリー・ツリー
第六位 サラの鍵
第七位 少年と自転車
第八位 ゴモラ
第九位 007/スカイフォール
第十位 アベンジャーズ
邦画は東日本大震災を題材にした2本が上位を占めた。やはり、日本映画にはこのテーマを扱う義務がある。どう描いても明るい映画になるはずもないが、だからといってこのシビアな素材から逃げていては、カツドウ屋の名がすたるというものだ。
洋画の一位は2011年にアジアフォーカス福岡映画祭で観ているのだが、やはり傑作であることには間違いない。イラン映画として初の米アカデミー賞を獲得したことも含めて、要チェックの作品である。
なお、以下の通り各賞も選んでみた。まずは邦画の部。
監督・脚本:園子温(ヒミズ)
主演男優:夏八木勲(希望の国)
主演女優:二階堂ふみ(ヒミズ)
助演男優:香川照之(鍵泥棒のメソッド)
助演女優:梶原ひかり(希望の国)
音楽:田中ユウスケ(鍵泥棒のメソッド)
撮影:芦澤明子(わが母の記)
新人:三吉彩花、能年玲奈(グッモーエビアン!)
次に洋画の部。
監督:アスガー・ファルハディ(別離)
脚本:マイク・リー(家族の庭)
主演男優:ジョージ・クルーニー(ファミリー・ツリー)
主演女優:ヴィオラ・デイヴィス(ヘルプ 心がつなぐストーリー)
助演男優:クリストファー・プラマー(人生はビギナーズ)
助演女優:ジェシカ・チャステイン(ヘルプ 心がつなぐストーリー)
音楽:ジョン・ウィリアムズ(戦火の馬)
撮影:ロジャー・ディーキンス(007/スカイフォール)
新人:シャイリーン・ウッドリー(ファミリー・ツリー)
例年ならばワーストテンも選ぶところだが、正直言って今回は思い出したくもない映画を俎上にのせるのは遠慮したい(笑)。
さて、11月に北九州市で開催されたAVフェアでは140インチのスクリーンを使用したシステムがデモされていたが、これは本当に凄いと思った。3D機能搭載なのは当たり前として、(通常、ディスプレイの下にセットされたスピーカーから出る)センターの音像をヴァーチャルで画面の高さにまで持ってくるという技術には舌を巻いたものだ。ここまでくるとミニ・シアターの設備とあまり変わらない。
昨今のミニ・シアターの斜陽化と家庭用AVシステムのイノベーションとが直接リンクするわけでもないが、映画という娯楽がある意味で非・日常的体験をさせてくれるものである以上、劇場の規模が大きくモノを言うのは間違いないだろう。今後の展開を注視したい。