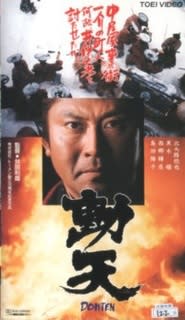(原題:ON THE MILKY ROAD )エミール・クストリッツァ監督のお馴染みの個性的な持ち味は発揮されているが、内容を勘案すると上映時間が長すぎる。しかも、中盤以降の展開は明らかに冗長だ。余計なシークエンスを削ってタイトに仕上げれば、もっと評価出来る映画になったと思われる。
舞台は東欧のどこかの国の村。戦争の真っ最中であり、村のあちこちで銃弾が飛び交っている状態だが、それでも住民の暮らしは続く。主人公の中年男コスタは、兵士たちにミルクを届けるため毎日ロバに乗って前線を渡り歩いている。ミルク売りの娘ミレナは彼を愛しているが、コスタは正直あまり乗り気では無い。折しも休戦協定が結ばれて、村はつかの間の平和を取り戻す。

ミレナの兄ジャガは戦場の英雄で、家族はもうすぐ帰ってくる彼のために結婚相手を探すことにする。花嫁に選ばれたのは、ローマからセルビア人の父を捜しに来て戦争に巻き込まれたという美女だった。だが、コスタは彼女を一目見るなりゾッコンになり、勝手にセッティングされたミレナとの結婚なんか、どうでもよくなってくる。一方、この花嫁と以前付き合っていたがフラれてしまった多国籍軍の英国将校が、彼女を連れ戻そうと特殊部隊を村に送り込み、村は再び戦火にさらされる。
やかましいバルカン・サウンドとカラフルな画面。出演者達の大仰なパフォーマンスや、それに匹敵するほどの動物たちの名演技(特にコスタが飼っている、ダンスを踊るハヤブサはケッ作だ)。いつもの“クストリッツァ節”は健在である。しかし、命からがら村を脱出したコスタと花嫁の逃避行がメインになる後半は、どうにも締まらない。

3人の兵士がコスタ達を追いかけるのだが、なぜかターゲットに近付いても3人一緒に行動している。三方に分かれて攻めるのが筋だと思うのだが、これでは“まとめて片付けてください”と言っているようなものだ。もちろん“クストリッツァ流の寓話仕立てだから問題ない”という見方も出来るのだろうが、特殊部隊の村での所業はやけにリアルだし、終盤のチェイス場面もオフビートなテイストは希薄だ。
そもそも、後半にコスタ達が展開するロードムービーは行き当たりばったりであり、“これで終わりか?”と思ったらまたダラダラと続くというパターンの繰り返し。これでは評価出来ない。
主役はクストリッツァ自身で、けっこう好演だ。ヒロイン役のモニカ・ベルッチが振りまく華やかなオーラは、いつもながら大したものだ。ペシミズムあふれる幕切れは悪くはないが、そこに至る展開がピリッとしないのであまり印象に残らず。鑑賞後の満足度はイマイチである。
舞台は東欧のどこかの国の村。戦争の真っ最中であり、村のあちこちで銃弾が飛び交っている状態だが、それでも住民の暮らしは続く。主人公の中年男コスタは、兵士たちにミルクを届けるため毎日ロバに乗って前線を渡り歩いている。ミルク売りの娘ミレナは彼を愛しているが、コスタは正直あまり乗り気では無い。折しも休戦協定が結ばれて、村はつかの間の平和を取り戻す。

ミレナの兄ジャガは戦場の英雄で、家族はもうすぐ帰ってくる彼のために結婚相手を探すことにする。花嫁に選ばれたのは、ローマからセルビア人の父を捜しに来て戦争に巻き込まれたという美女だった。だが、コスタは彼女を一目見るなりゾッコンになり、勝手にセッティングされたミレナとの結婚なんか、どうでもよくなってくる。一方、この花嫁と以前付き合っていたがフラれてしまった多国籍軍の英国将校が、彼女を連れ戻そうと特殊部隊を村に送り込み、村は再び戦火にさらされる。
やかましいバルカン・サウンドとカラフルな画面。出演者達の大仰なパフォーマンスや、それに匹敵するほどの動物たちの名演技(特にコスタが飼っている、ダンスを踊るハヤブサはケッ作だ)。いつもの“クストリッツァ節”は健在である。しかし、命からがら村を脱出したコスタと花嫁の逃避行がメインになる後半は、どうにも締まらない。

3人の兵士がコスタ達を追いかけるのだが、なぜかターゲットに近付いても3人一緒に行動している。三方に分かれて攻めるのが筋だと思うのだが、これでは“まとめて片付けてください”と言っているようなものだ。もちろん“クストリッツァ流の寓話仕立てだから問題ない”という見方も出来るのだろうが、特殊部隊の村での所業はやけにリアルだし、終盤のチェイス場面もオフビートなテイストは希薄だ。
そもそも、後半にコスタ達が展開するロードムービーは行き当たりばったりであり、“これで終わりか?”と思ったらまたダラダラと続くというパターンの繰り返し。これでは評価出来ない。
主役はクストリッツァ自身で、けっこう好演だ。ヒロイン役のモニカ・ベルッチが振りまく華やかなオーラは、いつもながら大したものだ。ペシミズムあふれる幕切れは悪くはないが、そこに至る展開がピリッとしないのであまり印象に残らず。鑑賞後の満足度はイマイチである。