91年作品。公開当時に、この映画をベタボメしている評論家が多かったのには呆れたものだ。それも内容ではなく、問題意識の面だけで評価している。これがいったい“評論”と呼べるのであろうか。別に問題意識そのものが悪いとは思わないが、とにかくこのヘタクソな映画づくりは勘弁してほしい。
東京の下町に住む高校生のゆかりは、親から戦争体験を聞きリポートにまとめるという宿題を出される。さっそく父親に話を聞こうとするが、得られたのは要領を得ない返答ばかり。そんなある日、父親の姉が飛び出した子供をかばって交通事故に遭う。背景には伯母の戦時中の体験があったようで、それをきっかけに父親は重い口を開き、ゆかりは父と伯母の戦争体験を知ることになる。
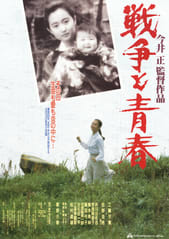
女優二人にそろって二役を演じさせていながら、それを少しもドラマとして生かしていない。そっくりの顔の女が出て来るのに、ほかの人物がその事実をまるで無視するなんて、どういうことだろう。
ヒロインの回想場面での、恋人と花畑で手をとりあって踊るシーンの信じられないほどのアナクロニズム。登場人物の設定などステレオタイプそのもので、やたら説明的で言い訳的なセリフ(米軍の本土空襲に対して、非戦闘員への空襲は日本軍の方が先だった、という歴史の授業みたいな展開など)の連発。ハッキリ言って、主演が工藤夕貴でなかったら、昭和30年代の映画と錯覚しただろう。
封切られた頃に労働組合がこの映画の前売券を扱っていた事実が示すように、これは旧総評系時代錯誤の輩が好みそうな映画なのである。冒頭、ヒロインの通う高校の夏休みの宿題として“身近な戦争体験”をリポートするように言いつける先生は、明らかに日教組の構成員だし、判で押したような周囲の人々の描写も、大昔の組合運動高揚映画そっくりだ。
“大金をかけた空襲シーン”が売り物だったらしいが、そんなことをセールス・ポイントにすること自体古い。この映画は一般大衆から費用を集めるという新しい製作手段を採用したことも話題だが、映画製作に一口10万円以上の金を出す“一般大衆”とは、本当の意味での“一般大衆”だったのかすこぶる疑問だ。
監督は今井正で、これは彼の最後の作品である。かつて内外の映画賞を賑わせた巨匠も、この程度の作品でキャリアを終えてしまったことは寂しいことである。
東京の下町に住む高校生のゆかりは、親から戦争体験を聞きリポートにまとめるという宿題を出される。さっそく父親に話を聞こうとするが、得られたのは要領を得ない返答ばかり。そんなある日、父親の姉が飛び出した子供をかばって交通事故に遭う。背景には伯母の戦時中の体験があったようで、それをきっかけに父親は重い口を開き、ゆかりは父と伯母の戦争体験を知ることになる。
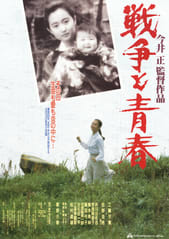
女優二人にそろって二役を演じさせていながら、それを少しもドラマとして生かしていない。そっくりの顔の女が出て来るのに、ほかの人物がその事実をまるで無視するなんて、どういうことだろう。
ヒロインの回想場面での、恋人と花畑で手をとりあって踊るシーンの信じられないほどのアナクロニズム。登場人物の設定などステレオタイプそのもので、やたら説明的で言い訳的なセリフ(米軍の本土空襲に対して、非戦闘員への空襲は日本軍の方が先だった、という歴史の授業みたいな展開など)の連発。ハッキリ言って、主演が工藤夕貴でなかったら、昭和30年代の映画と錯覚しただろう。
封切られた頃に労働組合がこの映画の前売券を扱っていた事実が示すように、これは旧総評系時代錯誤の輩が好みそうな映画なのである。冒頭、ヒロインの通う高校の夏休みの宿題として“身近な戦争体験”をリポートするように言いつける先生は、明らかに日教組の構成員だし、判で押したような周囲の人々の描写も、大昔の組合運動高揚映画そっくりだ。
“大金をかけた空襲シーン”が売り物だったらしいが、そんなことをセールス・ポイントにすること自体古い。この映画は一般大衆から費用を集めるという新しい製作手段を採用したことも話題だが、映画製作に一口10万円以上の金を出す“一般大衆”とは、本当の意味での“一般大衆”だったのかすこぶる疑問だ。
監督は今井正で、これは彼の最後の作品である。かつて内外の映画賞を賑わせた巨匠も、この程度の作品でキャリアを終えてしまったことは寂しいことである。

























