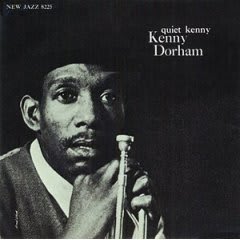上映時間が111分と、アニメーションにしてはやや長いと思われるが、弛緩している部分や目をはなして良い場面なんかひとつもない、すさまじい密度の高さを持つ
作品だ。
架空の街「宝町」を舞台に、子供ながら裏の世界を仕切っているクロとシロの二人の孤児が、再開発に名を借りた犯罪組織の進出騒ぎに巻き込まれてゆく過程を描く松本大洋の同名漫画の映画化。何より各登場人物の掘り下げの深さが尋常ではない。
腕っ節の強さと才覚で孤高を保っているつもりのクロと、幼く見えながらも実は誰よりもクロを想い、クロの心の支えとして屹立した存在感を示すシロとの関係性が、二人の屈託を含めて徹底的に描き込まれていることに感嘆する。彼らの抱える底なしの孤独と、一点の光となる微かな希望とが絶妙のイメージ描写により表現されるとき、胸が締め付けられるような切ない感動が湧き起こる。
主役の二人だけでなく、彼らを見守る浮浪者の老人の聡明ぶりや、昔気質のやくざとその一の子分との皮肉な運命、管轄の警察署のベテラン刑事と若手エリートも単なる作劇上の“飾り”ではなく、映画の中で確実に内面が変わってゆくドラマ性の一翼を担っている。対して“蛇”と呼ばれるマフィア(?)の元締めと殺し屋達には非人間性しかない。この対比がドラマにメリハリを付けると共に、作者のスタンスも明らかにさせる。それは人間性に対する掛け値なしの肯定だ。自らを信じ、また信ずるに値する他者を得ることが、ラスト近くのシロのセリフ通り“あんしん、あんしん”ということなのだ。
ノスタルジックで、しかしどこにもない街である舞台・宝町。この造型は見事と言うしかない(ここだけで入場料のモトは取れる)。観る者の度肝を抜くようなアクションシーン。凄惨なリアリズムと詩情あふれる美しい幻想場面が抜群のコントラスト。Plaidによる音楽も素晴らしい。
監督のマイケル・アリアスは米国人ながら日本のアニメーションに対する造型の深さを伺わせる。さらに声の出演が絶妙だ。クロに扮する二宮和也は上手い。終盤では“深層心理の声”まで担当しているが、まったく違和感のない安定した仕事ぶりだ。さらに凄いのがシロ役の蒼井優。陳腐な表現だが、キャラクターそのものに成りきっている。軽いトランス状態さえ感じさせる役柄への没入ぶりは圧倒的。ヤクザ役に田中泯を持ってきたのも作者の慧眼というしかなく、まるで「たそがれ清兵衛」の剣客がそのまま出てきたような凄みを感じさせる。
断じて子供向けの映画ではなく、アクの強いキャラ・デザインも相まって確実に観客を選ぶ作品だが、ヴォルテージの高さは今年度の邦画随一だ。必見。