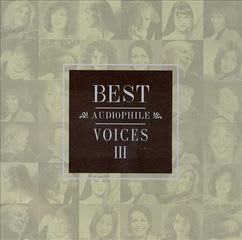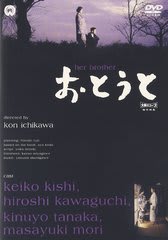(原題:Private Benjamin)81年作品。70年代後半に“女性映画ブーム”というのがあった。もっとも、これは日本の配給会社や映画雑誌が勝手に考案したキャッチフレーズで、実のところは自立的な女性を主人公にした映画が欧米で“たまたま”目立っていたというだけの話だ。一方ではアメリカでは80年代に入ると保守派の隆盛により、そのトレンドがハリウッドにも影響を与えるようになっていった。そんな中にあっては“女性映画”も無関係ではなかったらしく、コメディ仕立ての本作にその典型例を見ることが出来る。
富豪の娘であるジュディ・ベンジャミンは2度目の結婚式を迎え、心は浮き立っていた。しかしながら新しい旦那は結婚後に急死。そんな傷心の彼女に近付いたのは、新兵募集係を務めるジム・バラード軍曹であった。彼は軍隊がどんなに素晴らしいところかを力説し、彼女を入隊させることに成功。さっそく新兵訓練のキャンプに赴いたジュディを待っていたのは、例によって鬼のような教官と過酷な訓練であった。
元より世間知らずの彼女にとって毎日があり得ない展開の連続で疲労困憊してしまう。ところが、ひょんなことで実戦ゲームで思わぬ大勝利をもたらしたのをきっかけに、次第に軍隊の水に馴染んでいく。そして、ベルギーのNATO基地勤務に栄転すると共に素敵な彼氏もゲットする公算になり、彼女の人生は明るさを増してゆくのであった。
何と、70年代の“女性映画”で描かれていたフェミニズム的なモチーフは、ここでは“軍隊に入れば達成できる”という結論にすり替えられている。確かに、生死隣り合わせの戦時では男も女も関係なく、その意味では“平等”なのかもしれないが、かくのごとき牽強付会には面食らうばかりである。
ハワード・ジーフの演出には大きな破綻は無い。主役はゴールディ・ホーンで、いつものように“個人芸”で笑わせてくれるが、やればやるほど米軍のPR映画じみてくるのは何とも複雑な気分になってくる。加えてビル・コンティによる勇ましい音楽がそれを助長するのだから、観ている側は困惑するばかりだ(笑)。
なお、この“軍隊に入れば人間的に成長する”というパターンは、翌年に作られる「愛と青春の旅だち」でも踏襲されているが、軍事面で混迷を極める昨今においては当分取り上げられることのないネタであろう。良い意味でも悪い意味でも、映画は時代にリンクしていくものなのだ。