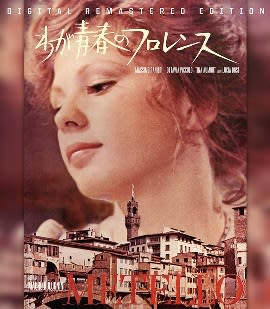(原題:ONE MORE TIME )2023年4月よりNetflixより配信されたタイムループ仕立てのスウェーデン製ラブコメ作品。他愛の無いシャシンなのだが、意外と楽しめた。脚本は少しばかり捻ってあるし、エクステリアはチャーミングだ。キャラクターもけっこう屹立している。何より上映時間が85分とコンパクトなのが良い。
主人公のアメリアは40歳になった現在も配偶者はもちろん交際相手もおらず、仕事は退屈で捨て鉢な人生を送っていた。そんな彼女がふと思い出したのは、幼少の頃に町外れに埋めたタイムカプセルのことだ。18歳になった日に掘り起こして開封する予定だったのだが、今まで失念していたのだ。暇つぶしに様子を見に行こうとしたその時、トラックと接触事故を起こして気を失ってしまう。

気が付くと、アメリアは18歳の誕生日にタイムスリップしていた。思わぬ形で若さを取り戻した彼女は当初は喜んでいたが、やがて同じ日を何度も繰り返すタイムループにハマったことに気付き愕然とする。何とかそこから脱出しようとするが、彼女の努力はことごとく水泡に帰す。
この設定はハロルド・ライミス監督の「恋はデジャ・ブ」(93年)に似ていると思ったら、劇中でもその作品のDVDが小道具として登場するので笑ってしまった。ただ「恋はデジャ・ブ」と違うのは、過去の特定の時点に主人公が飛ばされた上で、その一日が延々と繰り返されることだ。アメリアはライミス作品を“参考”にして、何かこの時間軸でやり残したことがあったはずだと奮闘するが、なかなか上手くいかない。
実はくだんのタイムカプセルに関係する人物が鍵を握っているのだが、それにどうアプローチするのか、その過程がちょっと面白い。ラストの扱いも意外性がある。ヨナタン・エツラーの演出は特段才気走ったところは無いが、観る者を退屈させないだけの堅実さは持ち合わせている。主演のヘッダ・スティールンステットが中年期も十代の頃も両方演じているが、あまり違和感を覚えないのは本人の演技力に加えてある種年齢不肖のルックスによるところが大きい。
マクスウェル・カニンガムにエリノア・シルヴェスパレ、ミリアム・イングリッド、ペル・フリッツェルといった顔ぶれはもちろん馴染みは無いが、皆良い演技をしている。そして何より主人公たちが身に付ける衣装や、住居の佇まいがカラフルで目を奪われる。そして郊外の自然の風景は本当に美しい。あまり期待するのは禁物かもしれないが、観て損するような内容ではないと思う。
主人公のアメリアは40歳になった現在も配偶者はもちろん交際相手もおらず、仕事は退屈で捨て鉢な人生を送っていた。そんな彼女がふと思い出したのは、幼少の頃に町外れに埋めたタイムカプセルのことだ。18歳になった日に掘り起こして開封する予定だったのだが、今まで失念していたのだ。暇つぶしに様子を見に行こうとしたその時、トラックと接触事故を起こして気を失ってしまう。

気が付くと、アメリアは18歳の誕生日にタイムスリップしていた。思わぬ形で若さを取り戻した彼女は当初は喜んでいたが、やがて同じ日を何度も繰り返すタイムループにハマったことに気付き愕然とする。何とかそこから脱出しようとするが、彼女の努力はことごとく水泡に帰す。
この設定はハロルド・ライミス監督の「恋はデジャ・ブ」(93年)に似ていると思ったら、劇中でもその作品のDVDが小道具として登場するので笑ってしまった。ただ「恋はデジャ・ブ」と違うのは、過去の特定の時点に主人公が飛ばされた上で、その一日が延々と繰り返されることだ。アメリアはライミス作品を“参考”にして、何かこの時間軸でやり残したことがあったはずだと奮闘するが、なかなか上手くいかない。
実はくだんのタイムカプセルに関係する人物が鍵を握っているのだが、それにどうアプローチするのか、その過程がちょっと面白い。ラストの扱いも意外性がある。ヨナタン・エツラーの演出は特段才気走ったところは無いが、観る者を退屈させないだけの堅実さは持ち合わせている。主演のヘッダ・スティールンステットが中年期も十代の頃も両方演じているが、あまり違和感を覚えないのは本人の演技力に加えてある種年齢不肖のルックスによるところが大きい。
マクスウェル・カニンガムにエリノア・シルヴェスパレ、ミリアム・イングリッド、ペル・フリッツェルといった顔ぶれはもちろん馴染みは無いが、皆良い演技をしている。そして何より主人公たちが身に付ける衣装や、住居の佇まいがカラフルで目を奪われる。そして郊外の自然の風景は本当に美しい。あまり期待するのは禁物かもしれないが、観て損するような内容ではないと思う。