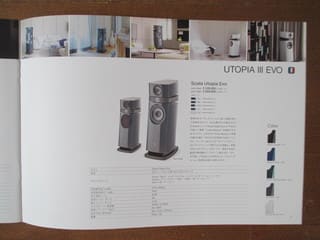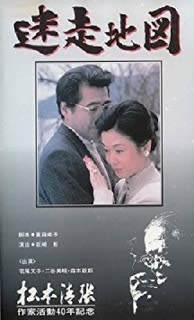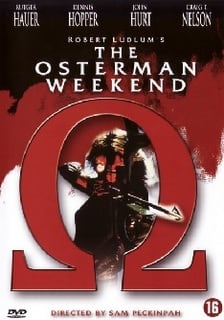(原題:UNA MUJER FANTASTICA)ヒリヒリとした感触を持つ辛口の映画ながら、求心力は高い。マイノリティに対する風当たりの強さを社会批判的に描きつつ、最終的に印象に残るのは主人公の凛とした存在感だ。観て良かったと思える佳編である。
サンティアゴのナイトクラブでウェイトレスをしながら歌手活動をおこなうマリーナは、元男性のトランスジェンダーだ。彼女は、年の離れた恋人オルランドと一緒に暮らしている。関係は順調で、今度2人で旅行に出掛ける計画を立てていた。だが、ある晩オルランドは自宅で倒れてしまう。病院に担ぎ込まれたが、帰らぬ人になった。マリーナは悲しむが、オルランドの元妻およびその息子の態度は冷たく、住んでいたアパートから追い出される。さらには通夜や葬儀にも出席出来ないことになり、彼女は唯一の希望であるオルランドとの旅行のチケットを探し回る。
冒頭の、オルランドが封筒を紛失するシークエンスが、後半のマリーナの行動の伏線になっているのをはじめ、本作のシナリオは良く出来ている。最初はヒロインに親切にしてくれたオルランドの弟も、次第に世間体を気にするようになり、警察も今回の一件を性犯罪だと決めつける素振りを見せる。ついにはマリーナは、オルランドの関係者によって手酷い仕打ちを受けてしまう。
この容赦ない筋書きには身を切られる思いがするが、一方で彼女をフォローしてくれる人もいる。それは彼女が働く店の主人であり、ボイストレーナーの教師だったり、兄弟たちだ。これらは決して御都合主義的な人物配置ではなく、いわば“渡る世間に鬼はない”という作者のポジティヴな達観と捉えるのが正しいだろう。主人公の“自分は一体何者なのか”というアイデンティティの検証に立ち会う、スリリングなプロセスを体感出来る。
セバスティアン・レリオの演出は粘り強く、さらに鏡を使った印象的なシーンを多用するなど、観客を引っ張る上で健闘している。特筆したいのが音楽の使い方で、主人公が歌手であるという点が最大限活かされている。ラストの処理はもちろん、序盤のクラブでの歌唱、そして挿入されるアラン・パーソンズ・プロジェクトのナンバー「タイム」が大きな効果を上げている。
主演のダニエラ・ヴェガもトランスジェンダーであるためか、切迫したパフォーマンスで観る者を釘付けにする。鋭い眼差しが印象的な逸材だ。オルランドに扮するフランシスコ・レジェスも良い味を出している。第90回アカデミー賞における外国語映画賞部門のチリ代表で、見事大賞に輝いた。ベンハミン・エチャサレッタのカメラが捉えるサンティアゴの街の風景も興味深い。