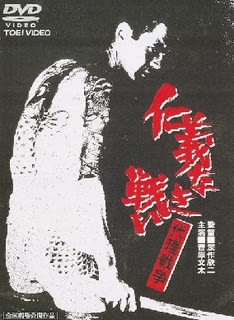(原題:NAVALNY )現時点では必見の作品だと思う。題材は世界情勢を俯瞰する上で欠かせないものであり、しかも映画として実に良く出来ている。ドキュメンタリーではあるが娯楽作品としてのテイストも持ち合わせているほどだ。
ロシアの反体制派の活動家アレクセイ・アナトーリエヴィチ・ナワリヌイは、2007年に民主主義政党“ヤブロコ”を除名処分になった後、弁護士の肩書を利用して政府や大企業の不正を次々と暴いてゆき、政界にも進出する。政権側は彼を最大の敵と見做し、不当な逮捕を繰り返す。そして2020年8月、ナワリヌイは西シベリアのトムスクから旅客機でモスクワに向かう途中で何者かに毒物を盛られ、昏睡状態に陥る。ベルリンの病院に避難し奇跡的に一命を取り留めた彼は、自ら調査チームを結成して真相究明に乗り出す。

反体制の急先鋒であったナワリヌイが、政府当局から目をつけられて危うく消されそうになるプロセスは社会派サスペンスの装いだが、さらに興味深いのは危機を脱してから逆襲に転じるくだりである。彼はイギリスに本拠を置く調査報道機関“ベリングキャット”のスタッフと共闘。いわゆる“オープンソース・インベスティゲーション”の手法を駆使して、真実を突き止める。特に、関係者に成りすまして容疑者の一人をトラップに嵌めるパートなど、並みのスパイ映画が裸足で逃げ出すほどのサスペンスを醸成させている。
妻のユリヤをはじめとする親族や、志を同じくする仲間と目標に向かって突き進む彼の雄姿を見ていると、さらに悪化した現在のロシア情勢を何とか打開する道があるのではないかと、淡い希望を持ったりする。国威高揚のため隣国に戦争を仕掛けたプーチンの支持率は高いが、劇中で描かれたように少なくない数のナワリヌイの支持者たちが存在するのも事実。今は彼は逆境にあるが、希望を捨ててはならないと、強く思う。
ダニエル・ロアーの演出は小気味良く、98分という短めの尺も相まって、強い印象を残す。マリウス・デ・ブリーズによる音楽も効果的。なお、ナワリヌイは2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻を厳しく批判している。もしも彼のような者がロシアの指導者になれば、世界はもっと明るくなるかもしれない。
ロシアの反体制派の活動家アレクセイ・アナトーリエヴィチ・ナワリヌイは、2007年に民主主義政党“ヤブロコ”を除名処分になった後、弁護士の肩書を利用して政府や大企業の不正を次々と暴いてゆき、政界にも進出する。政権側は彼を最大の敵と見做し、不当な逮捕を繰り返す。そして2020年8月、ナワリヌイは西シベリアのトムスクから旅客機でモスクワに向かう途中で何者かに毒物を盛られ、昏睡状態に陥る。ベルリンの病院に避難し奇跡的に一命を取り留めた彼は、自ら調査チームを結成して真相究明に乗り出す。

反体制の急先鋒であったナワリヌイが、政府当局から目をつけられて危うく消されそうになるプロセスは社会派サスペンスの装いだが、さらに興味深いのは危機を脱してから逆襲に転じるくだりである。彼はイギリスに本拠を置く調査報道機関“ベリングキャット”のスタッフと共闘。いわゆる“オープンソース・インベスティゲーション”の手法を駆使して、真実を突き止める。特に、関係者に成りすまして容疑者の一人をトラップに嵌めるパートなど、並みのスパイ映画が裸足で逃げ出すほどのサスペンスを醸成させている。
妻のユリヤをはじめとする親族や、志を同じくする仲間と目標に向かって突き進む彼の雄姿を見ていると、さらに悪化した現在のロシア情勢を何とか打開する道があるのではないかと、淡い希望を持ったりする。国威高揚のため隣国に戦争を仕掛けたプーチンの支持率は高いが、劇中で描かれたように少なくない数のナワリヌイの支持者たちが存在するのも事実。今は彼は逆境にあるが、希望を捨ててはならないと、強く思う。
ダニエル・ロアーの演出は小気味良く、98分という短めの尺も相まって、強い印象を残す。マリウス・デ・ブリーズによる音楽も効果的。なお、ナワリヌイは2022年2月から始まったロシアのウクライナ侵攻を厳しく批判している。もしも彼のような者がロシアの指導者になれば、世界はもっと明るくなるかもしれない。