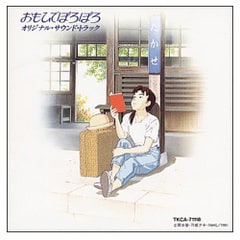91年作品。この頃の日本映画界は質的にドン底にあった。新進気鋭の映像作家は出てこず、ベテラン陣も行き詰まっていた状況。その中にあって宮崎駿=高畑勲コンビの作り出す映像群だけが屹立したクォリティの高さを誇っていた。本作はその代表作だ(監督は高畑が担当している)。
時代設定は1982年の夏。東京の大企業に勤めるOLのタエ子(27歳)は休暇を取って東北の山村に旅行した折、ふとしたはずみで小学校5年の自分を回想していく。ドラマチックな出来事があるわけではない。アニメーションとしては実に地味な題材ながら、これだけ見せてくれるのというのはすごい。
人物描写のうまさに舌を巻く。キャリア指向でもなく、かといって結婚したい相手もいない、という平凡な20代後半の女性を等身大に、しかも魅力的にとらえた作品は、公開当時も今も含めた日本映画の中ではそう多くはない。登場してくる人々はすべてどこにでもいそうな、普通の市井の人々である。それでいて、皆とても存在感があり、観客が納得できるキャラクターになっているのは、作者の素材をとらえる目が確かなせいだろう。
タエ子はその村で有機農業を推進しているトシオと出会う。タエ子より年下だが、頼りになる好青年だ。映画はそれから自然と人間のかかわりという重大なテーマに入っていく。ここで作者は都会=悪、田舎=善というような単純な図式は取っていない。一見自然に囲まれたような田舎の風景は、実は人間が自然と戦い、共存できるようになった結果なのだ。そしてそれを維持するためにはハンパではない努力が必要なことも示される。ただ、その主題はヒロインの人生の転機を描くというメインテーマの陰にかくれていて決して出しゃばることはない。このあたりも作者の節度が感じられて好ましい。
そしてアニメーション技術だが、ハッキリ言って超絶レベルである。回想場面はソフト・フォーカスのようなリリカルな画調だ。観客の郷愁を誘うノスタルジックな場面の連続で、それだけで目頭が熱くなる。対して現在(82年)を描く部分は、驚異的リアリズムで圧倒される。これはもう実写とほとんど変わらない。セリフを先に収録してから画面を作るプレスコ方式が威力を発揮し、主人公の2人は声を担当する今井美樹と柳葉敏郎が本当に演じているのではないかと錯覚を起こさせるほどだ。しかし、千変万化する自然の風景と登場人物の思いきった構図など、ちゃんとアニメーションでしか出来ない映像をカバーしているのがすごい。
アニメーションにしては異様にカット数が少ない。つまり、長回しが多くカメラの移動があまりない(アニメーションでこう言うのもヘンだけど)のも、落ち着いた雰囲気を出すのに貢献している。さらに原色を抑え、繊細極まりない中間色を多用していることがかなりの効果を上げている。そして回想場面でのナツメロはもとより、村の風景のバックに流れる東欧のエスニック・サウンドという音楽センスには脱帽した。都はるみの歌う主題歌に乗った感動のラストシーンまで、欠点らしいものは挙げることができない。高畑監督作としても「火垂るの墓」と並ぶ傑作である。