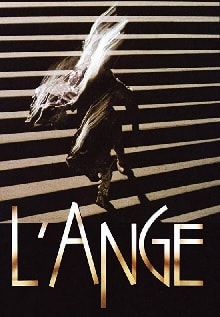(原題:BLACKKKLANSMAN)オスカーを獲得した「グリーンブック」よりはいくらか面白く、スパイク・リー監督作としても久々に水準に達する出来だとは思うが、絶賛されるようなヴォルテージの高い内容かというと、首を捻らざるを得ない。実話の映画化との触れ込みながら、あまりストーリーに説得力が無いのも気になるところだ。
1970年。コロラド州コロラドスプリングスの警察署で初の黒人刑事として採用されたロン・ストールワースは、当初は署内の白人のスタッフから煙たがられていた。しかし情報部に配属されると、持ち前の積極性を発揮。過激な白人至上主義団体としてマークされていたKKK(クー・クラックス・クラン)に潜り込むため、メンバー募集に電話をかける。
KKKの幹部に電話口で気に入られたロンだったが、問題は入会の面接試験を受けるのが事実上不可能であることだった。そこで、ロンは同僚の白人刑事フリップ・ジマーマンに共同捜査を持ちかける。電話はロンが担当し、フリップがKKKの連中と直接会うというのだ。つまりはKKKの内部調査のために、二人で一人の人物を演じる変則的なフォーメーションが成立する。
シリアスな題材を扱ってはいるが、タッチは明るくスムーズだ。効果的なギャグも時折挿入され、まさしくこれはスパイク・リーの映画なのだと納得する。特に“白人の英語と黒人の英語は違う”というネタには笑った。しかしながら、設定とストーリーには無理がある。
二人一役でKKKに潜入する主人公達だが、声や話し方が同一であるはずがなく、そのあたりを見破られる危険性は無かったのか疑問だ。そもそも、警察当局やロン達に明確な目的性が感じられない。最初から白人刑事に担当させた方が良かったのではないか。そのあたりを糊塗するかのように、後半ではKKKによるテロ騒ぎが扱われるが、取って付けたような印象だ。実話という御題目に寄りかかりすぎて、脚本の精査を怠ったようである(オスカー受賞も納得できない)。
さらに、ラストでのニュースフィルムの挿入も賛否が分かれるところだろう。確かに今もKKKは存在しているが、それが現時点で人種問題に総論的にコミットできる素材なのかどうか、甚だ疑問だ。なお、主演のジョン・デイヴィッド・ワシントンとアダム・ドライバーは好演。ワシントンの父親はあのデンゼルであることを知り、少し驚いた。