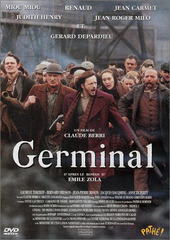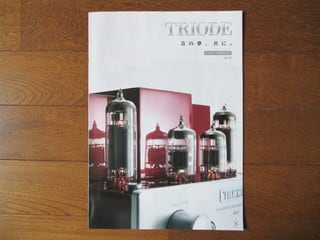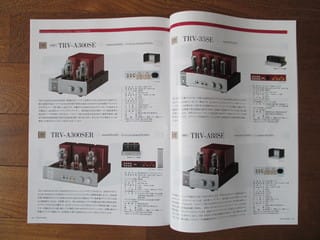(原題:Gravity )アトラクションとしては楽しめるのかもしれないが、真面目に対峙して観るとあまり上等ではない劇映画だ。とにかく突っ込みどころが多すぎる。レベルとしてはローランド・エメリッヒ監督による一連の“大味ディザスター映画”と良い勝負だろう。
ハッブル宇宙望遠鏡のメンテナンスのため船外作業をしていたストーン博士と宇宙飛行士のマットは、突然スペースデブリ(宇宙ゴミ)の急襲を受ける。宇宙空間に放り出され、たった一本のロープで繋がっているだけの2人。空気の残量はわずかでヒューストンとの交信も断たれてしまう。果たして、この絶望的な状況の中から生還出来るのか・・・・という筋書きだ。

人工衛星の爆発事故が起こっても、かくも簡単に衛星破壊の連鎖が発生するとは考えにくい。だいたい、各人工衛星は軌道傾斜角がそれぞれ異なるのではなかったか。宇宙望遠鏡の隣に国際宇宙ステーション(ISS)があり、そのまた隣に中国の宇宙ステーションがあるという位置関係は納得出来ない。ハッブル望遠鏡は赤道付近にあるらしく、対してISSはロシア上空にあるという。どう考えてもジェットパックでひょいと行ける距離ではないし、それ以前に、この設定は御都合主義的な臭いがプンプンする。
やっとのことでISSにたどり着いたストーンが、いきなり宇宙服を脱いで半裸になるシーンには仰天した。ぶつかれば致命傷になりそうな浮遊物が大量に存在している環境で、この行動は有り得ない。しかも、船外活動には必需品であるはずのオムツをしていた気配も無い。そもそもISSの他の乗組員はどこに行った。全員が船外に出ていたために全滅したとは考えにくい。かといってISS自体は全壊していないし、脱出用のカプセルもそのままだ。

そして、なぜか中国の宇宙ステーションにも誰もいない。無人ステーションではないことは生活日常品が浮いていることで分かるのだが、彼らの消息については何も説明されていない。また消火器が噴射剤に使われる場面で失笑し、計器類が中国語で書かれた操縦席を前にしたヒロインが“何とかうまくやってしまう”くだりで脱力した。極めつけは、長らく宇宙空間にいて足腰が弱っているとはとても思えないラストの主人公の行動。大風呂敷を広げるなら、もうちょっと上手くやってほしいものだ。
考えてみれば、リアル系SF映画の注目作とされているわりには、新しいモチーフはほとんどない。宇宙空間での“遭難”なんか、今までいくつもの映像作品で取り上げられていたし、大金を掛けて作られたはずの映像も、3D画面における効果以外には造型が凡庸だ。
キャストはサンドラ・ブロックとジョージ・クルーニーの2人しかおらず、それぞれ頑張ってはいるのだが、どうもこの底の浅い作劇では評価しかねる。監督は「トゥモロー・ワールド」などのアルフォンソ・キュアロンで、本作に限ればさほどの“作家性”は見出せず。個人的には、観なくても良い映画だった。
ハッブル宇宙望遠鏡のメンテナンスのため船外作業をしていたストーン博士と宇宙飛行士のマットは、突然スペースデブリ(宇宙ゴミ)の急襲を受ける。宇宙空間に放り出され、たった一本のロープで繋がっているだけの2人。空気の残量はわずかでヒューストンとの交信も断たれてしまう。果たして、この絶望的な状況の中から生還出来るのか・・・・という筋書きだ。

人工衛星の爆発事故が起こっても、かくも簡単に衛星破壊の連鎖が発生するとは考えにくい。だいたい、各人工衛星は軌道傾斜角がそれぞれ異なるのではなかったか。宇宙望遠鏡の隣に国際宇宙ステーション(ISS)があり、そのまた隣に中国の宇宙ステーションがあるという位置関係は納得出来ない。ハッブル望遠鏡は赤道付近にあるらしく、対してISSはロシア上空にあるという。どう考えてもジェットパックでひょいと行ける距離ではないし、それ以前に、この設定は御都合主義的な臭いがプンプンする。
やっとのことでISSにたどり着いたストーンが、いきなり宇宙服を脱いで半裸になるシーンには仰天した。ぶつかれば致命傷になりそうな浮遊物が大量に存在している環境で、この行動は有り得ない。しかも、船外活動には必需品であるはずのオムツをしていた気配も無い。そもそもISSの他の乗組員はどこに行った。全員が船外に出ていたために全滅したとは考えにくい。かといってISS自体は全壊していないし、脱出用のカプセルもそのままだ。

そして、なぜか中国の宇宙ステーションにも誰もいない。無人ステーションではないことは生活日常品が浮いていることで分かるのだが、彼らの消息については何も説明されていない。また消火器が噴射剤に使われる場面で失笑し、計器類が中国語で書かれた操縦席を前にしたヒロインが“何とかうまくやってしまう”くだりで脱力した。極めつけは、長らく宇宙空間にいて足腰が弱っているとはとても思えないラストの主人公の行動。大風呂敷を広げるなら、もうちょっと上手くやってほしいものだ。
考えてみれば、リアル系SF映画の注目作とされているわりには、新しいモチーフはほとんどない。宇宙空間での“遭難”なんか、今までいくつもの映像作品で取り上げられていたし、大金を掛けて作られたはずの映像も、3D画面における効果以外には造型が凡庸だ。
キャストはサンドラ・ブロックとジョージ・クルーニーの2人しかおらず、それぞれ頑張ってはいるのだが、どうもこの底の浅い作劇では評価しかねる。監督は「トゥモロー・ワールド」などのアルフォンソ・キュアロンで、本作に限ればさほどの“作家性”は見出せず。個人的には、観なくても良い映画だった。