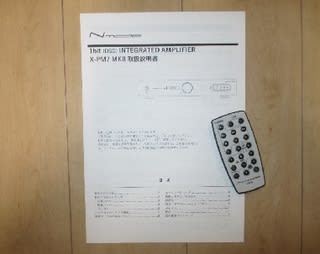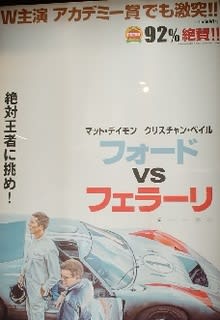(原題:MAHLER)74年イギリス作品。ケン・ラッセル監督の“異常感覚”とも言うべきユニークすぎるタッチと、本来的な伝記映画のルーティンが良い按配にミックスされ、普遍性と作家性が両立する得難い作品に仕上げられている。また、視点を当事者ではなく傍らにいる者(この場合はマーラーの妻)に合わせている点も、素材をいたずらに高踏的に持ち上げない点で的確であったと言えよう。
1911年、ニューヨークでの指揮活動を終えた作曲家グスタフ・マーラーは、ウィーンに帰るために列車に乗っていた。懸案の第十交響曲の完成に向けての構想を練っている間、彼の脳裏には過去の出来事が去来する。ボヘミア地区で生を受けた彼は、貧しい子供時代を送っていた。それでも祖父はグスタフにピアノを習わせ、そこで彼は音楽に傾倒する。

長じてかなり年下の妻アルマと結婚するものの、軍人マックスがアルマに言い寄っていることを知るに及び、気が気ではない。列車に同乗しているアルマも過去を回想していた。実は彼女は元々作曲家志望だった。ところがグスタフの友人である歌手に習作を酷評され、夢を断念したのだった。2人の想いを乗せながら、やがて列車はウィーンに到着する。
冒頭、マーラーの第三交響曲の第一楽章をバックに繭の中からアルマが出てくるというシーンが映し出される。もちろんこれはマーラーの夢の話なのだが、彼が妻を失うことを恐れている心理状態の暗喩だ。対してアルマは、夫の仕事のために大きな犠牲を強いられており、根深い不満を抱いている。さらには自らの作品をバカにされ、ショックでその楽譜を森の中に埋めてしまう。両者の格差は埋めようがないと思われるが、それでもグスタフが製作を続けてこられたのは、アルマの存在があってこそなのだ。
列車の中での時間内に作劇を限定しながら、登場人物の内面を最大限広げるという意欲的な構成が功を奏している。また、ラッセル監督らしい独特の映像処理もフィーチャーされており、少年マーラーが夜の森の中で、突如姿をあらわした白馬に乗るシーンや、マックスが突然ナチスの親衛隊となるくだりなどは大いに盛り上がる。
主演のロバート・パウエルは好演。アルマに扮したジョージナ・ヘイルも健闘している。楽曲の演奏はベルナルド・ハイティンク指揮のアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団によるもので、ケレン味のないパフォーマンスが映画の雰囲気とマッチしていた。ディック・ブッシュによる撮影、シャーリー・ラッセルの衣装デザインも申し分ない。ラスト、列車から降りて家路に向かうマーラー達の“その後の運命”を考えると、感慨深いものがある。
1911年、ニューヨークでの指揮活動を終えた作曲家グスタフ・マーラーは、ウィーンに帰るために列車に乗っていた。懸案の第十交響曲の完成に向けての構想を練っている間、彼の脳裏には過去の出来事が去来する。ボヘミア地区で生を受けた彼は、貧しい子供時代を送っていた。それでも祖父はグスタフにピアノを習わせ、そこで彼は音楽に傾倒する。

長じてかなり年下の妻アルマと結婚するものの、軍人マックスがアルマに言い寄っていることを知るに及び、気が気ではない。列車に同乗しているアルマも過去を回想していた。実は彼女は元々作曲家志望だった。ところがグスタフの友人である歌手に習作を酷評され、夢を断念したのだった。2人の想いを乗せながら、やがて列車はウィーンに到着する。
冒頭、マーラーの第三交響曲の第一楽章をバックに繭の中からアルマが出てくるというシーンが映し出される。もちろんこれはマーラーの夢の話なのだが、彼が妻を失うことを恐れている心理状態の暗喩だ。対してアルマは、夫の仕事のために大きな犠牲を強いられており、根深い不満を抱いている。さらには自らの作品をバカにされ、ショックでその楽譜を森の中に埋めてしまう。両者の格差は埋めようがないと思われるが、それでもグスタフが製作を続けてこられたのは、アルマの存在があってこそなのだ。
列車の中での時間内に作劇を限定しながら、登場人物の内面を最大限広げるという意欲的な構成が功を奏している。また、ラッセル監督らしい独特の映像処理もフィーチャーされており、少年マーラーが夜の森の中で、突如姿をあらわした白馬に乗るシーンや、マックスが突然ナチスの親衛隊となるくだりなどは大いに盛り上がる。
主演のロバート・パウエルは好演。アルマに扮したジョージナ・ヘイルも健闘している。楽曲の演奏はベルナルド・ハイティンク指揮のアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団によるもので、ケレン味のないパフォーマンスが映画の雰囲気とマッチしていた。ディック・ブッシュによる撮影、シャーリー・ラッセルの衣装デザインも申し分ない。ラスト、列車から降りて家路に向かうマーラー達の“その後の運命”を考えると、感慨深いものがある。