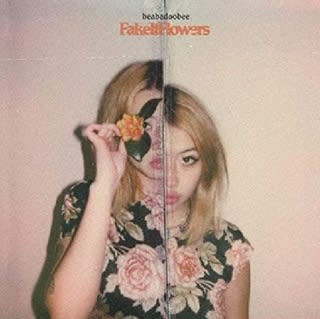すでに惰性になった感はあるが、年末恒例の2020年の個人的な映画ベストテンを発表したいと思う(^^;)。
日本映画の部
第一位 なぜ君は総理大臣になれないのか
第二位 本気のしるし
第三位 風の電話
第四位 はりぼて
第五位 his
第六位 37セカンズ
第七位 彼女は夢で踊る
第八位 プリズン・サークル
第九位 のぼる小寺さん
第十位 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実

外国映画の部
第一位 パラサイト 半地下の家族
第二位 21世紀の資本
第三位 行き止まりの世界に生まれて
第四位 ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
第五位 黒い司法 0%からの奇跡
第六位 オフィシャル・シークレット
第七位 レイニーデイ・イン・ニューヨーク
第八位 赤い闇 スターリンの冷たい大地で
第九位 シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!
第十位 カセットテープ・ダイアリーズ

2020年に世間を騒がせ、おそらく今後もしばらくは続くと思われるコロナ禍が、映画界をも直撃した。緊急事態宣言時にはすべての映画館はクローズ。ようやく制限が解除されても、上映する映画が無い。特にハリウッド製の話題作は軒並み公開延期だ。それでもマイナー系を中心に各劇場はラインナップを揃え、こちらも何とかベストテンを選べたのは安心した。
日本映画ではドキュメンタリー部門の健闘が光っていたが、それだけ“現実”の重みがヘタなフィクションを凌駕したということだろう。特に政治の無力性が国民の生活を圧迫している昨今、実録物はこれからも大きな存在感を持って作られると思う。
外国映画では何といっても「パラサイト 半地下の家族」のオスカー獲得が話題になった。ただし、これを観て“韓国社会は格差が大きくて大変だなァ”という感想を安易に持ってしまうのは禁物だ。社会格差は日本の方が大きいのである。この実態を我が事のように捉えるか、あるいは他人事にしてしまえるのか、その“断絶”が世の中を覆っているように感じる。
なお、以下の通り各賞も選んでみた。まずは邦画の部。
監督:大島新(なぜ君は総理大臣になれないのか)
脚本:深田晃司、三谷伸太朗(本気のしるし)
主演男優:三浦春馬(天外者)
主演女優:土村芳(本気のしるし)
助演男優:遠山雄(いつくしみふかき)
助演女優:浅田美代子(朝が来る)
音楽:橋本一子(ばるぼら)
撮影:向後光徳(水上のフライト)
新人:宮沢氷魚(his)、モトーラ世理奈(風の電話)、小野莉奈(テロルンとルンルン)、池田エライザ監督(夏、至るころ)
次は洋画の部。
監督:ジャスティン・ペンバートン(21世紀の資本)
脚本:ポン・ジュノ、ハン・ジヌォン(パラサイト 半地下の家族)
主演男優:マ・ドンソク(悪人伝)
主演女優:マーゴット・ロビー(ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY)
助演男優:フランコ・ネロ(コリーニ事件)
助演女優:ナタリー・ドーマー(博士と狂人)
音楽:ロマン・トルイエ(シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!)
撮影:ホン・ギョンピョ(パラサイト 半地下の家族)
新人:パク・ジフ(はちどり)、リナ・クードリ(パピチャ 未来へのランウェイ)、オリヴィア・ワイルド監督(ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー)
ついでに、ワーストテンも選んでみた(笑)。
邦画ワースト
1.Fukushima 50
体制に阿って事実をねじ曲げるという、映画人として最も恥ずべき構図が展開している。ワーストワンは決定的だ。
2.ミッドナイトスワン
悪ふざけとしか思えない、不快な場面の連続。
3.君が世界のはじまり
4.宇宙でいちばんあかるい屋根
5.スパイの妻
ヴェネツィアでの監督賞受賞は“功労賞”だとは承知しているが、それにしても作品の質が低い。
6.おらおらでひとりいぐも
7.私をくいとめて
8.ロマンスドール
9.記憶の技法
10.ソワレ
洋画ワースト
1.テネット
アイデア倒れ。映画的興趣は見当たらない。
2.燃ゆる女の肖像
それらしい雰囲気だけ。中身は無い。
3.1917 命をかけた伝令
技巧優先で、ドラマが不在。
4.男と女 人生最良の日々
5.ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語
6.悪の偶像
7.ペイン・アンド・グローリー
8.ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ
9.ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋
10.リチャード・ジュエル
ローカルな話題としては、キノシネマ天神のオープンを挙げたい。館名に“天神”と付いてはいるが、ロケーションは天神とは離れている。それでもミニシアターが出来たことは実に大きい。しかも3スクリーンも備えている。これからどういう作品を提供してくれるのか、実に楽しみである。
日本映画の部
第一位 なぜ君は総理大臣になれないのか
第二位 本気のしるし
第三位 風の電話
第四位 はりぼて
第五位 his
第六位 37セカンズ
第七位 彼女は夢で踊る
第八位 プリズン・サークル
第九位 のぼる小寺さん
第十位 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実

外国映画の部
第一位 パラサイト 半地下の家族
第二位 21世紀の資本
第三位 行き止まりの世界に生まれて
第四位 ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
第五位 黒い司法 0%からの奇跡
第六位 オフィシャル・シークレット
第七位 レイニーデイ・イン・ニューヨーク
第八位 赤い闇 スターリンの冷たい大地で
第九位 シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!
第十位 カセットテープ・ダイアリーズ

2020年に世間を騒がせ、おそらく今後もしばらくは続くと思われるコロナ禍が、映画界をも直撃した。緊急事態宣言時にはすべての映画館はクローズ。ようやく制限が解除されても、上映する映画が無い。特にハリウッド製の話題作は軒並み公開延期だ。それでもマイナー系を中心に各劇場はラインナップを揃え、こちらも何とかベストテンを選べたのは安心した。
日本映画ではドキュメンタリー部門の健闘が光っていたが、それだけ“現実”の重みがヘタなフィクションを凌駕したということだろう。特に政治の無力性が国民の生活を圧迫している昨今、実録物はこれからも大きな存在感を持って作られると思う。
外国映画では何といっても「パラサイト 半地下の家族」のオスカー獲得が話題になった。ただし、これを観て“韓国社会は格差が大きくて大変だなァ”という感想を安易に持ってしまうのは禁物だ。社会格差は日本の方が大きいのである。この実態を我が事のように捉えるか、あるいは他人事にしてしまえるのか、その“断絶”が世の中を覆っているように感じる。
なお、以下の通り各賞も選んでみた。まずは邦画の部。
監督:大島新(なぜ君は総理大臣になれないのか)
脚本:深田晃司、三谷伸太朗(本気のしるし)
主演男優:三浦春馬(天外者)
主演女優:土村芳(本気のしるし)
助演男優:遠山雄(いつくしみふかき)
助演女優:浅田美代子(朝が来る)
音楽:橋本一子(ばるぼら)
撮影:向後光徳(水上のフライト)
新人:宮沢氷魚(his)、モトーラ世理奈(風の電話)、小野莉奈(テロルンとルンルン)、池田エライザ監督(夏、至るころ)
次は洋画の部。
監督:ジャスティン・ペンバートン(21世紀の資本)
脚本:ポン・ジュノ、ハン・ジヌォン(パラサイト 半地下の家族)
主演男優:マ・ドンソク(悪人伝)
主演女優:マーゴット・ロビー(ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY)
助演男優:フランコ・ネロ(コリーニ事件)
助演女優:ナタリー・ドーマー(博士と狂人)
音楽:ロマン・トルイエ(シラノ・ド・ベルジュラックに会いたい!)
撮影:ホン・ギョンピョ(パラサイト 半地下の家族)
新人:パク・ジフ(はちどり)、リナ・クードリ(パピチャ 未来へのランウェイ)、オリヴィア・ワイルド監督(ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー)
ついでに、ワーストテンも選んでみた(笑)。
邦画ワースト
1.Fukushima 50
体制に阿って事実をねじ曲げるという、映画人として最も恥ずべき構図が展開している。ワーストワンは決定的だ。
2.ミッドナイトスワン
悪ふざけとしか思えない、不快な場面の連続。
3.君が世界のはじまり
4.宇宙でいちばんあかるい屋根
5.スパイの妻
ヴェネツィアでの監督賞受賞は“功労賞”だとは承知しているが、それにしても作品の質が低い。
6.おらおらでひとりいぐも
7.私をくいとめて
8.ロマンスドール
9.記憶の技法
10.ソワレ
洋画ワースト
1.テネット
アイデア倒れ。映画的興趣は見当たらない。
2.燃ゆる女の肖像
それらしい雰囲気だけ。中身は無い。
3.1917 命をかけた伝令
技巧優先で、ドラマが不在。
4.男と女 人生最良の日々
5.ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語
6.悪の偶像
7.ペイン・アンド・グローリー
8.ラストブラックマン・イン・サンフランシスコ
9.ロング・ショット 僕と彼女のありえない恋
10.リチャード・ジュエル
ローカルな話題としては、キノシネマ天神のオープンを挙げたい。館名に“天神”と付いてはいるが、ロケーションは天神とは離れている。それでもミニシアターが出来たことは実に大きい。しかも3スクリーンも備えている。これからどういう作品を提供してくれるのか、実に楽しみである。