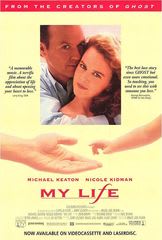94年東映京都作品。この映画が公開された年は、東宝と松竹で“忠臣蔵対決”が展開されており、ファンの間で話題になっていた。一人蚊帳の外に置かれた東映が、とりあえず製作したようなのが本作である。ただし同じ“時代物”といっても題材が明治時代で、チャンバラの要素も無い。興業面でも振るわず、何だか企画面で“ハズしてしまった”ような印象を受けるシャシンだ(笑)。
明治末、熊本にあった九州随一の遊郭“東雲楼”おける女たちの愛憎を描く。監督はベテランの関本郁夫。脚本は松田寛夫によるオリジナルで、撮影に森田富士郎、音楽に佐藤勝という手練れのスタッフを揃えている。しかしながら、出来としてはあまりよろしくない。
とにかく登場する女たちがとことん頭が悪いのには呆れる。東雲楼の頭である鶴(かたせ梨乃)はシッカリしているように見えて、ロクでもない相場師(津川雅彦)に貢いでしまうし、お茶子頭の志津(斎藤慶子)は、結ばれないとわかっている男(風間トオル)のために鶴の足を引っ張ってしまう。
借金の返済を間近に控えた銀龍(鳥越マリ)は、理不尽な母親のためにまた借金を重ねる。その他、東雲楼のメンバー全員が目先のことしか考えず(本人たちもそれは承知しているのだが)、結果として自分の首を締めてしまう。彼女たちに出来るのは、福太郎(及川麻衣)のように、ひたすら元気に歌って踊って“ほれほれ見んしゃい”とケツをまくることだけだ。
何も考えず、バイタリティだけで生きていく女たちは、哀れには思うが同情できない。それを思い入れたっぷりに“こういう女もいじらしくていいでしょ”と差し出す神経は理解の外にある。
ただ、面白かったのが斎藤慶子と南野陽子の方言ネイティヴ・スピーカー対決(笑)。東映でしか絶対出来ないエゲツなさ全開の応酬で、東京のモンにはわからない異様な熱気が画面に横溢する。この良さがわかるのは地方出身者の特権かもしれない(意味不明 ^^;)。




明治末、熊本にあった九州随一の遊郭“東雲楼”おける女たちの愛憎を描く。監督はベテランの関本郁夫。脚本は松田寛夫によるオリジナルで、撮影に森田富士郎、音楽に佐藤勝という手練れのスタッフを揃えている。しかしながら、出来としてはあまりよろしくない。
とにかく登場する女たちがとことん頭が悪いのには呆れる。東雲楼の頭である鶴(かたせ梨乃)はシッカリしているように見えて、ロクでもない相場師(津川雅彦)に貢いでしまうし、お茶子頭の志津(斎藤慶子)は、結ばれないとわかっている男(風間トオル)のために鶴の足を引っ張ってしまう。
借金の返済を間近に控えた銀龍(鳥越マリ)は、理不尽な母親のためにまた借金を重ねる。その他、東雲楼のメンバー全員が目先のことしか考えず(本人たちもそれは承知しているのだが)、結果として自分の首を締めてしまう。彼女たちに出来るのは、福太郎(及川麻衣)のように、ひたすら元気に歌って踊って“ほれほれ見んしゃい”とケツをまくることだけだ。
何も考えず、バイタリティだけで生きていく女たちは、哀れには思うが同情できない。それを思い入れたっぷりに“こういう女もいじらしくていいでしょ”と差し出す神経は理解の外にある。
ただ、面白かったのが斎藤慶子と南野陽子の方言ネイティヴ・スピーカー対決(笑)。東映でしか絶対出来ないエゲツなさ全開の応酬で、東京のモンにはわからない異様な熱気が画面に横溢する。この良さがわかるのは地方出身者の特権かもしれない(意味不明 ^^;)。