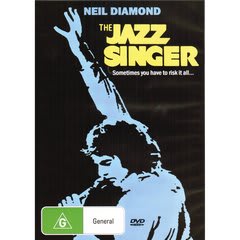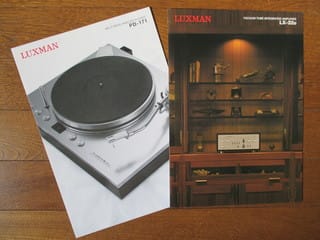(原題:Le fils de l'autre)話が御都合主義的に進むのは、似たようなネタを扱った是枝裕和監督の「そして父になる」と同じだ。そして、それが作品の瑕疵になっていないことも共通している。
テルアビブに住む18歳のユダヤ人の少年ヨセフは、兵役検査で不合格になる。両親との血液型が一致しないというのだ。調べてみると、同じ病院で同じ日に生まれたヨルダン川西岸に暮らすパレスチナ人の少年ヤシンと、出生の際に取り違えられたことが明らかになる。ヨセフとヤシン、そしてそれぞれの家族は、大きな苦難に直面することになる。
監督はユダヤ系フランス人のロレーヌ・レヴィ。舞台がイスラエルで、取り違えられたのがユダヤ人とパレスチナ人。しかも18年の月日が流れている。さらには、信教の問題もある。ヨセフはラビ(ユダヤ教の聖職者)に相談するものの、ラビは“改宗するしかないだろう”という言葉しか返せない。なぜなら、ユダヤ教は単なる宗教ではなく、ユダヤ人のアイデンティティだからだ。
しかし、この映画の設定は主人公達にとって好都合に出来ている。ヨセフの父は軍人で、子供に対する躾は厳しいが、一方で面倒見はとても良い。母親はフランス生まれで、リベラルな考えを持ち合わせている。ヤシンの父は今は不遇な立場だが、元々は腕の良いエンジニアだ。母親も典型的な良妻賢母タイプ。つまりは、どちらの両親もマトモな人物なのだ。
父親同士がイスラエルの政策を巡って口論になったり、ヤシンの兄が拗ねたりするが、それが後々尾を引くような重大なトラブルに繋がることはない。何より、当の二人がともに気の良い若者であり、打ち解けるまでにそう時間は掛からなかったりする。誰がどう見たってこれは“ラッキーなケース”だと思うだろう。
ただし“話が出来すぎているから、事の重大さが十分に伝わらない!”と指摘するのも野暮だ。作者は殊更にシビアなタッチを打ち出すことなど、最初から不要であると判断している。これは送り手が、登場人物達を信じ、人間を信じ、そして世の中を信じていることの証である。さらには、混迷するパレスチナ情勢も必ず解決し、必ず平和に暮らせる日が来ると信じている。この徹底したポジティヴ思考が映画のテーマに一本芯を通し、小賢しい批判をも跳ね返す力強さを与えたといえよう。
キャストは皆好演。特にヨセフの母親を演じるエマニュエル・ドゥヴォスの深い人間性を表現するパフォーマンスには感心した。2012年の東京国際映画祭で大賞と監督賞を受賞。見応えのある佳編である。