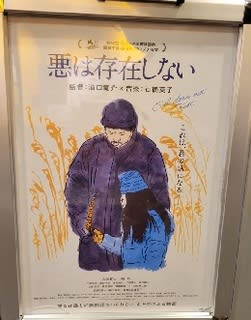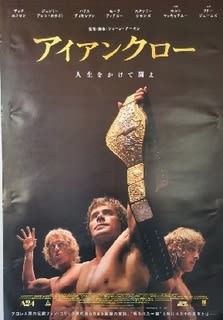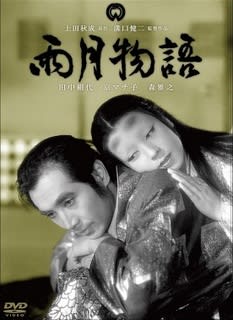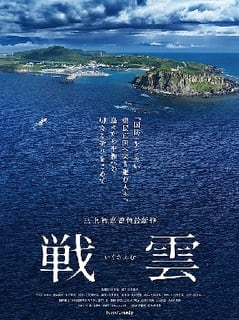(原題:RAPITO)これが史実であることに驚くしかない。西欧における宗教、あえて言えば一神教が掲げる価値観(教義)と、それがもたらす影響力について思い知らされる一編だ。さらにはその“原理主義”とも言える教えと、一般市民の普遍的な哀歓との確執をも掬い取っているあたりも、映画が平板な出来になることを巧みに防いでいる。観る価値はあると思う。
1858年、イタリア北部のボローニャのユダヤ人街に居を構えるモルターラ家に、突如として教皇ピウス9世の命を受けた兵士たちが押し入り、7歳になる息子のエドガルドを連れ去ってしまう。何でも、エドガルドは赤ん坊の頃に洗礼を受けたらしく、ユダヤ教徒の家庭で育てることは出来ないので教会側で引き取るとのことだ。納得出来ない両親は世論やユダヤ人社会の後押しを得て教皇庁と対峙するが、申し入れを受ければ教会の権威が失墜すると考える教皇はエドガルドの返還に応じようとしない。やがてイタリア王国が成立し、時代の流れは教会の立場を微妙なものにしていく。
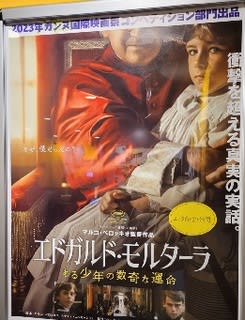
エドガルドが洗礼を受けることになった原因は、心情的には理解できるものである。もちろん両親の気持ちも分かる。そして幼くして親元から引き離されたエドガルド自身の悩みも映画はカバーしている。しかし、そんな彼らの平易な思いに、宗教は何ら寄り添うことは無い。偏狭な一神教の教義が権威を生み、それが社会全体の硬直化に繋がる。当然ながら作者は宗教そのものを糾弾するつもりは無い。ただ、エドガルドが長じてカトリック側の人間になっていくプロセスや、同時に教皇への複雑な思いが蓄積する様子などが描かれることにより、宗教との板挟みになってしまった者の苦悩を描き出している点は評価して良い。
もっとも、後半のクーデターによって政変が起きるくだりは効果的に表現されていない。まあ、戦闘シーンを再現するほどの予算規模ではなかったと思われるが、もうちょっと力を入れた方が盛り上がっただろう。撮り方次第で、ある程度の工夫は出来たはずだ。
監督のマルコ・ベロッキオはドラマ運びは巧みで、登場人物たちの内面も上手くカバーしている。主人公の少年期を演じるエネア・サラと、青年になったエドガルドに扮したレオナルド・マルテーゼは妙演。教皇役のパオロ・ピエロボンも海千山千ぶりを発揮している。そして何といっても、フランチェスコ・ディ・ジャコモのカメラによる奥行きの深い映像が素晴らしい。歴史好きならば要チェックだ。
1858年、イタリア北部のボローニャのユダヤ人街に居を構えるモルターラ家に、突如として教皇ピウス9世の命を受けた兵士たちが押し入り、7歳になる息子のエドガルドを連れ去ってしまう。何でも、エドガルドは赤ん坊の頃に洗礼を受けたらしく、ユダヤ教徒の家庭で育てることは出来ないので教会側で引き取るとのことだ。納得出来ない両親は世論やユダヤ人社会の後押しを得て教皇庁と対峙するが、申し入れを受ければ教会の権威が失墜すると考える教皇はエドガルドの返還に応じようとしない。やがてイタリア王国が成立し、時代の流れは教会の立場を微妙なものにしていく。
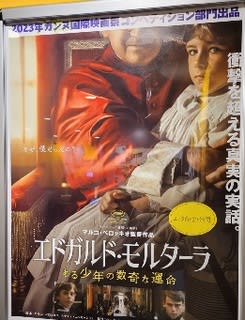
エドガルドが洗礼を受けることになった原因は、心情的には理解できるものである。もちろん両親の気持ちも分かる。そして幼くして親元から引き離されたエドガルド自身の悩みも映画はカバーしている。しかし、そんな彼らの平易な思いに、宗教は何ら寄り添うことは無い。偏狭な一神教の教義が権威を生み、それが社会全体の硬直化に繋がる。当然ながら作者は宗教そのものを糾弾するつもりは無い。ただ、エドガルドが長じてカトリック側の人間になっていくプロセスや、同時に教皇への複雑な思いが蓄積する様子などが描かれることにより、宗教との板挟みになってしまった者の苦悩を描き出している点は評価して良い。
もっとも、後半のクーデターによって政変が起きるくだりは効果的に表現されていない。まあ、戦闘シーンを再現するほどの予算規模ではなかったと思われるが、もうちょっと力を入れた方が盛り上がっただろう。撮り方次第で、ある程度の工夫は出来たはずだ。
監督のマルコ・ベロッキオはドラマ運びは巧みで、登場人物たちの内面も上手くカバーしている。主人公の少年期を演じるエネア・サラと、青年になったエドガルドに扮したレオナルド・マルテーゼは妙演。教皇役のパオロ・ピエロボンも海千山千ぶりを発揮している。そして何といっても、フランチェスコ・ディ・ジャコモのカメラによる奥行きの深い映像が素晴らしい。歴史好きならば要チェックだ。