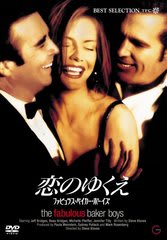黒澤明監督1960年作品。お馴染みの黒澤御大の“小役人罵倒、愚民差別”のスタンスが炸裂しており、力で迫る演出で一応楽しめるのだけど、他の傑作群と比べてイマイチ感銘度が薄いのは、焦点が定まらず余計なシーンが目に付くからであろう。
土地開発公団の副総裁の娘の結婚式で思いがけないハプニングが起こったのを皮切りに、庁舎新築にからまる不正入札事件をめぐる不可解な出来事が頻発する。差出人不明の密告状を受け取った検察当局が動き出すが、連重要参考人の自殺や失踪が相次ぎ、真相はなかなか掴めない。そんな中、くだんの娘の夫になる副総裁の秘書は独自の捜査に乗り出す。
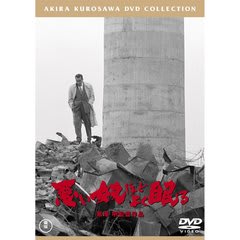
汚職の巨魁であるべき公団副総裁の上に、庶民がとても近づくこともできない“黒幕”を置いてしまっては、主人公の努力も何やら最初から徒労に終わりそうで、娯楽作としてはしっくりこない。各エピソードの扱いも総花的で、メリハリに欠ける。
主演の三船敏郎をはじめ、加藤武や森雅之、志村喬、西村晃、香川京子とキャストは多彩だが、それぞれの芝居にちょっとクサさを感じる瞬間もある。でもまあ、三船の存在感はさすがだった(田中邦衛のヒットマンも笑えたけど ^^;)。
土地開発公団の副総裁の娘の結婚式で思いがけないハプニングが起こったのを皮切りに、庁舎新築にからまる不正入札事件をめぐる不可解な出来事が頻発する。差出人不明の密告状を受け取った検察当局が動き出すが、連重要参考人の自殺や失踪が相次ぎ、真相はなかなか掴めない。そんな中、くだんの娘の夫になる副総裁の秘書は独自の捜査に乗り出す。
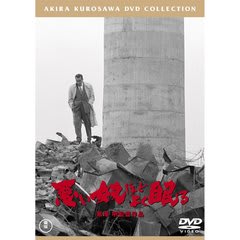
汚職の巨魁であるべき公団副総裁の上に、庶民がとても近づくこともできない“黒幕”を置いてしまっては、主人公の努力も何やら最初から徒労に終わりそうで、娯楽作としてはしっくりこない。各エピソードの扱いも総花的で、メリハリに欠ける。
主演の三船敏郎をはじめ、加藤武や森雅之、志村喬、西村晃、香川京子とキャストは多彩だが、それぞれの芝居にちょっとクサさを感じる瞬間もある。でもまあ、三船の存在感はさすがだった(田中邦衛のヒットマンも笑えたけど ^^;)。