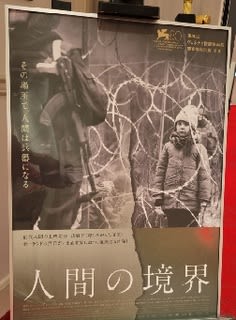(原題:BREWSTER'S MILLIONS )86年作品。まず驚いたのが、このライトなコメディがウォルター・ヒル監督の手によるものであることだ。同監督はそれまで「ザ・ドライバー」(78年)や「48時間」(82年)「ストリート・オブ・ファイヤー」(84年)などのハードなアクション編を次々とモノにしていて、そっち方面での俊英と見られていた。ところが、ここにきてまさかの新境地開拓。何とも器用な作家である。
マイナーリーグのハッケンサック・ブルズ所属の投手モンティ・ブルースターは、ある晩相棒のスパイク・ノーランと酒場で相手チームの選手たちと大ゲンカし、あっさりクビを言い渡される。失意のモンティの元に、顔さえ知らなかった石油成金の大叔父が3億ドルの遺産を残して逝去したとの連絡が届く。そしてモンティが3億ドルを手にするには条件があり、それは30日間で3千万ドルをすべて使い切れというもの。ただし1ドルでも残したら3億ドルの遺産はすべて白紙になる。しかもこの大乱費のの理由を誰にも打ち明けてはならない。かくして、アホらしくも痛快な“30日間3千万ドル大乱費”がスタートする。
いくら無駄遣いが大好きな小市民でも(笑)、30日間で日本円にして数十億円を全額溶かすというのは至難の業である。モンティはスパイクを副社長にして破産するための会社を作る。ところが、ロクでもない投資で逆に儲かってしまうのだ。それでもカネの力でメジャーリーグと試合して長年の夢を叶えるが、やがて最大のムダ使いはこれだとばかりに市長選に立候補する。
W・ヒルの演出はいつもの活劇編と同様にテンポが良く、次から次と舞い込む“逆境”に徒手空拳で立ち向かうモンティの奮闘を面白おかしく見せる。冒頭の、グラウンドを列車が横切って試合中断になるというマイナーリーグを茶化したギャグから、二転三転するラストのオチまで好調だ。
主演のリチャード・プライヤーは当時売れっ子の喜劇役者で、スパイク役のジョン・キャンディと共にお笑い場面の創出には余念が無い(この2人は若くして世を去ってしまったのが残念だ)。ロネット・マッキーにスティーヴン・コリンズ、ヒューム・クローニンといった脇の面子も申し分ない。
なお、本作を観て思い出したのが、テレンス・ヒル主演の「Mr.ビリオン」だ。莫大な遺産を総額するために厄介な条件を期限までにクリアする必要があるという基本プロットは同じ。こちらは77年製作だからネタとしては古いのだが、「マイナーブラザーズ」自体が1961年に作られた「おかしなおかしなお金持ち」(日本未公開)のリメイクなので、この題材は昔からあるのかもしれない。