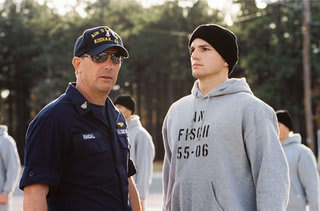(原題:Heat)96年作品。音楽でも演劇でもそうなのだが、大物2人が競演したとして、それが単純に1+1=2になるとは限らないのが世の常なのだ。ヘタすると1+1がマイナスなる場合も少なくない。この映画、ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノとの初の共演(「ゴッドファーザーPART2」では出番が違っていた)で封切り当時は話題を振りまいたクライム・アクションだが、2人の大物を動かす演出家は彼ら以上のキレ者でなければならないことは言うまでもない。しかし・・・・。
マイケル・マンは一流の監督ではない。「ラスト・オブ・モヒカン」などという駄作もあるが、しょせん“ちょっとクセのあるTV出身の映画屋”だ。大物2人に対して何ができるというのだ。
この映画のダメな点は、意味もないのに長いことだ。主人公2人の私生活などの状況説明が不必要に多い。デ・ニーロの恋人をめぐるエピソードとか、パチーノの娘(ナタリー・ポートマン)の自殺未遂騒動なんてカットしてよろしい。パチーノ刑事が、デ・ニーロ一味を尾行捜査する場面も不要。ラストの飛行場での追っかけシーンは緊張感もないのにやたら長い。
そして話題になった喫茶店で2人が対峙する場面。公開当時に某週刊誌が、実は2人は“共演”していない、と指摘した点だけど、ワザとらしい画面合成でそれも事実かもしれないと思った。しかしそれ以上に、高揚感も迫力もない凡庸なカット割りの連続にアクビさえ出てしまう。セリフ廻しも最悪で、何のための共演か全然わかっていない。
要するにこの監督、2人に遠慮してしまったのだ。無難な素材と演出で出演者と余計な摩擦を起こさないように振る舞っただけなのだ。加えてこの監督の唯一の持ち味である“意味もなく暗いタッチ”が全篇を覆い、結果として死ぬほど長い3時間に観客を付き合わせることになる。これじゃダメだ。
対してヴァル・キルマー扮するデ・ニーロの子分のエピソードや、銀行強盗に急遽加わった前科者の黒人の描き方にはちょっと突っ込めば面白くなった可能性もある。でも今から何言っても無駄だ。
2人と大喧嘩してでも自分の映像に固執するような作家を持って来るべきだった。さらに、興行のためには無駄なシーンを容赦なく切り捨てる冷徹なプロデューサーを起用するべきだった(製作もM・マンが担当)。今どき“映画史上最長の壮絶な銃撃戦シーン”なんてキャッチフレーズの範疇にも入らないぞ。“退屈な凡作”として片付けてしまおう。



マイケル・マンは一流の監督ではない。「ラスト・オブ・モヒカン」などという駄作もあるが、しょせん“ちょっとクセのあるTV出身の映画屋”だ。大物2人に対して何ができるというのだ。
この映画のダメな点は、意味もないのに長いことだ。主人公2人の私生活などの状況説明が不必要に多い。デ・ニーロの恋人をめぐるエピソードとか、パチーノの娘(ナタリー・ポートマン)の自殺未遂騒動なんてカットしてよろしい。パチーノ刑事が、デ・ニーロ一味を尾行捜査する場面も不要。ラストの飛行場での追っかけシーンは緊張感もないのにやたら長い。
そして話題になった喫茶店で2人が対峙する場面。公開当時に某週刊誌が、実は2人は“共演”していない、と指摘した点だけど、ワザとらしい画面合成でそれも事実かもしれないと思った。しかしそれ以上に、高揚感も迫力もない凡庸なカット割りの連続にアクビさえ出てしまう。セリフ廻しも最悪で、何のための共演か全然わかっていない。
要するにこの監督、2人に遠慮してしまったのだ。無難な素材と演出で出演者と余計な摩擦を起こさないように振る舞っただけなのだ。加えてこの監督の唯一の持ち味である“意味もなく暗いタッチ”が全篇を覆い、結果として死ぬほど長い3時間に観客を付き合わせることになる。これじゃダメだ。
対してヴァル・キルマー扮するデ・ニーロの子分のエピソードや、銀行強盗に急遽加わった前科者の黒人の描き方にはちょっと突っ込めば面白くなった可能性もある。でも今から何言っても無駄だ。
2人と大喧嘩してでも自分の映像に固執するような作家を持って来るべきだった。さらに、興行のためには無駄なシーンを容赦なく切り捨てる冷徹なプロデューサーを起用するべきだった(製作もM・マンが担当)。今どき“映画史上最長の壮絶な銃撃戦シーン”なんてキャッチフレーズの範疇にも入らないぞ。“退屈な凡作”として片付けてしまおう。