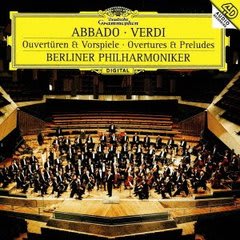(原題:ENGLISH VINGLISH)これは面白い。ヒロインの成長物語を、インド製娯楽映画にありがちな“大雑把な作劇”を廃し、観る者の共感を呼べるように丁寧に仕上げている。しかも、ちゃんとインド映画のツボを押さえたエンタテインメント性も確保されており、いたずらに“グローバリズム”だの“芸術性”だのといった次元に走っていない。まさに大人の映画作りだ。
インドの地方都市で暮らすシャシは、料理が得意で子供達の面倒見も良い“理想の”専業主婦なのだが、家族の中で唯一英語が話せない。そのために肩身の狭い思いをしている。そんな時、ニューヨークに住む姉の娘が結婚するという知らせを受け、シャシは手伝いも兼ねて式の1か月以上前から単身渡米する。案の定、そこでも英語が話せずに思い通りにならないことばかり。
ところがある日“4週間で英語が話せる”という英会話教室の広告を見つけた彼女は、こっそりと英語をマスターしようと思い立つ。その教室にはさまざまな国から来た老若男女が集まっており、シャシは英語を学ぶと共に彼らと知り合うことによって、自分の世界が広がっていくのを実感する。
この映画のミソは“英語がしゃべれることがグローバルな人材になる必須条件であり、主人公はそれを達成したから事態は好転した”などというナイーヴすぎる図式を捨象していることである。彼女の願いは、まず家族とより良いコミュニケーションを取ることだ。英会話教室に集う仲間達も、グローバルに活躍して成功したいといった大それた希望は持っていない。ただ周囲の人々と意思疎通を図りたいだけなのだ。
もちろん、シャシを取り巻いていた環境にはインド社会特有の保守性が影を落としていたことは間違いない。しかし、映画はそれに真っ向から対峙してフェミニズムなんかに舵を切ることは無い。英語をマスターすることで、ささやかながら主婦としての自信を取り戻し、改めて家族と地域文化の素晴らしさを実感するという、極めて良識的で抑制の効いた地点に着地させようとしている。このあたりの作者のスタンスは、実にクレバーだ。
ウリ・シンディーの演出は理性的でソツがない。大々的な歌と踊りは出てこないが(笑)、ヒロインの内面を照射するような楽曲を数多くバックに流すなど、長い上映時間を飽きさせずに見せきっている。
そして特筆すべきは、ニューヨークの街が魅力的に捉えられていることだ。ゴミゴミとした裏通りや剣呑な連中がうろつく地域はまったく映さず、観光名所を含めたこの街の美景を効果的に綴っているだけなのだが、観る者にとっては一度は住みたくなるほど、素敵に描かれている。また、ヒロインを取り巻く市井の人々が皆親切であるのも気持ちが良い。
主演の(国民的女優と言われる)シュリデヴィは50代とは思えぬ若さと美しさ、そして気品を保持しており、特に優雅な身のこなしには見とれるばかり。劇中で年下のフランス男から惚れられるのも当然だろう。披露宴でのヒロインの感動的なスピーチも含めて、鑑賞後の印象は極上と言える。観て損は無い。