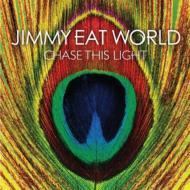(原題:Vier Minuten)かなりの求心力を持った映画だと思う。主人公は、ピアノ一筋に生きて昔はフルトヴェングラーからもその才能を認められたほどの腕前だったが、気が付けば家庭を築くなどの人並みの幸せを掴めないまま老境に至ってしまった女性ピアノ教師。そんな彼女がドイツの刑務所で出会ったのが殺人犯として服役している若い娘。粗暴極まりない性格だが、ピアノの腕だけは天才的だ。
荒みきった若者の心が優秀な師匠と芸術の力によって良い方向へ導かれる・・・・という、ありがちなアウトラインを持つ本作は、同類の筋書きを持つ凡百の映画とは比べものにならないほどのヴォルテージの高さを誇っている。
この二人はピアノが好きという共通点のみで接近するのだが、当初は相手のことなんか何とも思っていないように描かれる。教師が興味があるのは娘の才能だけ。娘はピアノを弾くことしか関心がない。そんな二人が理解し合えるようになるには、ハリウッド映画のような御為ごかしの予定調和など最優先で排除しなければならない。
映画はそれぞれの過去、しかも二人がなぜそんな気難しい人間になったかを、小出しにかつ容赦なく(効果的に)描出する。教師側の若い頃のエピソード、ドイツ敗戦間近の野戦病院で看護婦をしていた彼女が体験する悲惨な出来事は、観ていてまるで身を切られるようだ。彼女の人生はそこでいったん“終わった”かのように思われる。年を取ってから今回ようやく自分の全才能を賭けて向き合える対象を見つけるまでの間、彼女はその空虚な心を抱いたまま長い時間を過ごしてきたのだ。その痛切さが十分伝わってくる。
娘の方も、かつては天才少女ピアニストとして評価されてきた逸材だが、養父からの性的虐待及びそれを契機として悪い仲間と付き合い始めたため、犯罪に手を染めてしまう(無罪であることも暗示させるが)。
そんな二人のレッスンは、まるで戦争だ。本音がぶつかり合うバトルの末、ようやく連帯感らしきものを会得するが、それはまた綱渡りのような危なっかしさをも内包している。二人の戦いは映画が終わってからもずっと続く・・・・そんな一筋縄ではいかない人間模様を、ドイツの俊英クリス・クラウス監督は骨太な筆致で浮き彫りにする。
若い娘を演じるハンナー・ヘルツシュプルングは、ハッキリ言って凄い。全身これ攻撃性の塊だ。登場早々に看守を半殺しにするのを手始めに、程度を知らない暴力を横溢させる。見ているだけでスリル満点だ。老教師役のモニカ・ブライブトロイも頑迷さと苦悩を滲ませた、奥行きの深い演技で迎え撃つ。二人とも今年度の外国映画の中では屈指のパフォーマンスだ。
先日観た「僕のピアノコンチェルト」も音楽の使い方に感心したが、本作はさらに堂に入っている。ベートーヴェンやシューマン、モーツァルトのお馴染みの名曲はもちろん、ロックやジャズのテイストを大胆に取り入れたアネッテ・フォックスの音楽が素晴らしい効果をあげている。特に題名になっているラスト4分間のヒロインの演奏は、まさに激烈と言うしかなく、この部分だけでも十分入場料のモトは取れるだろう。鮮やかな幕切れを含めて、観る価値十分の秀作と言える。